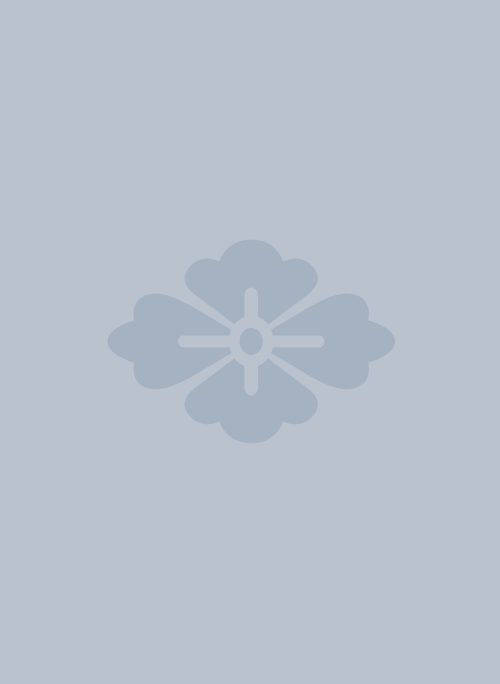「……うー」
ショーまで後僅かとなったある日、ルルはショーに出るための衣装をあれこれ着替えさせられていた。
このサーカスで数少ない女性のエルフは、無表情でルルの前に服を合わせていく。
他のエルフも会話を返してくれても、決して話が弾むわけではない。
事務的なものが多く、ルルは寂しさを感じていた。
そう考えると、まともに感情表現出来ているのは、エルフの少年くらいだ。
しかし、仲は良くないので、未だに彼の名前を呼ぶ気にはなれない。
「……これで良いですか?」
「えーと、お腹が出てないのが良いかな」
ここの気候はいつも暑いので、布は薄い素材の物が多いが、ルルはやたらお腹の出ている服は苦手だった。
お腹を冷やしてはいけないらしいし、何より太ったりしたら嫌でも目立つ。
団長みたいに、ズボンに出っ張ったお腹が乗っかるようにだけはなりたくない。
だが、ここに来てから、ルルはまともな食事など殆ど与えられてないにも等しいので、太りようがないが。
飢え死にしない程度には食事をもらえるが、味の薄いものが多くて、あまり食べた気にならない。
団長は、商品としての価値がある幻獣には、それなりに食事を与えるようにしているが。
「ご主人様には、なるべく派手なものをと言われております」
「……じゃあ、これでいい」
赤と黄色のチョッキと赤いスカート。お腹が出ているのは気になるが、ラッドの肌と同じ色なので、まぁいいかと納得することにした。
エルフや母みたいに綺麗だったら、もっと堂々と出来たのだが。
「では、私はこれで」
「うん、どうもありがとう!」
お礼を言って見送ると、ルルはラッドの元へ向かう。
途中通った幻獣の部屋で、何時ものようにエルフの少年から嫌味を言われ、ムカムカとしたが。
だが、ラッドの姿を見ると、そのムカムカは吹き飛んだ。
ラッドは人の言葉を話さないが、馬鹿にしたりはけしてしない。
だから、ラッドの前でルルはくるっとターンをした。
「これ、どうかな?やっぱり派手だよね」
派手な服でなければ、霞んでしまうのだから仕方がないが。
ラッドは意味が分かってないのか、檻に鼻先を擦り寄せている。
「……もうすぐだね」
ショーの日に、果たしてラッドと自分は上手く演義を出来るだろうか?
他の幻獣達と合わせようとしたが、ラッドはラッドで別に出てもらうと団長に言われ、ルルは結局、ラッドと幻獣達を一緒に遊ばせてあげることが出来なかった。
今、ラッドには自分だけ。そして、ルルにはラッドだけしか心を開ける相手が、笑顔を見せる相手がいないのだ。
その事が、少し胸に刺さるのを感じながら、ルルはラッドに抱き着いた。
檻越しから伝わるラッドの体温の温かさに、何故か泣きたくなる。
「……頑張ろうね。ラッド」
『ウォン』
ショーまで後僅かとなったある日、ルルはショーに出るための衣装をあれこれ着替えさせられていた。
このサーカスで数少ない女性のエルフは、無表情でルルの前に服を合わせていく。
他のエルフも会話を返してくれても、決して話が弾むわけではない。
事務的なものが多く、ルルは寂しさを感じていた。
そう考えると、まともに感情表現出来ているのは、エルフの少年くらいだ。
しかし、仲は良くないので、未だに彼の名前を呼ぶ気にはなれない。
「……これで良いですか?」
「えーと、お腹が出てないのが良いかな」
ここの気候はいつも暑いので、布は薄い素材の物が多いが、ルルはやたらお腹の出ている服は苦手だった。
お腹を冷やしてはいけないらしいし、何より太ったりしたら嫌でも目立つ。
団長みたいに、ズボンに出っ張ったお腹が乗っかるようにだけはなりたくない。
だが、ここに来てから、ルルはまともな食事など殆ど与えられてないにも等しいので、太りようがないが。
飢え死にしない程度には食事をもらえるが、味の薄いものが多くて、あまり食べた気にならない。
団長は、商品としての価値がある幻獣には、それなりに食事を与えるようにしているが。
「ご主人様には、なるべく派手なものをと言われております」
「……じゃあ、これでいい」
赤と黄色のチョッキと赤いスカート。お腹が出ているのは気になるが、ラッドの肌と同じ色なので、まぁいいかと納得することにした。
エルフや母みたいに綺麗だったら、もっと堂々と出来たのだが。
「では、私はこれで」
「うん、どうもありがとう!」
お礼を言って見送ると、ルルはラッドの元へ向かう。
途中通った幻獣の部屋で、何時ものようにエルフの少年から嫌味を言われ、ムカムカとしたが。
だが、ラッドの姿を見ると、そのムカムカは吹き飛んだ。
ラッドは人の言葉を話さないが、馬鹿にしたりはけしてしない。
だから、ラッドの前でルルはくるっとターンをした。
「これ、どうかな?やっぱり派手だよね」
派手な服でなければ、霞んでしまうのだから仕方がないが。
ラッドは意味が分かってないのか、檻に鼻先を擦り寄せている。
「……もうすぐだね」
ショーの日に、果たしてラッドと自分は上手く演義を出来るだろうか?
他の幻獣達と合わせようとしたが、ラッドはラッドで別に出てもらうと団長に言われ、ルルは結局、ラッドと幻獣達を一緒に遊ばせてあげることが出来なかった。
今、ラッドには自分だけ。そして、ルルにはラッドだけしか心を開ける相手が、笑顔を見せる相手がいないのだ。
その事が、少し胸に刺さるのを感じながら、ルルはラッドに抱き着いた。
檻越しから伝わるラッドの体温の温かさに、何故か泣きたくなる。
「……頑張ろうね。ラッド」
『ウォン』