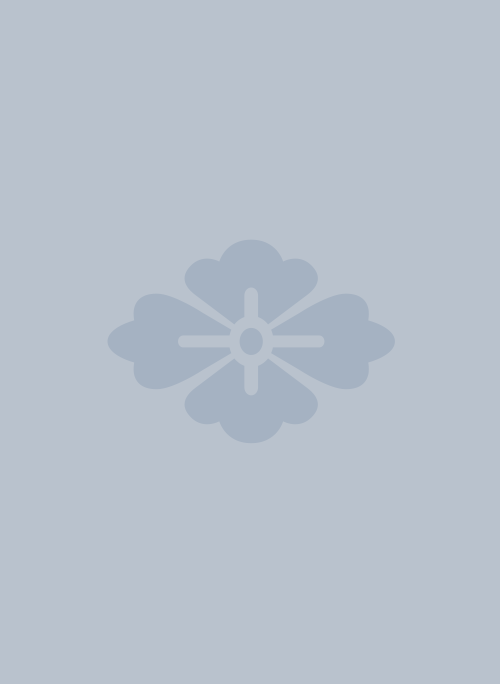新聞の裏に、手書きでカリカリと文字を綴っていく。
(君は、真実に近付いている。君の心の真実にね。……そう仕向けたのは僕だけど)
しかし、彼女が気持ちを自覚したとして、それを素直に表に出すとは思えない。
(それに、やっぱり君を受け入れられるのは、僕だけだよ。だって、君は僕と同じだから。助手君じゃ君には眩しすぎる)
同類だからこそ、理解しあえる。フランツはそう思ったからアマネの心を欲した。
(ウィル君はいい人だけど、彼には君の過去を受け止めきれるかな?)
アマネを否定したりはしないだろう。けれども、優しすぎる彼に、アマネの過去を受け止めることは出来るだろうか?
「どちらにしても、そろそろ動かないとね」
フランツはフッと小さく笑うと、帽子を被り外へ出た。
「……パターンが同じですね」
「は?何が?」
アマネの呟きに、ウィルが首を傾げると、広げていた新聞をウィルへと差し出す。
「裏の一番下の左端を読んでください」
「えーと……『今日午後二時に、ベーカー街のカフェに来てね。Fから愛しのAへ』…………ってなんじゃこりゃ!!」
読み上げたことを後悔するウィルを見ながら、アマネは心の中でため息を吐いた。
(何のつもりか分かりませんが。……けれども、丁度良いかもしれません)
フランツに、確認しておきたいことがあったのだ。出来れば、彼が本格的に動く前に。
「と言う訳ですので、私は出掛けてきますね」
「………ああ」
「?……止めないんですか?」
フランツ相手に過剰に反応する様子がなかったので、アマネは訝しげな視線を送る。
すると、ウィルは笑った。
「別に、俺がどうこう言うことじゃないだろ?俺はお前の助手なんだし。あいつがお前に危害を加えなきゃ、俺が止める理由はねぇよ」
(それに、お前は俺の気持ちを知らないからな。まだ、知られたくもねぇし)
アマネがフランツをどう思ってるかは分からない。だが、フランツは少なくとも本気だろう。
アマネは母親に愛情を求める子供と例えたが、フランツは子供ではない。
一人の男だ。それをアマネは分かっているのだろうか?
「気を付けてけよ」
「……はい。行ってきます」
アマネは何時もの服装で、髪を後ろに束ねて出掛けた。
まるで、仕事にでも行くようだなとウィルは苦笑し、それからこそこそと身支度を済ます。
(いや、ほら、気になる訳じゃねぇけど、この前みたいになると大変だし、念のためな……決して覗きじゃない)
誰に言い訳をしているのか、ウィルは心の中で早口に言うと、外へと出た。
尾行はくれぐれも気を抜かないようにしなければ。なんせ勘の良い人間が二人もいるのだから。
(君は、真実に近付いている。君の心の真実にね。……そう仕向けたのは僕だけど)
しかし、彼女が気持ちを自覚したとして、それを素直に表に出すとは思えない。
(それに、やっぱり君を受け入れられるのは、僕だけだよ。だって、君は僕と同じだから。助手君じゃ君には眩しすぎる)
同類だからこそ、理解しあえる。フランツはそう思ったからアマネの心を欲した。
(ウィル君はいい人だけど、彼には君の過去を受け止めきれるかな?)
アマネを否定したりはしないだろう。けれども、優しすぎる彼に、アマネの過去を受け止めることは出来るだろうか?
「どちらにしても、そろそろ動かないとね」
フランツはフッと小さく笑うと、帽子を被り外へ出た。
「……パターンが同じですね」
「は?何が?」
アマネの呟きに、ウィルが首を傾げると、広げていた新聞をウィルへと差し出す。
「裏の一番下の左端を読んでください」
「えーと……『今日午後二時に、ベーカー街のカフェに来てね。Fから愛しのAへ』…………ってなんじゃこりゃ!!」
読み上げたことを後悔するウィルを見ながら、アマネは心の中でため息を吐いた。
(何のつもりか分かりませんが。……けれども、丁度良いかもしれません)
フランツに、確認しておきたいことがあったのだ。出来れば、彼が本格的に動く前に。
「と言う訳ですので、私は出掛けてきますね」
「………ああ」
「?……止めないんですか?」
フランツ相手に過剰に反応する様子がなかったので、アマネは訝しげな視線を送る。
すると、ウィルは笑った。
「別に、俺がどうこう言うことじゃないだろ?俺はお前の助手なんだし。あいつがお前に危害を加えなきゃ、俺が止める理由はねぇよ」
(それに、お前は俺の気持ちを知らないからな。まだ、知られたくもねぇし)
アマネがフランツをどう思ってるかは分からない。だが、フランツは少なくとも本気だろう。
アマネは母親に愛情を求める子供と例えたが、フランツは子供ではない。
一人の男だ。それをアマネは分かっているのだろうか?
「気を付けてけよ」
「……はい。行ってきます」
アマネは何時もの服装で、髪を後ろに束ねて出掛けた。
まるで、仕事にでも行くようだなとウィルは苦笑し、それからこそこそと身支度を済ます。
(いや、ほら、気になる訳じゃねぇけど、この前みたいになると大変だし、念のためな……決して覗きじゃない)
誰に言い訳をしているのか、ウィルは心の中で早口に言うと、外へと出た。
尾行はくれぐれも気を抜かないようにしなければ。なんせ勘の良い人間が二人もいるのだから。