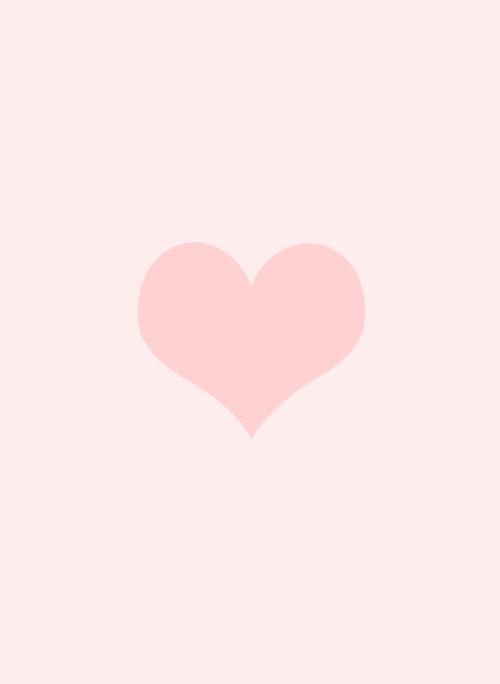「私の家ではこれをシチューと言って食べていました!
正確に言えば、濃いシチューってお父さんが言ってました!」
愛菜は強めに答えた。
濃いシチュー…
確かに濃いシチューだけど…
僕は作り方がよく分からないが行程は同じで色だけ違うのか?
黙り込んで考えてしまった。
「恭也さん?」
愛菜の顔を見て
ビーフシチューでもシチューでもどっちでも良くなった。
愛菜が僕のために作ってくれたのだから。
だけど…
「愛菜、これはビーフシチューって言うんだよ。
確かに濃いシチューという愛菜もあっているかもしれない。」
「そーなんですか…
物知らずですみません。」
「愛菜、謝らなくていいんだよ。
これで愛菜は1つ物事を覚えられた。偉いぞ。」
愛菜は照れるように笑った。
僕の常識は君には通用しない。
そんな君が愛おしい。