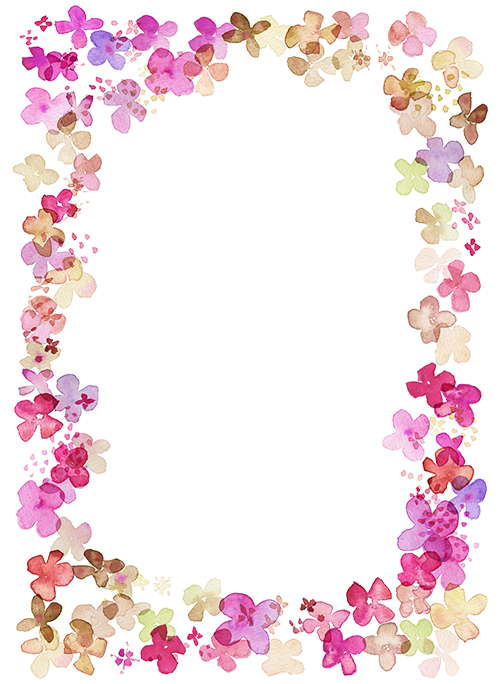じっと包まれながら、
わたしは、不思議な感覚に
陥っていた。
あるはずのない、感覚。
でも、この温もりを
どこかで体験したかのような、
既視感に、戸惑っていた。
親でもなく、
ホームの誰かでもなく、
璃子でもない…
モヤがかかって見えない
誰かに。
その時…
回された腕が、解かれて
「困らせて、ごめんな。
びっくりさせちまった…」
そう言った、桐生くんの瞳が
まだ儚げに揺れていて、
わたしの胸がキリキリと
締め上げられる。
これ以上、そんな顔を
見ていたくなくて、
わたしは、笑顔で首を振った。
「わたしは大丈夫。
桐生くんこそ、大丈夫?」
わたしは、背伸びして
桐生くんの眉間に寄せられた
皺を、指でほぐしてあげた。
突然、触れられたことによる
驚きなのか、桐生くんは
目を見開いて、見つめてきた。
「ごめんなさい!
急に触っちゃって…」
慌てて弁解した、わたしに
クスッと微笑んで、
「いや、ありがとな…」と、
優しい声色で、見つめる
桐生くんに、わたしも
笑顔で頷いた。
結局、ホームまで
送り届けてくれた、桐生くんは
別れ際には、笑顔を見せて
帰って行った。
その日の夜…
わたしは、不思議な夢を見た。
小学生の頃、遠足で行った
緑丘公園にいる夢。
小高い丘の上にある、
お気に入りの場所で、
わたしは、コスモスに囲まれた
ベンチに座っていて、
誰かと一緒に、寄り添って
ある約束をした。
とても幸せな時間…
そして、その誰かに
指輪を貰って、笑い合う。
そんな夢だった。
夢から覚めた、わたしは
右手の薬指で光る指輪を
見つめて、夢の中で貰った指輪も
こんな感じだったなと、
物思いにふけった、わたしは
ふと、思った。
そもそも、この指輪って
いつから持ってたっけ?
病室で、取り乱してしまった
くらいに大切な物だったのは
なんとなく、分かるけど…
自分で購入した覚えはないし、
こんな物を送ってもらう人も
わたしにはいない。
頭を捻りながら、考えるも
頭にモヤがかかったように、
何も思い出せない。
分かりそうで、分からない。
そんな気持ちを抱えたまま、
わたしは、学校に登校した。
授業中も、休み時間も、
ずっと指輪のことを考えて
気付けば、放課後になっていた。
「はあー…」
思わず出た、溜め息は
思いのほか、大きかったようで
璃子に不思議な目をされた。
「流羽、今日はどしたの?
ずっと溜め息ばっかしてるよ?」
「え?そんなに?
気づかなかった…
なんでもないんだけどね、
この指輪が、すごく気になって」
右手を上げて、璃子に
見せてみた。
「何が気になってるの?」
真剣に聞いてくれる璃子に、
不思議な夢を見たことや、
自分で買った覚えがないこと、
貰った覚えがないこと…
でも、とても大切な物だという
気持ちを打ち明けた。
それを聞いた璃子は、
少し考える素振りを見せて、
わたしを見つめた。
「病院の先生には、無理に
思い出させるのはダメって、
言われたけど…
流羽にとって、その指輪が
どれだけ大切なものなのかを
思い出す、きっかけになるかも
しれない。
流羽はどうしたい?」
真剣に問われて、
指輪に視線を落とした。
淡いピンク色の石が付いた、
可愛い指輪…
無いと落ち着かなくて、
あると、ホッとする
不思議な指輪。
どういう経緯を経て、この
薬指に収められたのか?
それが分かれば、何かが
大きく変わる気がした。
指輪から璃子へと、視線を移し
頷いた。
「わたし、知りたい…
知らなきゃいけない、
そんな気がするの」
「よしっ!そうと決まれば
あそこに、行かなくちゃ!」
あそこ?
首を傾げる、わたしに
璃子は、笑った。
そして、璃子に言われるまま
日曜日の昼下がりの駅前で
立ち尽くす、わたしの前に
現れたのは、桐生くんだった。
一歩ずつ近付いてくる
桐生くんに、わたしの心臓は
壊れそうなほど、
ドキドキしている。
目の前に立ち、わたしを
見下ろす、桐生くんは
平然とした感じで、
でも…
どこか、温かさを持った
瞳で見つめてきた。
なんで、桐生くんがここに?
今日は璃子と会う約束で、
ここに来た、わたし。
その時…
混乱するわたしの元に
一通のメールが届いた。
差出人は、璃子。
急いでメールを開くと、
『体調悪し。
桐生に頼んだから、
安心して、行っておいで!』
体調が悪いのは、仕方ないけど
それで、どうして
桐生くんに頼んだの!?
彼女さんがいるのに、
こうしてお休みの日に
2人で出掛けたら、
彼女さんに誤解されちゃうよ!
携帯を仕舞って、
大きく溜め息をついた。
「桐生くん…
来て貰って、悪いんだけど…
わたし、1人で大丈夫だから
彼女さんのところにでも
行ってあげて?
わたしと居たら、変な誤解
させちゃうから」
「いや、大丈夫。
2人でいること、知ってるから」
「え!?知ってるって…
話したの!?」
璃子も璃子だけど、
桐生くんも何を考えてるの?
そんなこと話したら、
彼女さんは、きっと今頃
気が気じゃないはずだよ…
それとも…
想い合って、信じ合ってるからこそ
送り出したのかな?
胸がチクっと痛んだ。
改めて、想いの深さを
見せられた気がして、
喉元から、迫り上がるものを
必死に堪える。
鼻の奥が、ツンとして
伝える事が許されないことが、
こんなにも苦しいなんて、
初めて知った…
「本当に、大丈夫だから
桐生くんは帰って?
璃子から、行く場所も
聞いてないから、どのみち
帰るだけだし」
俯いて話す、わたしの
頭に、大きくて温かいものが
乗せられた。
「大丈夫、どこに行くか
俺、知ってるから。
一緒に行こう」
わたしは無言で、首を振り続けた。
例えそうだとしても、
やっぱり…
「とにかく、行けば分かる」
そう言って、わたしの手を取って
駅の方へと、歩き出す
桐生くんの手は、
包み込むように、優しくて
温かかった。
わたしは、不思議な感覚に
陥っていた。
あるはずのない、感覚。
でも、この温もりを
どこかで体験したかのような、
既視感に、戸惑っていた。
親でもなく、
ホームの誰かでもなく、
璃子でもない…
モヤがかかって見えない
誰かに。
その時…
回された腕が、解かれて
「困らせて、ごめんな。
びっくりさせちまった…」
そう言った、桐生くんの瞳が
まだ儚げに揺れていて、
わたしの胸がキリキリと
締め上げられる。
これ以上、そんな顔を
見ていたくなくて、
わたしは、笑顔で首を振った。
「わたしは大丈夫。
桐生くんこそ、大丈夫?」
わたしは、背伸びして
桐生くんの眉間に寄せられた
皺を、指でほぐしてあげた。
突然、触れられたことによる
驚きなのか、桐生くんは
目を見開いて、見つめてきた。
「ごめんなさい!
急に触っちゃって…」
慌てて弁解した、わたしに
クスッと微笑んで、
「いや、ありがとな…」と、
優しい声色で、見つめる
桐生くんに、わたしも
笑顔で頷いた。
結局、ホームまで
送り届けてくれた、桐生くんは
別れ際には、笑顔を見せて
帰って行った。
その日の夜…
わたしは、不思議な夢を見た。
小学生の頃、遠足で行った
緑丘公園にいる夢。
小高い丘の上にある、
お気に入りの場所で、
わたしは、コスモスに囲まれた
ベンチに座っていて、
誰かと一緒に、寄り添って
ある約束をした。
とても幸せな時間…
そして、その誰かに
指輪を貰って、笑い合う。
そんな夢だった。
夢から覚めた、わたしは
右手の薬指で光る指輪を
見つめて、夢の中で貰った指輪も
こんな感じだったなと、
物思いにふけった、わたしは
ふと、思った。
そもそも、この指輪って
いつから持ってたっけ?
病室で、取り乱してしまった
くらいに大切な物だったのは
なんとなく、分かるけど…
自分で購入した覚えはないし、
こんな物を送ってもらう人も
わたしにはいない。
頭を捻りながら、考えるも
頭にモヤがかかったように、
何も思い出せない。
分かりそうで、分からない。
そんな気持ちを抱えたまま、
わたしは、学校に登校した。
授業中も、休み時間も、
ずっと指輪のことを考えて
気付けば、放課後になっていた。
「はあー…」
思わず出た、溜め息は
思いのほか、大きかったようで
璃子に不思議な目をされた。
「流羽、今日はどしたの?
ずっと溜め息ばっかしてるよ?」
「え?そんなに?
気づかなかった…
なんでもないんだけどね、
この指輪が、すごく気になって」
右手を上げて、璃子に
見せてみた。
「何が気になってるの?」
真剣に聞いてくれる璃子に、
不思議な夢を見たことや、
自分で買った覚えがないこと、
貰った覚えがないこと…
でも、とても大切な物だという
気持ちを打ち明けた。
それを聞いた璃子は、
少し考える素振りを見せて、
わたしを見つめた。
「病院の先生には、無理に
思い出させるのはダメって、
言われたけど…
流羽にとって、その指輪が
どれだけ大切なものなのかを
思い出す、きっかけになるかも
しれない。
流羽はどうしたい?」
真剣に問われて、
指輪に視線を落とした。
淡いピンク色の石が付いた、
可愛い指輪…
無いと落ち着かなくて、
あると、ホッとする
不思議な指輪。
どういう経緯を経て、この
薬指に収められたのか?
それが分かれば、何かが
大きく変わる気がした。
指輪から璃子へと、視線を移し
頷いた。
「わたし、知りたい…
知らなきゃいけない、
そんな気がするの」
「よしっ!そうと決まれば
あそこに、行かなくちゃ!」
あそこ?
首を傾げる、わたしに
璃子は、笑った。
そして、璃子に言われるまま
日曜日の昼下がりの駅前で
立ち尽くす、わたしの前に
現れたのは、桐生くんだった。
一歩ずつ近付いてくる
桐生くんに、わたしの心臓は
壊れそうなほど、
ドキドキしている。
目の前に立ち、わたしを
見下ろす、桐生くんは
平然とした感じで、
でも…
どこか、温かさを持った
瞳で見つめてきた。
なんで、桐生くんがここに?
今日は璃子と会う約束で、
ここに来た、わたし。
その時…
混乱するわたしの元に
一通のメールが届いた。
差出人は、璃子。
急いでメールを開くと、
『体調悪し。
桐生に頼んだから、
安心して、行っておいで!』
体調が悪いのは、仕方ないけど
それで、どうして
桐生くんに頼んだの!?
彼女さんがいるのに、
こうしてお休みの日に
2人で出掛けたら、
彼女さんに誤解されちゃうよ!
携帯を仕舞って、
大きく溜め息をついた。
「桐生くん…
来て貰って、悪いんだけど…
わたし、1人で大丈夫だから
彼女さんのところにでも
行ってあげて?
わたしと居たら、変な誤解
させちゃうから」
「いや、大丈夫。
2人でいること、知ってるから」
「え!?知ってるって…
話したの!?」
璃子も璃子だけど、
桐生くんも何を考えてるの?
そんなこと話したら、
彼女さんは、きっと今頃
気が気じゃないはずだよ…
それとも…
想い合って、信じ合ってるからこそ
送り出したのかな?
胸がチクっと痛んだ。
改めて、想いの深さを
見せられた気がして、
喉元から、迫り上がるものを
必死に堪える。
鼻の奥が、ツンとして
伝える事が許されないことが、
こんなにも苦しいなんて、
初めて知った…
「本当に、大丈夫だから
桐生くんは帰って?
璃子から、行く場所も
聞いてないから、どのみち
帰るだけだし」
俯いて話す、わたしの
頭に、大きくて温かいものが
乗せられた。
「大丈夫、どこに行くか
俺、知ってるから。
一緒に行こう」
わたしは無言で、首を振り続けた。
例えそうだとしても、
やっぱり…
「とにかく、行けば分かる」
そう言って、わたしの手を取って
駅の方へと、歩き出す
桐生くんの手は、
包み込むように、優しくて
温かかった。