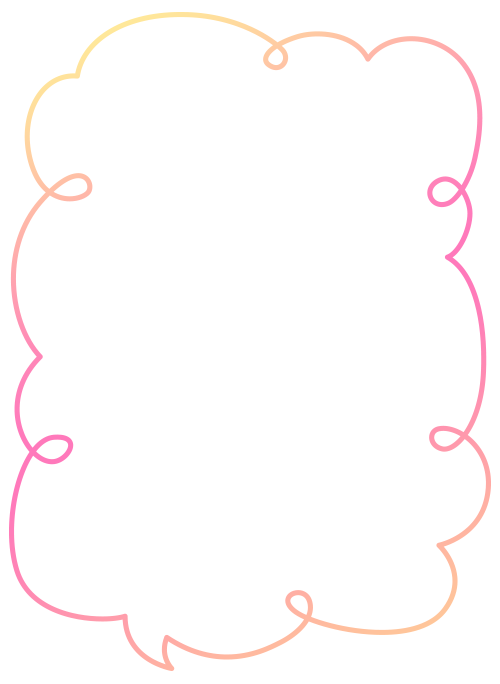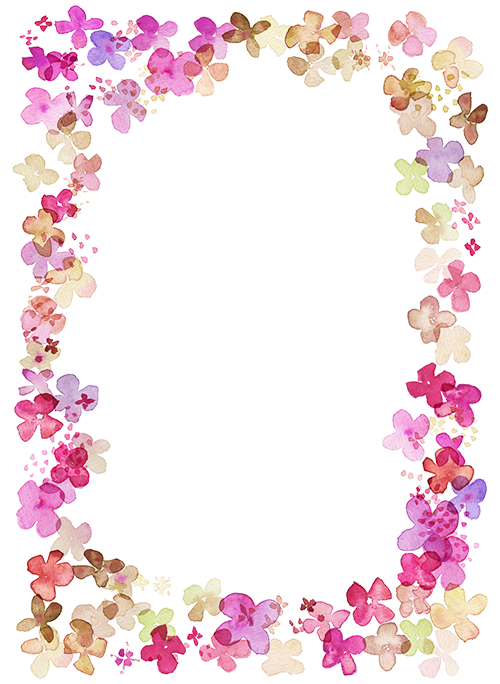「それは違う――!」
「俺には何が違うのかよくわかんないけど、ハルトも池田のこと見損なったと思う。あの日以来、お前の話なくなったし」
「……っ」
「ハルトの中学の時の彼女ってさ、人の悪口言う奴だったんだよ。しかも、浮気症。それでもハルトは耐えてたんだよ。そいつのことが好きだったから。でも、別れ際に言われたんだ」
「――ハルトのことなんて好きじゃない、って?」
「なんだ、知ってたのかよ。そうだ。だから、今度は人の悪口を言わない優しくて信用できる子と付き合いたいって。俺は池田もハルトと同じ気持ちだと思ってたから応援してたけど……そうじゃなかったんだな」
林君は呆れたような表情をあたしを見つめる。
違う。そうじゃない。そうじゃないの。
心の中で叫んでもその言葉は喉の奥底に沈んでいく。
「ハルトはお前のことが好きだったのに、うまくいかなくて残念だったよ」
林君はそれだけ言うとあたしの横を通り過ぎていった。
眼球が左右に揺れる。ドクンドクンッと大きな音を立てて震える心臓の音だけが妙に脳に響く。
ハルトはあたしのことが好きだった。
好きだった。
だった。
もう過去形になってしまったの……?
息をするのも忘れてしまうぐらい動揺していた。
ねぇ、ハルト。あたしたちのボタンはいつ掛け違えてしまったんだろう。
あの日、あの時、あたしが『嫌い』なんて言わなければ、今ハルトの隣にいるのはあたしだったんだよね……?
ハルトの隣の席は……セイラじゃない。
あたしだけのものだったんだ。
その場に呆然と立ち尽くすあたしに、後悔が波のように一気に押し寄せてきた。
「俺には何が違うのかよくわかんないけど、ハルトも池田のこと見損なったと思う。あの日以来、お前の話なくなったし」
「……っ」
「ハルトの中学の時の彼女ってさ、人の悪口言う奴だったんだよ。しかも、浮気症。それでもハルトは耐えてたんだよ。そいつのことが好きだったから。でも、別れ際に言われたんだ」
「――ハルトのことなんて好きじゃない、って?」
「なんだ、知ってたのかよ。そうだ。だから、今度は人の悪口を言わない優しくて信用できる子と付き合いたいって。俺は池田もハルトと同じ気持ちだと思ってたから応援してたけど……そうじゃなかったんだな」
林君は呆れたような表情をあたしを見つめる。
違う。そうじゃない。そうじゃないの。
心の中で叫んでもその言葉は喉の奥底に沈んでいく。
「ハルトはお前のことが好きだったのに、うまくいかなくて残念だったよ」
林君はそれだけ言うとあたしの横を通り過ぎていった。
眼球が左右に揺れる。ドクンドクンッと大きな音を立てて震える心臓の音だけが妙に脳に響く。
ハルトはあたしのことが好きだった。
好きだった。
だった。
もう過去形になってしまったの……?
息をするのも忘れてしまうぐらい動揺していた。
ねぇ、ハルト。あたしたちのボタンはいつ掛け違えてしまったんだろう。
あの日、あの時、あたしが『嫌い』なんて言わなければ、今ハルトの隣にいるのはあたしだったんだよね……?
ハルトの隣の席は……セイラじゃない。
あたしだけのものだったんだ。
その場に呆然と立ち尽くすあたしに、後悔が波のように一気に押し寄せてきた。