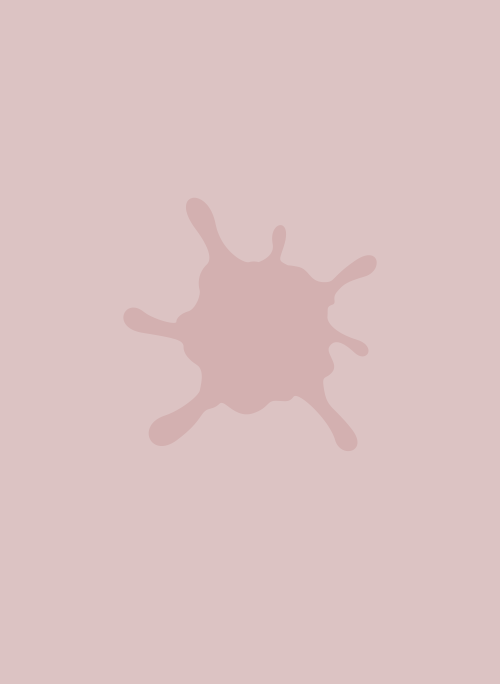「香澄、火ついた?」
「うん。ついた~」
「そう、良かった」
香澄と二人でお風呂を掃除した。
小さい頃は3人で入った記憶がある。
その記憶に大人の女性もいた。
タケルのお母さんだ。
そうすると、小学校に上がる前の記憶だ。
そんな思い出のあるここに、また来られるなんて思ってもみなかった。
今がすごく幸せな気がした。
同じ生きるのに、どうして今まであんなに苦しい思いをしなければいけなかったのだろう?
今も、二人の友達が私のためにそばにいてくれてるのはわかる。
二人に迷惑をかけている。
それもわかっている。
でも、それをしてくれる友達がいてくれることが、どんなに幸せなことだろう。
ましてや、タケルは…
「どした?」
香澄がやって来た。
「ちょっと考え事」
「ちょっとって、さっきからずっとここにいたの?」
火をつけてから、私はずっと考え込んでいたらしい。
「あちゃ…」
「皆美ったら。で、沸いたかな?」
香澄は蓋を開けて混ぜてみた。
「うん、ちょうどいい感じ」
香澄が濡れた手を振りながらこっちを見て言った。
「じゃあ、一緒に入る?」
「うん」
香澄と一緒だなんて何年振りだろう。
ちょっとドキドキしちゃう。
「おれは?」
タケルが後ろから言った。
「ばーか!」
私はそう言うと、両手で口を横に開いて、いーってした。
「おまえこそガキみたいだな…」
タケルが呆れた顔をした。
「オトコが一番風呂だ!」とタケルが訳のわからないことを言っていたが、却下した。
元々の屋敷の規模から湯船は大きめだ。
二人でゆったり入っていると香澄が言った。
「皆美、肌きれいだね」
「そう?香澄も相変わらず色白できれいだよ」
「ありがと」
二人で入ると本当にのんびりと長湯だった。
「おまえら、いい加減にしろ!」
ガラッと浴室の戸が開いてタケルが叫んだ。
バシャッ!!
私たちはお湯をぶっかけタケルを退散させた。
戸の向こうで「調べに行く時間がなくなるだろ…」とぶつぶつと言っているタケルだった。
「うん。ついた~」
「そう、良かった」
香澄と二人でお風呂を掃除した。
小さい頃は3人で入った記憶がある。
その記憶に大人の女性もいた。
タケルのお母さんだ。
そうすると、小学校に上がる前の記憶だ。
そんな思い出のあるここに、また来られるなんて思ってもみなかった。
今がすごく幸せな気がした。
同じ生きるのに、どうして今まであんなに苦しい思いをしなければいけなかったのだろう?
今も、二人の友達が私のためにそばにいてくれてるのはわかる。
二人に迷惑をかけている。
それもわかっている。
でも、それをしてくれる友達がいてくれることが、どんなに幸せなことだろう。
ましてや、タケルは…
「どした?」
香澄がやって来た。
「ちょっと考え事」
「ちょっとって、さっきからずっとここにいたの?」
火をつけてから、私はずっと考え込んでいたらしい。
「あちゃ…」
「皆美ったら。で、沸いたかな?」
香澄は蓋を開けて混ぜてみた。
「うん、ちょうどいい感じ」
香澄が濡れた手を振りながらこっちを見て言った。
「じゃあ、一緒に入る?」
「うん」
香澄と一緒だなんて何年振りだろう。
ちょっとドキドキしちゃう。
「おれは?」
タケルが後ろから言った。
「ばーか!」
私はそう言うと、両手で口を横に開いて、いーってした。
「おまえこそガキみたいだな…」
タケルが呆れた顔をした。
「オトコが一番風呂だ!」とタケルが訳のわからないことを言っていたが、却下した。
元々の屋敷の規模から湯船は大きめだ。
二人でゆったり入っていると香澄が言った。
「皆美、肌きれいだね」
「そう?香澄も相変わらず色白できれいだよ」
「ありがと」
二人で入ると本当にのんびりと長湯だった。
「おまえら、いい加減にしろ!」
ガラッと浴室の戸が開いてタケルが叫んだ。
バシャッ!!
私たちはお湯をぶっかけタケルを退散させた。
戸の向こうで「調べに行く時間がなくなるだろ…」とぶつぶつと言っているタケルだった。