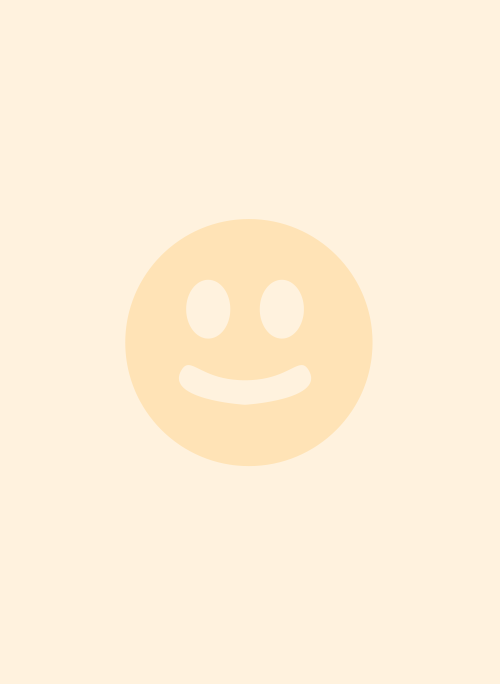「……あれは罵倒していたわけじゃ、ないんだよ。……僕は、志真――お母さんの助けになりたかった……。子育てを手伝いたいから、何か出来ることはないかって、いつも持ちかけていたんだ。……でも、お母さんはいつもその申し出を拒んだ……。育児は自分ひとりで出来るから、任せておけばいいって言ってね。……自分はそれで、どんどん弱っていってたっていうのに……僕には仕事に専念してもらいたいって言って、きかなかった。それで、その話で僕が食い下がるうちに口論になってしまうことは、確かに何度もあったんだ。僕は……お爺ちゃんが言うとおり、鈍感でカッとなりやすい性格だ。……あの狭いアパートで……雌舞希が見ているのなんて気にも留めないで、お母さんに怒鳴り声を浴びせたこともあったと思う。……そのせいで、お母さんを全く傷つけなかったかって言われれば、それは……否定できない。……だから……、雌舞希の僕に対する拒絶を初めて見た時、お母さんが病んだ原因は、自分にあるんだって……、僕自身もそう思ったんだ」
その話し方には、私の中のお父さんの印象と、ずいぶん違いがあった。
私の記憶の中にいるお父さんは、こんな殊勝な姿勢の男じゃなかった。
いつも大声で叫んでいて、誰かの話になんて、まるっきり耳を貸さないような男だったはずなのだ。
……だけれど、それと同時に、お父さんは本当はあの頃から、今目の前で話しているこの男とまったく同じような人間だったと、そんなふうにも感じていた。
少なくとも、今お父さんがしている話が、自分の都合の良いように理不尽に改変されたものだ、なんていうふうには思わなかった。
……もっと言えば、「私もそう思う」と相づちを打ちたいぐらいに、私の記憶とお父さんの発言が食い違って感じられることはなかった。