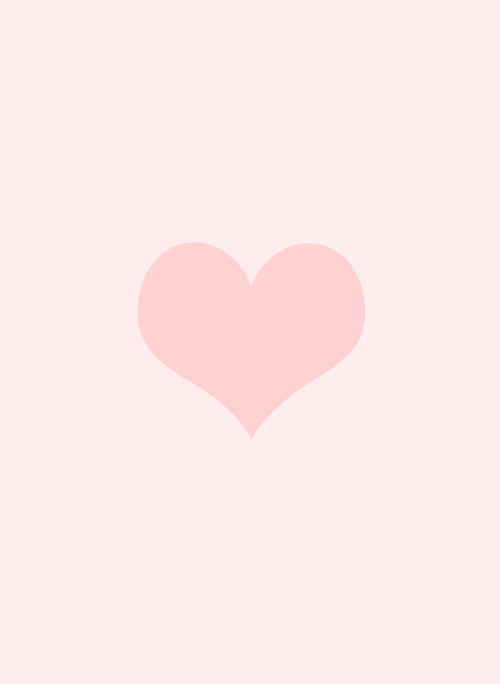「相島さんは変わってますよねー。」
「なんで?」
「だって普通は私のこういうところを知って引くの、男の人は。」
「誰も引いてねーとは言ってないけど。」
「…じゃあ、引いてるの?」
「今更別に。つーか、見た目と嗜好品は関係ないだろ。」
「…そう、だけど。」
そんな風に強く、思えない。
「…じゃあ何?お前はもし俺が甘いもの好きっつったら引くのかよ。」
「…驚くけど、引きはしない、かな。一緒に食べに行けるし。」
「そんなもんだよ、嗜好品なんて。そいつの一部でしかない。一部でお前の全部を決めつける男なんて趣味わりーとしか言いようがねぇよ。」
ぐうの音も出ない。相島はいつだって正論だ。その正論が時々刺さって、今日はたまたま優しく聞こえる。
「…相島さんが優しい…。私、いくら払うんですかねこれ。」
「いくら払ってくれんのかなー。楽しみだわ。」
「…悪い顔してる。あ、お金はあんまりないけど、チョコはある!」
「またチョコかよ。」
右手をなんとか鞄の中に滑り込ませてチョコを探す。
「はい、ビターチョコ。」
「なんでビター?」
「…もらいすぎて、食べれない分。」
「それ、捨てる気だったやつ?」
「違いますー!ホットミルクに溶かして飲もうと…。」
「あっそ。じゃあもらう。」
「え?」
口を開けた相島を前に、変な声が出た。
「え?あの、相島さん?」
「どう考えてもお前が食わせる以外にねーからな。早くしろ。」
確かに相島の左手は紗弥の左手を、右手は紗弥の腰を支えている。相島が袋を開けて食べるのは無理だ。
「…マジですか。」
「マジですよ。つーか何照れてんだよ。照れるようなことじゃねーだろ。」
「…いや、そうなんだけど、…なんていうか、相島さん無防備だから!」
「無防備なのはお前の方だけどな。早くしろよー!」
「わかったって!」
もう酔いに任せてしまうことにする。大きく開いた口の中に、そっとビターチョコを入れた。
ポキッという音が聞こえてすぐに、チョコはなくなったようだった。
「なんで?」
「だって普通は私のこういうところを知って引くの、男の人は。」
「誰も引いてねーとは言ってないけど。」
「…じゃあ、引いてるの?」
「今更別に。つーか、見た目と嗜好品は関係ないだろ。」
「…そう、だけど。」
そんな風に強く、思えない。
「…じゃあ何?お前はもし俺が甘いもの好きっつったら引くのかよ。」
「…驚くけど、引きはしない、かな。一緒に食べに行けるし。」
「そんなもんだよ、嗜好品なんて。そいつの一部でしかない。一部でお前の全部を決めつける男なんて趣味わりーとしか言いようがねぇよ。」
ぐうの音も出ない。相島はいつだって正論だ。その正論が時々刺さって、今日はたまたま優しく聞こえる。
「…相島さんが優しい…。私、いくら払うんですかねこれ。」
「いくら払ってくれんのかなー。楽しみだわ。」
「…悪い顔してる。あ、お金はあんまりないけど、チョコはある!」
「またチョコかよ。」
右手をなんとか鞄の中に滑り込ませてチョコを探す。
「はい、ビターチョコ。」
「なんでビター?」
「…もらいすぎて、食べれない分。」
「それ、捨てる気だったやつ?」
「違いますー!ホットミルクに溶かして飲もうと…。」
「あっそ。じゃあもらう。」
「え?」
口を開けた相島を前に、変な声が出た。
「え?あの、相島さん?」
「どう考えてもお前が食わせる以外にねーからな。早くしろ。」
確かに相島の左手は紗弥の左手を、右手は紗弥の腰を支えている。相島が袋を開けて食べるのは無理だ。
「…マジですか。」
「マジですよ。つーか何照れてんだよ。照れるようなことじゃねーだろ。」
「…いや、そうなんだけど、…なんていうか、相島さん無防備だから!」
「無防備なのはお前の方だけどな。早くしろよー!」
「わかったって!」
もう酔いに任せてしまうことにする。大きく開いた口の中に、そっとビターチョコを入れた。
ポキッという音が聞こえてすぐに、チョコはなくなったようだった。