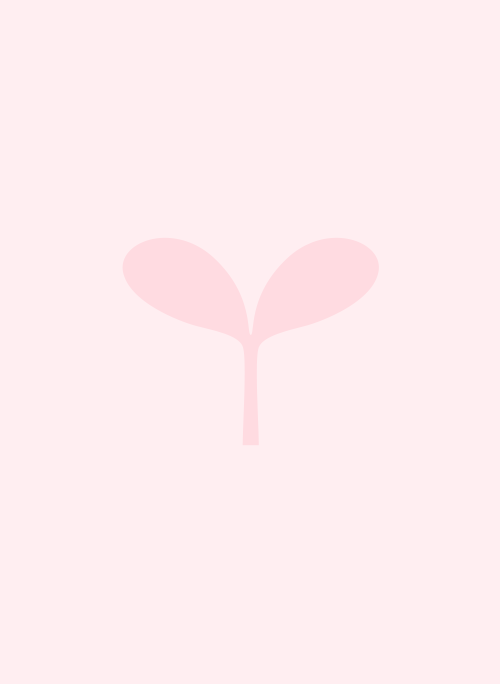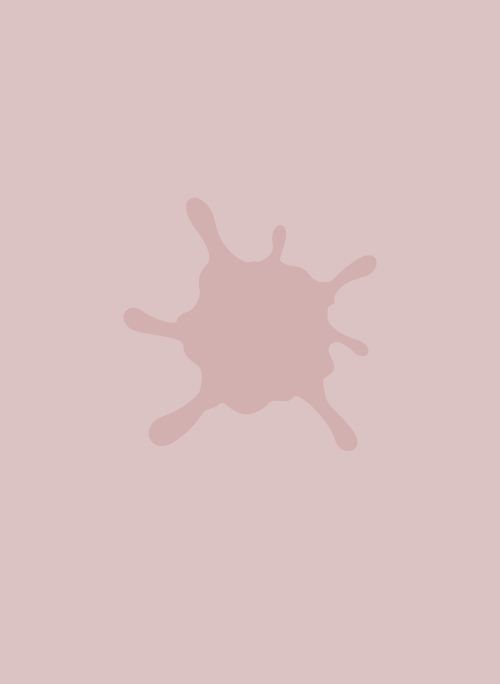明け方のマリアの微笑みが脳裏に浮かぶ。
眼球が忙しなく動き、歩美は更に混乱する。
あの日、大きく名前の書かれた単語帳を広げていた。
そして思い掛けず、マリアは毒薬を渡す機会を得た。
咄嗟の判断で手渡したのだろうか。
決して計画的ではないように見えた。
しかし、それは間違いだったと、歩美は気付いた。
あの機会を得るために、手渡す機会を得るためだけに、マリアはずっとあのような行動を取り続けたのではないか?
それだけを心の支えとして生きている人間も、いるのではないか?
「私、踏んづけた時に、怪我もしました。皮膚から毒が入っている筈です。でも、何ともない」
「貴方は生きておられる、それがあの人の答えなのでしょう」
「答え……」
歩美は、まだ冬沙子の掌にある粉々になった青い鳥に、目を落とした。
「私たちの娘が生きていたのなら、ちょうど貴方ぐらいの年になっていたでしょうから。娘の名前はね……『亜由美』っていうのよ」
眼球が忙しなく動き、歩美は更に混乱する。
あの日、大きく名前の書かれた単語帳を広げていた。
そして思い掛けず、マリアは毒薬を渡す機会を得た。
咄嗟の判断で手渡したのだろうか。
決して計画的ではないように見えた。
しかし、それは間違いだったと、歩美は気付いた。
あの機会を得るために、手渡す機会を得るためだけに、マリアはずっとあのような行動を取り続けたのではないか?
それだけを心の支えとして生きている人間も、いるのではないか?
「私、踏んづけた時に、怪我もしました。皮膚から毒が入っている筈です。でも、何ともない」
「貴方は生きておられる、それがあの人の答えなのでしょう」
「答え……」
歩美は、まだ冬沙子の掌にある粉々になった青い鳥に、目を落とした。
「私たちの娘が生きていたのなら、ちょうど貴方ぐらいの年になっていたでしょうから。娘の名前はね……『亜由美』っていうのよ」