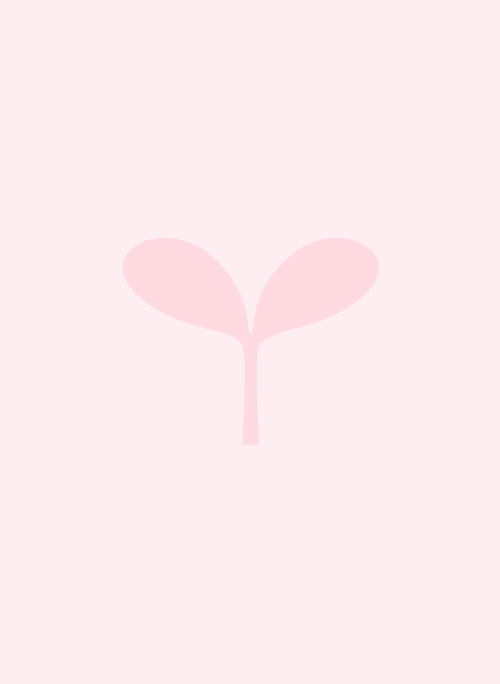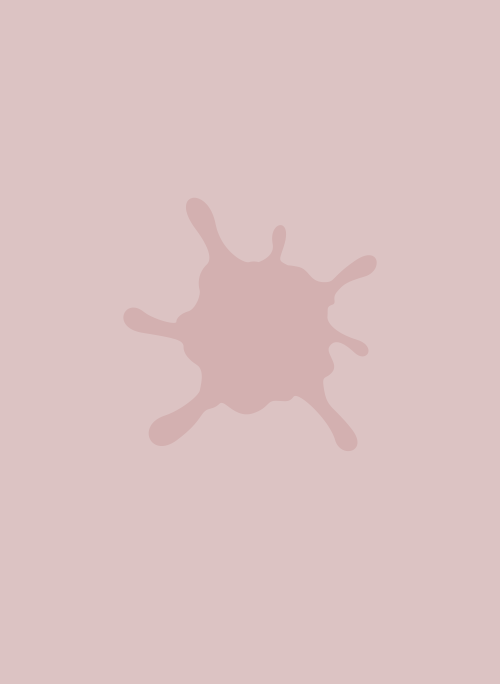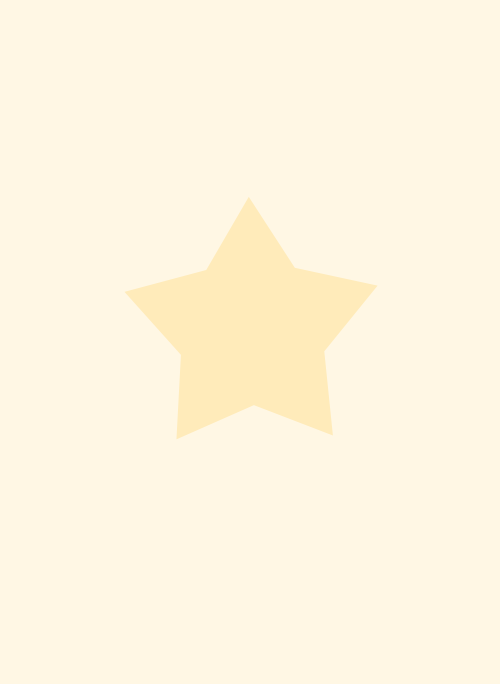今は故郷を飛び出し、アユミは自由の身になった。
自活もしている。
だが、そんなアユミにご親切にも年に数回程度、こうして滅多に電話を取らない編集長が思い出させてくれるのだ。
彼は決して下の名前では呼ばない。
馴れ合いを許さないから、長が勤まる、そう言っているかのような態度だ。
現在の彼のポストはスクープに拠るところが大きいと、何かの機会の時に同僚から聞いた。
しかし、今の彼は堅実で地道な判断力の塊に見える。
常に自問し、自分の役割に撤しているのだろうか。
「神坊さん、電話を回します」
官僚のような口調なのに、澄み切った声だった。
「はい、お願いします」
歩美は仕方なく受話器を取った。
自活もしている。
だが、そんなアユミにご親切にも年に数回程度、こうして滅多に電話を取らない編集長が思い出させてくれるのだ。
彼は決して下の名前では呼ばない。
馴れ合いを許さないから、長が勤まる、そう言っているかのような態度だ。
現在の彼のポストはスクープに拠るところが大きいと、何かの機会の時に同僚から聞いた。
しかし、今の彼は堅実で地道な判断力の塊に見える。
常に自問し、自分の役割に撤しているのだろうか。
「神坊さん、電話を回します」
官僚のような口調なのに、澄み切った声だった。
「はい、お願いします」
歩美は仕方なく受話器を取った。