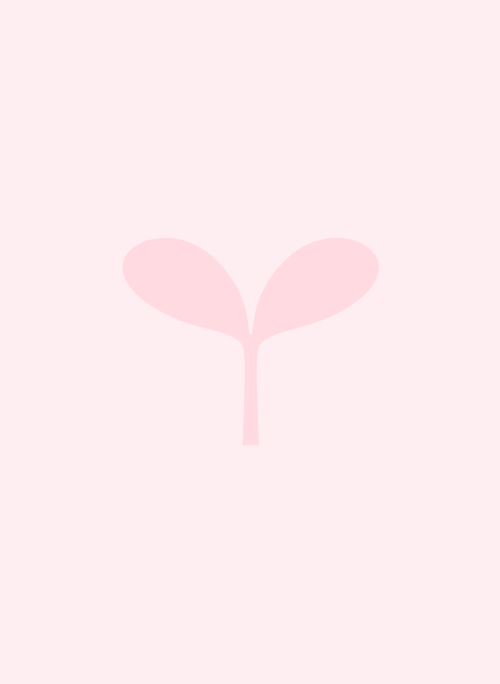先日、青いガラス細工を失ったことを除けば、アユミの毎日は変わらない。
忙殺された時間の中で、日々の些細な変化を思い起こす余裕など、ありはしなかった。
それでも、少しだけ変わったところもある。
ただ疲労回復だけに努めてきた味気ない自宅の一時が、同窓会への参加を機に、アユミの心に僅かながらも明かりを灯すようになったことだった。これは自覚している。
「ジンボウさん、電話です」
机の上で仕事の段取りを考えていたアユミは、完全に不意を突かれてしまった。
しかし、理由はそれだけではない。出版社で勤めているフロアで、名字でアユミを呼ぶのは、三十そこそこの若い編集長だけなのである。
それも滅多に他の人間の電話を取らない上に、普段から殆んど声を掛けられることのない相手だった。
さらに、彼には逸話もある。
赴任してからというもの、毎日オフィスに最後まで残り、考え事をしているのだそうだが、ビルの管理会社の話によると、夜間の見回り時に建物からパッタリと姿を消すことがあるそうで、守衛の間では「ゴースト」と仇名されている人物なのだ。
勿論、「ゴーストって、仇名、付いてますよ」なんて本人には誰も言わないし、言えない。むしろアユミには、もっと彼にぴったりな言葉があるような気がしてならない。
何れにせよ、そういったいくつもの理由が重なり合ったせいか、名前を呼ばれアユミの背筋が反射的にピンと伸びた。
忙殺された時間の中で、日々の些細な変化を思い起こす余裕など、ありはしなかった。
それでも、少しだけ変わったところもある。
ただ疲労回復だけに努めてきた味気ない自宅の一時が、同窓会への参加を機に、アユミの心に僅かながらも明かりを灯すようになったことだった。これは自覚している。
「ジンボウさん、電話です」
机の上で仕事の段取りを考えていたアユミは、完全に不意を突かれてしまった。
しかし、理由はそれだけではない。出版社で勤めているフロアで、名字でアユミを呼ぶのは、三十そこそこの若い編集長だけなのである。
それも滅多に他の人間の電話を取らない上に、普段から殆んど声を掛けられることのない相手だった。
さらに、彼には逸話もある。
赴任してからというもの、毎日オフィスに最後まで残り、考え事をしているのだそうだが、ビルの管理会社の話によると、夜間の見回り時に建物からパッタリと姿を消すことがあるそうで、守衛の間では「ゴースト」と仇名されている人物なのだ。
勿論、「ゴーストって、仇名、付いてますよ」なんて本人には誰も言わないし、言えない。むしろアユミには、もっと彼にぴったりな言葉があるような気がしてならない。
何れにせよ、そういったいくつもの理由が重なり合ったせいか、名前を呼ばれアユミの背筋が反射的にピンと伸びた。