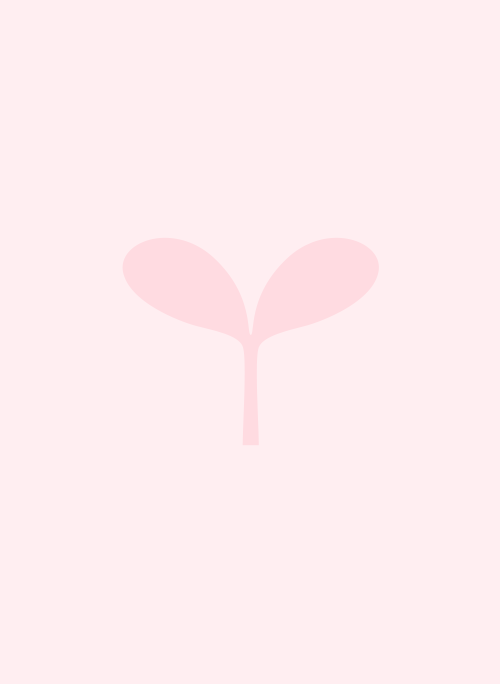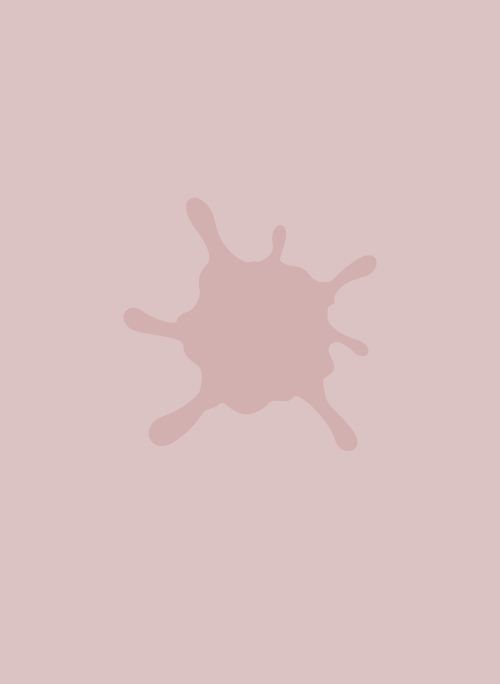「そう言えば、アユミ、気付いてた?」
シズカの語尾の調子が変わる。相手の息遣いを確かめるような、低い囁き。高校時代にもやった、二人っきりの内緒話だ。
「何が?」
「天沢のこと」
「アマサワ?」
わからない。シズカとの接点は高校時代だから、とアユミの脳が記憶を追い求める。
「いたじゃない。三年の時、よく青い鳥をわざわざ見に来ていた……」
「ああ、同学年にいた4組の天沢君ね」
頭の中で真面目そうな普通の男の子をキャッチする。表情はぼやけてよく分からない。多分、青い鳥を見に来た時に、一言二言、交したかもしれない。
「そう、その天沢。アユミのことが好きだったらしいよ」
「うそっ」
唐突すぎて、口の中が一瞬で渇く。舌の上に残った粘りさえ、干上がってゆく。
「やっぱり、そんなことだろうと思ったよ」
「ごめん」
その頃は何も感じなかった。もし気付いていたらどうだったのか? 自分を好きって、どういうことなのか、改めて考える。
「謝ることじゃないけど、少しは気にしないとね。若いんだからさ」
「うん」
「あたしって、おせっかいだよね」
「そんなことない。でも、何で教えてくれなかったのよ」
「気付くでしょ。普通」
ハッキリとした返事だ。滑舌もすこぶる良い。
「普通って言われても……」
アユミの口元がとがる。
「判りやすかったよ。天沢のヤツ。隠してるつもりがあったのかも、分からないけど」
どう判りやすかったのか、などと聞きたくなったのだが、親友と言えども流石に鈍感を晒け出すようで、止めた。
「へへへ、じゃあね」
シズカは意外にも、呆気なく電話を切った。
シズカの語尾の調子が変わる。相手の息遣いを確かめるような、低い囁き。高校時代にもやった、二人っきりの内緒話だ。
「何が?」
「天沢のこと」
「アマサワ?」
わからない。シズカとの接点は高校時代だから、とアユミの脳が記憶を追い求める。
「いたじゃない。三年の時、よく青い鳥をわざわざ見に来ていた……」
「ああ、同学年にいた4組の天沢君ね」
頭の中で真面目そうな普通の男の子をキャッチする。表情はぼやけてよく分からない。多分、青い鳥を見に来た時に、一言二言、交したかもしれない。
「そう、その天沢。アユミのことが好きだったらしいよ」
「うそっ」
唐突すぎて、口の中が一瞬で渇く。舌の上に残った粘りさえ、干上がってゆく。
「やっぱり、そんなことだろうと思ったよ」
「ごめん」
その頃は何も感じなかった。もし気付いていたらどうだったのか? 自分を好きって、どういうことなのか、改めて考える。
「謝ることじゃないけど、少しは気にしないとね。若いんだからさ」
「うん」
「あたしって、おせっかいだよね」
「そんなことない。でも、何で教えてくれなかったのよ」
「気付くでしょ。普通」
ハッキリとした返事だ。滑舌もすこぶる良い。
「普通って言われても……」
アユミの口元がとがる。
「判りやすかったよ。天沢のヤツ。隠してるつもりがあったのかも、分からないけど」
どう判りやすかったのか、などと聞きたくなったのだが、親友と言えども流石に鈍感を晒け出すようで、止めた。
「へへへ、じゃあね」
シズカは意外にも、呆気なく電話を切った。