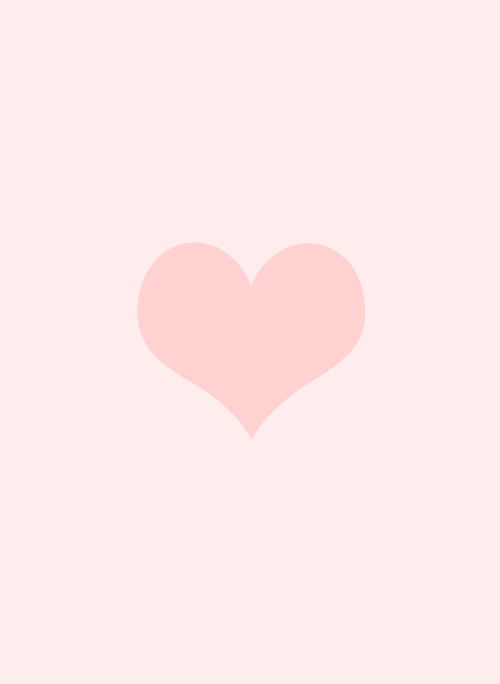窓の外には柿の木が一本とおばさんがやっている家庭菜園、ガーデニングと呼ぶには雑然とした花々が賑やかに広がっている。
春之とあんな風に一緒にいるのはよくあったことで、その季節は様々だったはずだ。
それなのにあの時間を思い出すとき、私はいつも秋のおだやかな日だったように思える。
日差しはあたたかいけど強くなく、外を吹く冷たい風は室内にいる私たちには届かない。
一年に数日あるかないかという、短く貴重な小春日和。
それは事実ではなく、もしかしたら春之に対する私の印象なのかもしれない。
太陽の光が窓で区切られて、フローリングの上に平行四辺形の陽だまりを作る。
その中には私と春之のふたりだけ。
春之のやわらかい髪の毛は日の光を受けて、雪を待つ原っぱのような、ミルクを多めに溶かしたコーヒーのようなふんわりとした色をしている。
猫背のシルエットも、少し目を伏せた横顔も、どこか輪郭がぼんやりとまるく見える。
現実感の薄いその光景を見て自分の手に視線を落とすと、春之を包むものと同じ光の中に私もいた。
━━━━━まるで、世界にふたりだけみたい。
世界がこのまま本当に切り取られたらいいのに、と私は思っていた。
実際はキッチンから母やおばさんたちの話し声と食器のぶつかる音が聞こえるし、リビングの方からは酔っぱらった男たちの遠慮のない笑い声がする。
切り取られた世界など私の妄想で錯覚。
だけどそのささいな錯覚ひとつで、私はバカみたいに幸せになれた。
私は「ずっとこうして生きていきたい」と思っていた。
当時はそんな明確な感情は自覚していなかったけれど、今振り返るとそう思う。
私の必死の創作会話は、部屋が暗くなり少し気温が下がって、
「あんたたち!こんな寒いところにいて! 風邪ひくからこっちに来なさい」
とおばさんに邪魔されるまで、ずっと続いた。
私は『水沢』にはなれないのだと決定的にわかる、ずっと前のことだ。