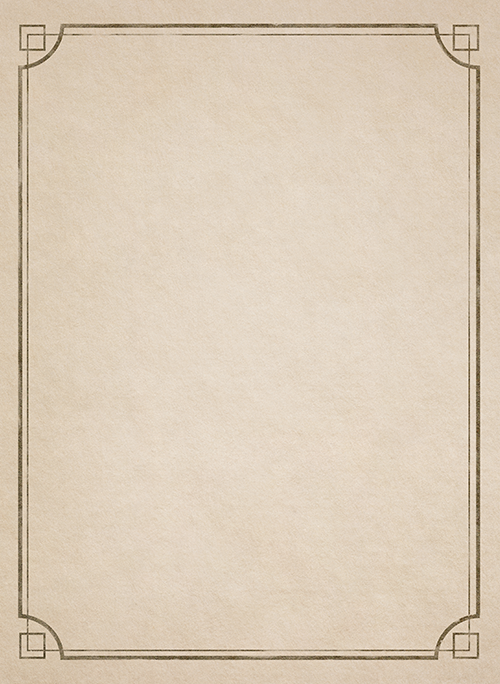「ん~?珍しいオナガちゃんが一人だぁ」
オナガの天敵たるワタリが現れることなど想定済みだった。
彼がここにくることを想定して動いた自分の馬鹿さ加減に嫌気がさした。
軽口を吐きながら、どこまで本心かわからない愛言葉を語るワタリの軽薄さがオナガは嫌いだった。
それでも、今彼を待っていた。
「…私のことバカだと思うでしょう?」
座るオナガの正面に立ったワタリが変わらぬ笑みを浮かべて頷く。
「そういう所も可愛いよ」
「…優しい言葉が欲しいの…今は」
「何も考えたくない?」
脳内を覗く、心を揺さぶり涙腺を壊す声色が心を染めていくように感じた。
逃げているだけ、それも最悪の方法で。
癒されたい、仕返しだなどとその程度の言葉では生ぬるい。
これは立派な裏切りだ。
「…ボクのこと軽蔑しているくせに、困った時は頼るなんて都合のいい女だねぇ」
責める様な声色は胸に心地いい。
罵声とも責め苦も、程よく心地よい。
甘やかされ、責められ、それでまた甘やかす。
ワタリの言葉は、存在は、いつもどうしようもなく都合がよく、曖昧で、そして心地よい。
逃げ場の様なその声色、決して救いにならないその曖昧さ。
否定しない、肯定しない、優しくしない、冷たくしない。
彼の存在全てが、心地よいのだからどうしようもない。
責められたいからここへきた。
罪の意識に飲まれたくない、罰を受けたくない。
悪事の共有は一方的ではいけない。
彼はその点よくわかっていた。