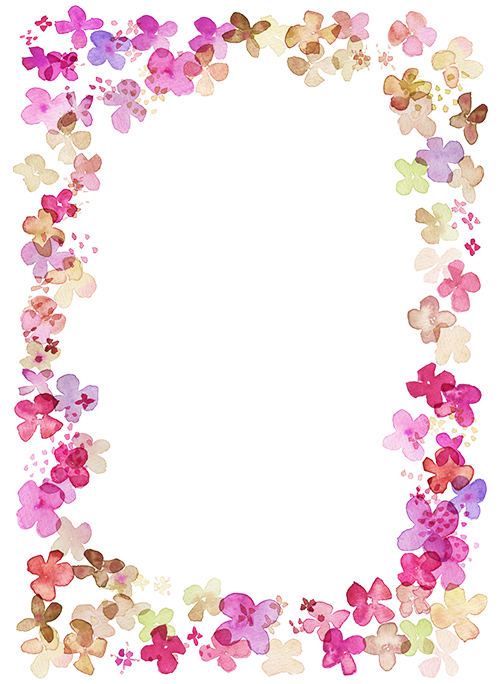「これが違いだ」と見せつけるかのように、お兄ちゃんは持っていた箱を開けた。
「短い間だったけど、日菜が世話になりました。これは、うちで出しているものだが、みなさんで。
さぁ帰るぞ、日菜」
お兄ちゃんに背中を抱かれ、入口に向かわせられる…。
こんなにあっさりお別れなんてできなくて、振り返る。
「…みんな…っ」
言いたいことが、山とある。
ごめんなさい、ありがとう、たのしかった、うれしかった、くやしかった…。
でも、いろんな感情が溢れて、言葉にならない。
代わりにとめどなく出てくるのは、大粒の涙だけ…。
わたしは、
何のためにここに来たの。
迷惑かけて、支えてもらって、頑張って…
でも、結局、なんにもできなくて―――。
きちんと一人立ちできたわけでもなければ、
本当の目的だった、晴友くんへの告白もできていない。
お兄ちゃんが過保護なのも、結局はわたしがいつまでも頼りない子だからだって、とっくに解かってる。
何もかも、ダメ。
ダメダメで、頼りないこんなわたし、もう嫌…。
このまま去ってしまったら、もっと自分のことが大嫌いになってしまう。
晴友くん…。
せめて…
せめてこの想いだけは伝えたい。
あなたを好きになったことで、このリヴァ―ジでの日々が始まったのなら、
終わる時は、想いを打ち明けて去りたい。
それがわたしの願い。
やるべき、一番の目的…。
「短い間だったけど、日菜が世話になりました。これは、うちで出しているものだが、みなさんで。
さぁ帰るぞ、日菜」
お兄ちゃんに背中を抱かれ、入口に向かわせられる…。
こんなにあっさりお別れなんてできなくて、振り返る。
「…みんな…っ」
言いたいことが、山とある。
ごめんなさい、ありがとう、たのしかった、うれしかった、くやしかった…。
でも、いろんな感情が溢れて、言葉にならない。
代わりにとめどなく出てくるのは、大粒の涙だけ…。
わたしは、
何のためにここに来たの。
迷惑かけて、支えてもらって、頑張って…
でも、結局、なんにもできなくて―――。
きちんと一人立ちできたわけでもなければ、
本当の目的だった、晴友くんへの告白もできていない。
お兄ちゃんが過保護なのも、結局はわたしがいつまでも頼りない子だからだって、とっくに解かってる。
何もかも、ダメ。
ダメダメで、頼りないこんなわたし、もう嫌…。
このまま去ってしまったら、もっと自分のことが大嫌いになってしまう。
晴友くん…。
せめて…
せめてこの想いだけは伝えたい。
あなたを好きになったことで、このリヴァ―ジでの日々が始まったのなら、
終わる時は、想いを打ち明けて去りたい。
それがわたしの願い。
やるべき、一番の目的…。