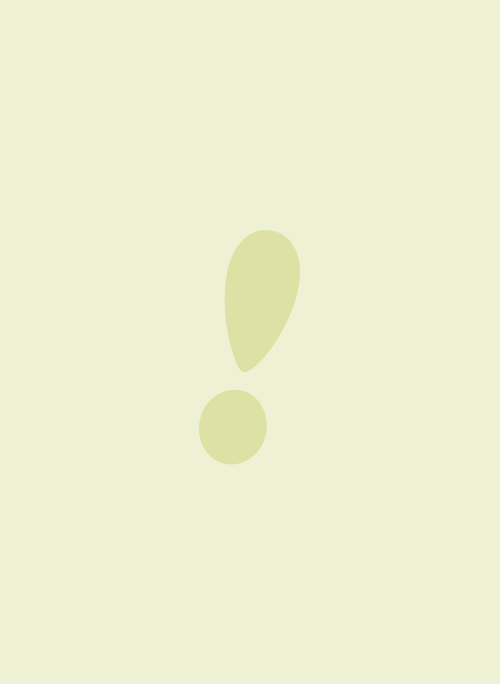ベルは頷いて、部屋の隅に置いてある細長い包みを取りに行く。
厚い麻布で包んだそれは、それなりに値の張る葡萄酒だ。
レイエ工房への礼に、と、エドガーが用意していたものだ。
ベルは包みを持ち、三人がはしごを担いで、レイエ工房に向かう。
昼下がりの風はほんのすこしひんやりとしていて、いつの間にか秋が深まってきていることに気がついた。
たった一週間。
家を出てからたった一週間しか経っていないのに、もうずいぶんと月日が経ったような気がしてしまう。
家を出たときは、もうすこし、今よりほんのすこしだけ、風は暖かかったはずだ。
お父様は元気だろうか、と、ふと思う。
家からそれほど離れていないベルシーにいて、一週間も見つかっていないということは、
きっとベルの手紙の通り、探さないでくれているのだろう。
部屋に散らかした髪はどうなっただろうか。
アネモネ色の髪。
もう、伸ばすこともないだろうけど。
そんなとりとめもないことを考えていると。