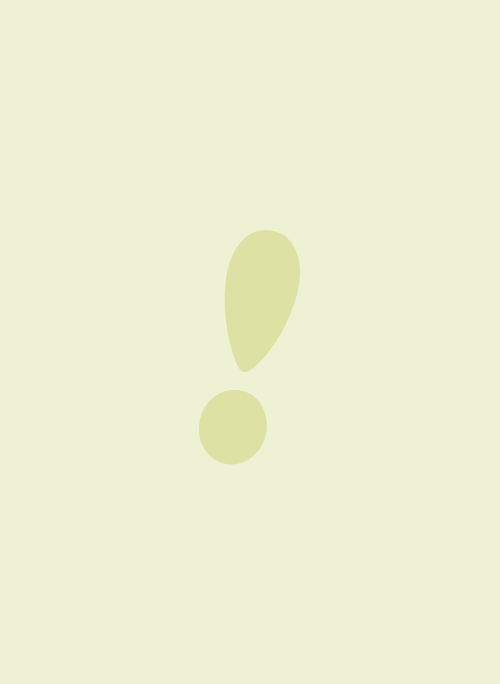一片の迷いも見せない筆運びを、ベルはぽかんと口を開けて眺めていた。
それはまさに職人の技だ。
画家は芸術家である前に職人なのだと、エドガーのゴツゴツした手を目で追いながら、ベルは思った。
「これで、」
ゆるやかな筆の跡をじっと眺めたままどれほど時間が経っただろうか。
気づけばエドガーは手を止め、梯子の上からセヴランに呼びかけた。
「いかがですか? すこしはましになりましたかな?」
まし、などと。
そんな謙遜などまったく必要ない。腹の底からそう思いながら、ベルはセヴランの表情を盗み見る。
セヴランの表情は変わらない。
聖堂に入ってきたときから厳しい顔つきで、和らいだことも、これ以上厳しくなったこともない。
そう気付いて、ベルはふと、このひとはすこしだけ親方に似ているかもしれない、と思った。
不機嫌なわけじゃない。
ただ単純に、表情が少ないだけなのかもしれない。
仰視法が甘いと言ったのも、たんに絵の出来に厳しいだけで、当てつけではないのかもしれない。
だって。