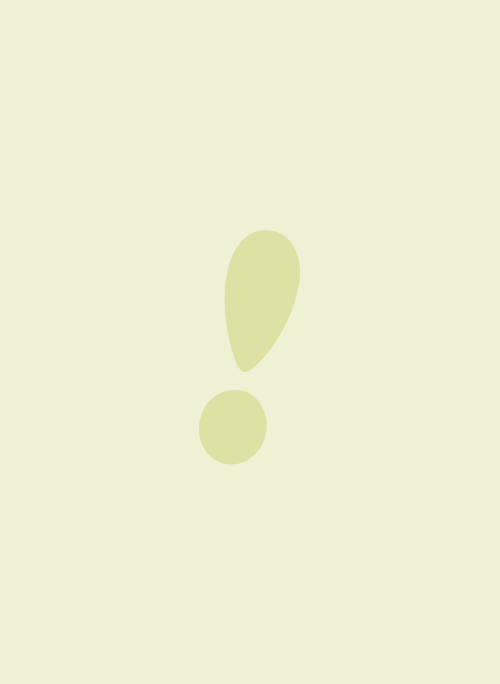上質な紙に書かれた流麗な文字はあたしのもの。
自分で言うのもなんだけど、字はどんな良家のお嬢様にだって負けないくらい綺麗だと思う。
「愛するお父様へ。わたくしは自ら志す道を行くため出て行きます。どうか探さないでください。――ベランジェールより」
小さな声で読み上げて、あたしは再びその紙を二つに折ると、床に散らばった赤毛の上にそっと置いた。
まとめておいた荷物を背負い、もう一度、姿見の中の自分を見た。
まるで別人のようになってしまった鏡の中のあたしの青い目を見つめて、決別の言葉をそっと、唇に乗せる。
「さようなら。――ベランジェール・ノエ」
開けた窓から吹き込む風に、部屋の中のアネモネ色が舞い上がった。
綺麗だわ、と、あたしはつぶやいた。
なんたって、最高の美神アフロディテが愛したアドニスの血の色だもの。
秋晴れの気持ちよく乾いた日差しが頬を照らす。
まるであたしの新たな人生を祝福しているよう、なんて馬鹿げたことを思いながら、窓枠に足をかけて外へ飛び出した。