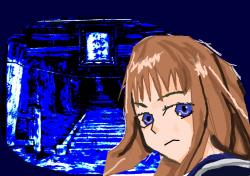そういえば、由美子はあの青年と何を話しているのだろうか。
2人は階段隅のラウンジで座りもせずに楽しそうに話をしている。
しかし、由美子のあんな表情は初めて見た。まるで初恋の人に再会したように、嬉しそうに頬を染めている。
まさかね。
こんな毎年恒例のスキー教室で、偶然にも初恋の人と出会うなんて、天文学的確率に等しいもの。考えすぎだ。
だが、戻ってきた由美子を見て、その確率は少し変動したように思えた。
「楽しそうでしたね。まさかあれが例の幼馴染の君ですか。」
からかってやることにした。今日だってさんざん私のスキーのスキルを馬鹿にされたのだ。お返しするのが後輩の礼儀。
しかし、由美子の返答は予想外のものだった。別に地雷を踏んだ訳ではない。
「よ。」
「え、なんて。」
「だから、そんな、ものよ。」
桜色の顔は一気に夏を飛び越えて、秋の紅葉を取り戻したようだった。
顔を真っ赤にする由美子を見て、私はその偶然の再会を祝福するのも忘れて、その奇跡のような偶然に酔いしれていた。
2人は階段隅のラウンジで座りもせずに楽しそうに話をしている。
しかし、由美子のあんな表情は初めて見た。まるで初恋の人に再会したように、嬉しそうに頬を染めている。
まさかね。
こんな毎年恒例のスキー教室で、偶然にも初恋の人と出会うなんて、天文学的確率に等しいもの。考えすぎだ。
だが、戻ってきた由美子を見て、その確率は少し変動したように思えた。
「楽しそうでしたね。まさかあれが例の幼馴染の君ですか。」
からかってやることにした。今日だってさんざん私のスキーのスキルを馬鹿にされたのだ。お返しするのが後輩の礼儀。
しかし、由美子の返答は予想外のものだった。別に地雷を踏んだ訳ではない。
「よ。」
「え、なんて。」
「だから、そんな、ものよ。」
桜色の顔は一気に夏を飛び越えて、秋の紅葉を取り戻したようだった。
顔を真っ赤にする由美子を見て、私はその偶然の再会を祝福するのも忘れて、その奇跡のような偶然に酔いしれていた。