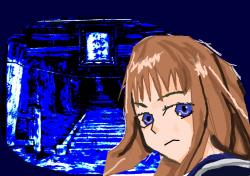そのような日々は体育祭前日まで続くのだが、ある日の朝、私は1番に学校へ来て、クラス旗の制作に励んでいた。
「早いな、山崎。」
旗の色付けに夢中になっていた私の後ろから、突然声が響いた。その声の主はカケルだった。
「ああ、本城くん。本城くんも早いね。きっと2番だよ。」
確かに魅力は感じていたが、この頃の私にとってのカケルは、その他大勢の中の一男子らという訳では無いが、まあクラスメイトの中でも仲が良い方の一男子、くらいにしか見ていなかった。
「あちゃー。2番か。だけど、明日は負けんぞ。」
それに、カケルの方も、そう言った事にはまったく無頓着という感じで、お互いハツラツとした若さが心地良い、至って健全な関係だった。
別に共通の趣味があったわけでも無いし、体育委員としての活動以外でも一緒にいるというわけでも無かったので、同級生や後輩に恋仲に間違われるようなことなど一度も無かった。
同級生の中には、いわゆる彼氏彼女の関係というモノを築いている方々もチラホラといらっしゃっだが、それはかなり少数派で、少なくとも私には縁遠いモノだった。
「早いな、山崎。」
旗の色付けに夢中になっていた私の後ろから、突然声が響いた。その声の主はカケルだった。
「ああ、本城くん。本城くんも早いね。きっと2番だよ。」
確かに魅力は感じていたが、この頃の私にとってのカケルは、その他大勢の中の一男子らという訳では無いが、まあクラスメイトの中でも仲が良い方の一男子、くらいにしか見ていなかった。
「あちゃー。2番か。だけど、明日は負けんぞ。」
それに、カケルの方も、そう言った事にはまったく無頓着という感じで、お互いハツラツとした若さが心地良い、至って健全な関係だった。
別に共通の趣味があったわけでも無いし、体育委員としての活動以外でも一緒にいるというわけでも無かったので、同級生や後輩に恋仲に間違われるようなことなど一度も無かった。
同級生の中には、いわゆる彼氏彼女の関係というモノを築いている方々もチラホラといらっしゃっだが、それはかなり少数派で、少なくとも私には縁遠いモノだった。