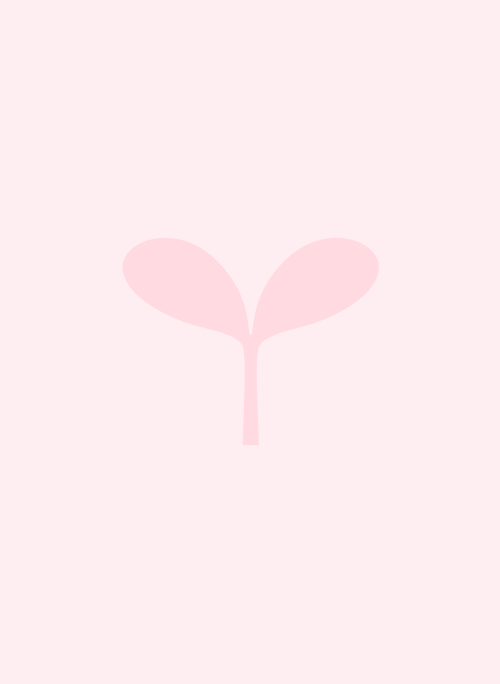「お友達の所へ行っておいで」
私は美月の帽子を外して頭を撫でると、背中を押した。しかし、美月はぴくりとも動かない。
「おとうさんが、美月をむかえにきてくれるの?」
私を見上げて、そう言った。私の右手は美月の両手の中にあった。
「あ、ああ。そうさ。迎えに来るよ」
「ほんとうに?」
「本当だよ」
「やくそくだからね?」
「約束するよ」
そこまで言って、ようやく美月は得心したようだった。ウンウンと、小さく頷いた。
「わかった。じゃ、行ってくるよ」
美月は私の手を放し、くるりと背を向けて、歩き出した。
「すみません。先生、宜しくお願いします」
私は志帆先生に向かってお辞儀をした。先生は笑顔で会釈をし、美月を連れて建物の中に入っていった。
中に入っていく様子を見ていて、美月が見えなくなった時、ぽつんと一人、取り残されたような気分になった。建物の中からは、元気の良い子供の声と音楽が漏れ聞こえてくる。
他のお母さん連中は、子供を預けるとそそくさと帰ったらしく、ふと見渡してみれば、私以外に誰もいなかった。きっと、これから仕事に行くか、家事が山積みなのだろう。
そういえば、今日、お父さんで幼稚園に送りに来たのも、私一人であった。しかし、今日は平日なのだ。もし普通の会社員なら、働いていなければおかしい曜日だろう。
私はまだ幼稚園の敷地内にいた。防犯上、門を閉めるとのことで、ずっと私を見ている職員が門の近くに立っていた。私は我に返り、「すみません」とだけ言って、門の外に出て行く。
だらりと粒状の汗が頬を伝って流れ落ちた。その私に、じりじりと蝉の鳴き声が覆いかぶさった。
本当に、今年の夏は暑かった。
1.夏の日 (完)
私は美月の帽子を外して頭を撫でると、背中を押した。しかし、美月はぴくりとも動かない。
「おとうさんが、美月をむかえにきてくれるの?」
私を見上げて、そう言った。私の右手は美月の両手の中にあった。
「あ、ああ。そうさ。迎えに来るよ」
「ほんとうに?」
「本当だよ」
「やくそくだからね?」
「約束するよ」
そこまで言って、ようやく美月は得心したようだった。ウンウンと、小さく頷いた。
「わかった。じゃ、行ってくるよ」
美月は私の手を放し、くるりと背を向けて、歩き出した。
「すみません。先生、宜しくお願いします」
私は志帆先生に向かってお辞儀をした。先生は笑顔で会釈をし、美月を連れて建物の中に入っていった。
中に入っていく様子を見ていて、美月が見えなくなった時、ぽつんと一人、取り残されたような気分になった。建物の中からは、元気の良い子供の声と音楽が漏れ聞こえてくる。
他のお母さん連中は、子供を預けるとそそくさと帰ったらしく、ふと見渡してみれば、私以外に誰もいなかった。きっと、これから仕事に行くか、家事が山積みなのだろう。
そういえば、今日、お父さんで幼稚園に送りに来たのも、私一人であった。しかし、今日は平日なのだ。もし普通の会社員なら、働いていなければおかしい曜日だろう。
私はまだ幼稚園の敷地内にいた。防犯上、門を閉めるとのことで、ずっと私を見ている職員が門の近くに立っていた。私は我に返り、「すみません」とだけ言って、門の外に出て行く。
だらりと粒状の汗が頬を伝って流れ落ちた。その私に、じりじりと蝉の鳴き声が覆いかぶさった。
本当に、今年の夏は暑かった。
1.夏の日 (完)