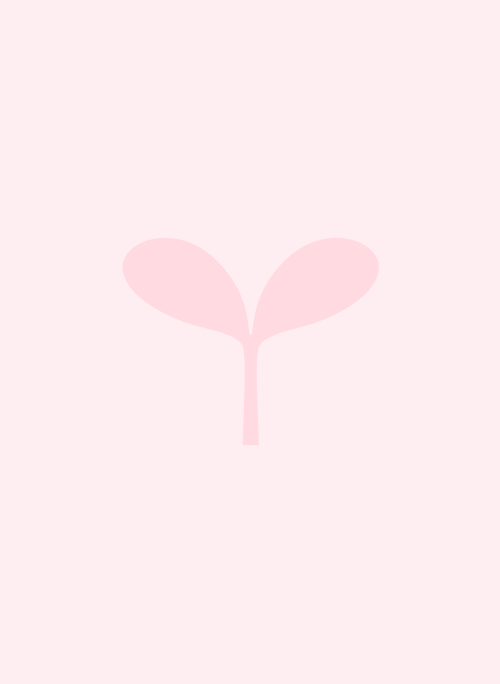指先から垂らした線香花火が、ちりちりと音を立てる。
水を溜めたバケツの側で、しゃがんだ美月の顔に、花火の光がしわくちゃな影絵を作った。
──その日の夜、新しくやって来たシンボルツリーを背に、美月と二人で花火に火をつけた。
民家にはそれぞれ明かりがともっていたが、漏れ聞こえる声や犬の鳴き声もなく、信じられないぐらいの、静かな夜だった。
美月は浴衣を着ていた。
地域の盆踊りのために、最近になって新しく買ったものだったのだが、運悪く、当日は雨が降った。その後、予備日として考えられていた翌日までも雨が止まず、とうとう延期から中止になってしまった。
それを聞いて残念がっていた美月を思い出し、今年はもう着ることもないだろうということで、押し入れの奥にしまわれていた浴衣だったのだが、私が花火をする折りに着たらどうかと考え、探し出して美月に見せた。
浴衣は、藍色の地に桃色の知らない花があしらわれていた。帯はかき氷のような、水色と白色の混ざりあった色合いだ。私が選んだ柄だった。
「落とさないように」
「うん」
線香花火の小さな玉に神経を集中し過ぎて、美月の黒目が真ん中によっている。
「息はしろよ」
「うん……」
どうやら、本当に息を止めていたようだった。
ちりちりとその線香花火の柔らかい玉の中から、か弱い光の結晶が、出たり引っ込んだりしていた。
開封された手持ち花火のセットだった。線香花火を残し、玄関の荷物の片隅に埋もれていた。
湿ってはいないか、と心配したが、どうやら取り越し苦労のようだった。
線香花火は、確かに私たちの目の前で、ちりちりと音を立てて燃えていた。
水を溜めたバケツの側で、しゃがんだ美月の顔に、花火の光がしわくちゃな影絵を作った。
──その日の夜、新しくやって来たシンボルツリーを背に、美月と二人で花火に火をつけた。
民家にはそれぞれ明かりがともっていたが、漏れ聞こえる声や犬の鳴き声もなく、信じられないぐらいの、静かな夜だった。
美月は浴衣を着ていた。
地域の盆踊りのために、最近になって新しく買ったものだったのだが、運悪く、当日は雨が降った。その後、予備日として考えられていた翌日までも雨が止まず、とうとう延期から中止になってしまった。
それを聞いて残念がっていた美月を思い出し、今年はもう着ることもないだろうということで、押し入れの奥にしまわれていた浴衣だったのだが、私が花火をする折りに着たらどうかと考え、探し出して美月に見せた。
浴衣は、藍色の地に桃色の知らない花があしらわれていた。帯はかき氷のような、水色と白色の混ざりあった色合いだ。私が選んだ柄だった。
「落とさないように」
「うん」
線香花火の小さな玉に神経を集中し過ぎて、美月の黒目が真ん中によっている。
「息はしろよ」
「うん……」
どうやら、本当に息を止めていたようだった。
ちりちりとその線香花火の柔らかい玉の中から、か弱い光の結晶が、出たり引っ込んだりしていた。
開封された手持ち花火のセットだった。線香花火を残し、玄関の荷物の片隅に埋もれていた。
湿ってはいないか、と心配したが、どうやら取り越し苦労のようだった。
線香花火は、確かに私たちの目の前で、ちりちりと音を立てて燃えていた。