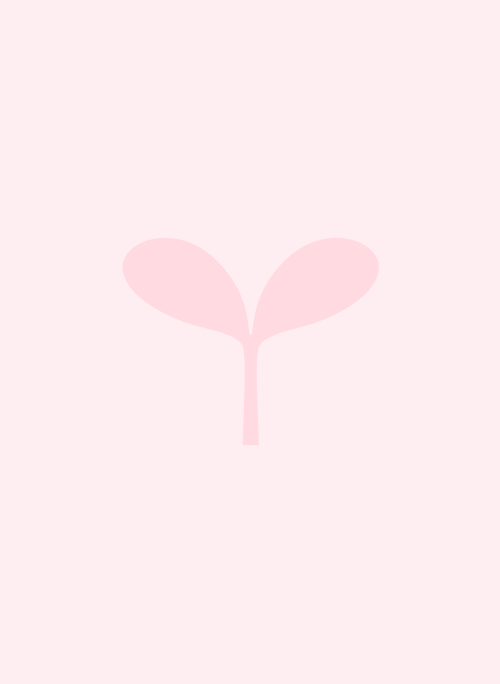「そろそろ中に入ろうか」
「美月はね、まだ木をみてる」
「そうか。ならお父さんは家に入って、美月に冷たい麦茶を持ってくるよ」
「うん」
美月はもう、オリーブの木の方を見ていた。
◇
「ただいま」
私は誰もいない家の中で、そんなことを口にした。
真っ直ぐに台所へ行き、戸棚から薬を取り出すと、掌に錠剤を開け、口に放り込んだ。傍らにあったコップは、水道水で満たした。
歯をくいしばって、ゴクリと錠剤ごと喉に流し込む。余りの激痛に、いきなり涙が吹き出た。喉を通った後にも、痛みが残り、呻き声をあげた。
少し落ち着いたところで、冷蔵庫の中から麦茶の入ったピッチャーを取り出し、取っ手のついた透明なプラスチックのコップに注ぐ。
台所からリビングを通して、大きなガラス戸からオリーブの木が見えた。
美月が触っているのか、また、サワサワと枝が揺れている。
「美月、よく冷えた麦茶だよ」
ガラス戸を開け、美月の姿を探す。麦茶の入ったコップは、すぐに細かい水滴でいっぱいになった。
「美月、どこだ?」
「……ねぇ、おとうさん」
声はすぐ後ろから聞こえた。振り返ると、美月が玄関からリビングを覗いていた。
「なんだ。中に入っていたのか。ほうら、冷たい麦茶だよ」
「おとうさん……」
美月は私が差し出した麦茶を、手にしようとしなかった。ただ、じっと、私を見ていた。
「どうしたんだ?」
しゃがんで目の高さを合わせると、美月は私の持っていた麦茶を受け取った。
「美月はね、まだ木をみてる」
「そうか。ならお父さんは家に入って、美月に冷たい麦茶を持ってくるよ」
「うん」
美月はもう、オリーブの木の方を見ていた。
◇
「ただいま」
私は誰もいない家の中で、そんなことを口にした。
真っ直ぐに台所へ行き、戸棚から薬を取り出すと、掌に錠剤を開け、口に放り込んだ。傍らにあったコップは、水道水で満たした。
歯をくいしばって、ゴクリと錠剤ごと喉に流し込む。余りの激痛に、いきなり涙が吹き出た。喉を通った後にも、痛みが残り、呻き声をあげた。
少し落ち着いたところで、冷蔵庫の中から麦茶の入ったピッチャーを取り出し、取っ手のついた透明なプラスチックのコップに注ぐ。
台所からリビングを通して、大きなガラス戸からオリーブの木が見えた。
美月が触っているのか、また、サワサワと枝が揺れている。
「美月、よく冷えた麦茶だよ」
ガラス戸を開け、美月の姿を探す。麦茶の入ったコップは、すぐに細かい水滴でいっぱいになった。
「美月、どこだ?」
「……ねぇ、おとうさん」
声はすぐ後ろから聞こえた。振り返ると、美月が玄関からリビングを覗いていた。
「なんだ。中に入っていたのか。ほうら、冷たい麦茶だよ」
「おとうさん……」
美月は私が差し出した麦茶を、手にしようとしなかった。ただ、じっと、私を見ていた。
「どうしたんだ?」
しゃがんで目の高さを合わせると、美月は私の持っていた麦茶を受け取った。