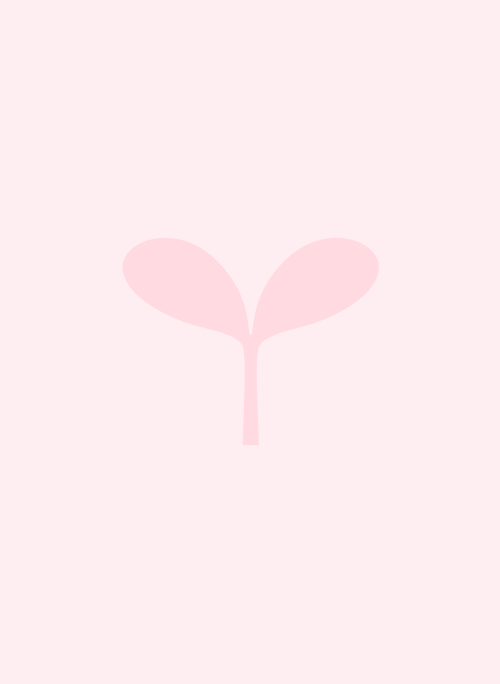「おとうさん、あれは?」
美月が後ろから、指差した。私の目には既にそれが見えていた。
「あれか? 工事だよ」
「ううん、ちがう」
「アレか?」
「うん。あれ」
「フフフ。アレはね、ウチのシンボルツリーだよ」
塀の外側のど真ん中にしっかりと植えられたスマートな木を指差したかったのだが、自転車を立ち漕ぎをしているため、私はハンドルから手を離せなかった。
「しんぼる、つりー?」
「そうだよ。シンボルツリー。オリーブの木なんだ」
これもまた、周囲から目立つ位置に植えられている。自転車を家の前に止めて、美月の腰を持って、木の前に降ろした。
「ほら、見てごらん。立派な木だろう?」
「わあー」
美月は両手を広げて、自分の背丈の3倍以上もあるオリーブの木を仰いだ。オリーブの葉は、そよ風に揺られ、サワサワと音を立てて、小さな娘を出迎えた。
「ちゃんと実がなるんだよ。オリーブの実がね。何年も掛るけど」
「それ、おいしいの?」
「そうだな。うん。実がなる頃には、美月も美味しいって言うよ」
「えー、わかんないよ」
「そうだね。難しかったね」
「さわってもいい?」
「いいさ。美月の希望も詰まってるから」
「美月のキボウ?」
「そうだよ。未来なんだ」
私は手のひらでオリーブの木を優しく撫でた。美月は美月で、私の膝辺りの木を、優しく撫でた。
それにしても、満足のいく工事の仕上がりだった。こちらの注文通り、キッチリとこなしている。いや、それ以上に頑張ってくれたようだ。
妻が好きな植物をあしらった門構えや、外壁。そしてこのオリーブの木と、申し分なかった。
美月が後ろから、指差した。私の目には既にそれが見えていた。
「あれか? 工事だよ」
「ううん、ちがう」
「アレか?」
「うん。あれ」
「フフフ。アレはね、ウチのシンボルツリーだよ」
塀の外側のど真ん中にしっかりと植えられたスマートな木を指差したかったのだが、自転車を立ち漕ぎをしているため、私はハンドルから手を離せなかった。
「しんぼる、つりー?」
「そうだよ。シンボルツリー。オリーブの木なんだ」
これもまた、周囲から目立つ位置に植えられている。自転車を家の前に止めて、美月の腰を持って、木の前に降ろした。
「ほら、見てごらん。立派な木だろう?」
「わあー」
美月は両手を広げて、自分の背丈の3倍以上もあるオリーブの木を仰いだ。オリーブの葉は、そよ風に揺られ、サワサワと音を立てて、小さな娘を出迎えた。
「ちゃんと実がなるんだよ。オリーブの実がね。何年も掛るけど」
「それ、おいしいの?」
「そうだな。うん。実がなる頃には、美月も美味しいって言うよ」
「えー、わかんないよ」
「そうだね。難しかったね」
「さわってもいい?」
「いいさ。美月の希望も詰まってるから」
「美月のキボウ?」
「そうだよ。未来なんだ」
私は手のひらでオリーブの木を優しく撫でた。美月は美月で、私の膝辺りの木を、優しく撫でた。
それにしても、満足のいく工事の仕上がりだった。こちらの注文通り、キッチリとこなしている。いや、それ以上に頑張ってくれたようだ。
妻が好きな植物をあしらった門構えや、外壁。そしてこのオリーブの木と、申し分なかった。