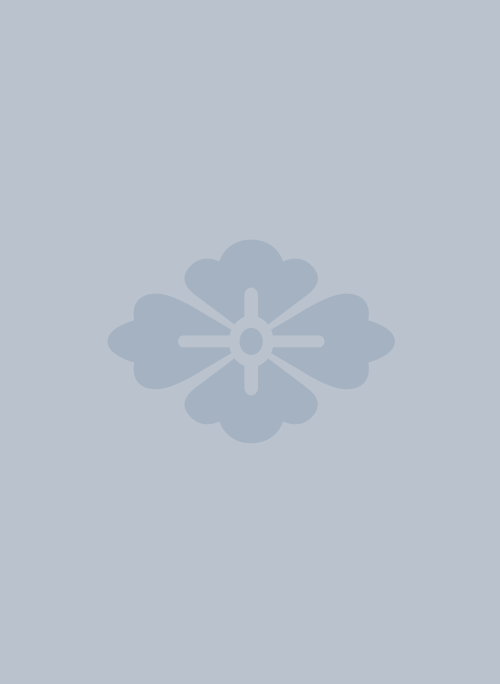激しい雷雨の中、東京駅の時計は夜の九時を指している。久しぶりの外出をした松下だった。
電車からの乗降客と雨宿りのために留まった乗客たちで、構内は大混雑だ。
諦めて雨の中に走り出す若者たちが増える中、どこといって行くあてを持たぬ松下だ。
外出と言えば聞こえは良いが、実のところは自宅マンションから逃げ出してきた。
半年ほど同居生活を送っているユカリからの逃避だ。
今日も朝からパソコンに向かっていた。
隣の居間では、これみよがしに大音量で映画に見入るユカリが居る。
「あーあ、こんなことならお店を辞めるんじゃなかったわ」
松下に向かって大声で話しかける。しかし松下からはなんの反応もない。
腹を立てたユカリ、大きく足を踏みならしながら部屋に入った。
チラリとユカリを一瞥した松下だが、なんの言葉もなくモニターに目を戻した。
ユカリはその場に立って、じっと松下を睨み付けた。
しばらくの後
「どういうつもりなの、あなた!」
と、ユカリが口を開いた。
振り向くこともなく
「なにがだ」
と松下が答えた。
見る見るユカリの顔が紅潮し
「人の目を見て話しなさいよ。失礼でしょ、そんなのって」
と、きつい口調で詰った。
「大事な場面なんだよ、今。話なら後にしてくれ!」
思わず怒鳴ってしまった。そしてうるさそうに、手で払う仕草を見せた。
「もう、頭にきた!」
そう叫ぶや否や、パソコンのコードをコンセントから引き抜いた。
画面の消えたモニターを見つめながら
「どういうつもりだ。今、どれだけの損失を出したか分かるか。
お前の年収分ぐらい、吹っ飛んだかもしれないんだぞ」
と、静かな声で言った。
「知らないわよ、そんなこと。あなたが悪いんだから」
口を尖らせるユカリに、松下の怒りが爆発した。
左頬に信じられない痛みを感じたユカリ、手に届く物を手当たり次第に投げ出した。
「許せない、許せない!」
ヒステリックに泣き叫ぶユカリに手を焼いた松下、ほうほうの体で部屋を逃げ出した。
ひとり取り残されたユカリ、その場にしゃがみ込んでしまった。自問自答を繰り返すが、答えは出ない。
“どこを間違えたの? 玉の輿に乗ったはずなのに…”
昨夜も口論となった。
中食と称される総菜類を並べるユカリに対し「たまには料理ぐらいしたらどうだ!」と、松下がこぼしたことからの口論だった。
家政婦じゃないんだから、と言い返したものの、己に非があることが分かっているユカリ、ただ泣き叫ぶしかなかった。
「あたしがどれだけの犠牲を払ったと思っているのよ。
ナンバーワンのあたしがお店を辞めて、ここに来てあげたのよ」
しかし松下の反応は冷たいものだった。
「なにが来てやった、だ。頼んだ覚えもないのに勝手に来て住み着いたんじゃないか。
ナンバーワンだ? ほのかに追い抜かれて、KAYの三人娘にも追い上げられて、青息吐息だったろうが。
ことみ・あかね、わかの三人だよ。俺の情報収集力をなめるなよ。
投資というのは、情報が命なんだよ。
そもそもあの店に通ったのは、なにもお前が気に入ったからじゃないんだ。あそこに通っていた…」
話し続ける松下の言葉が、ユカリには届かなくなった。
ナンバーワンではなくなっていたという事実、与えられていた特権を剥奪されたという事実、松下の元に逃げ込んできたという事実、それら全てを見透かされていた。
ユカリのプライドが、今、ずたずたに引き裂かれた。
ふらふらとテーブルを離れ、寝室に閉じこもった。
さすがに言い過ぎたと感じた松下、ドア越しに
「悪かった、ユカリ。言い過ぎたよ。今度、食事に行こう。
それからどうだ、もう一度パリに行かないか。明日にも相談しようじゃないか」
と、声を掛けた。
このことがあっての今日だった。
楽しみにしていたユカリに対し、松下からなんの話もない。
朝から夜になった今まで、株のチャート画面ばかりを見ている。
朝に声を掛けた折には、三台あるモニター画面の一つとして、旅行会社のサイトは出ていない。
ならば午後からにと思っても同じくで、そして夜になってもだ。
昨日の言葉はその場限りのことだったと、ユカリの気持ちが爆発した。
松下の居ない部屋で、独り取り残されたユカリ、これからのことを考えると不安でいっぱいになる。
自殺という文字が頭をかすめた。
“あてつけにやってやろうかしら”
しかしそれができない己であることは、ユカリ自身がよく知っている。
感情的になりやすいが、それとてすぐに収まってしまう。
そしてその因を分析し始める。
相手に非があってのこともあるが、その殆どは己の我がまま、思い過ごし、そして予測違いによるものだ。
そうなのだ、この分析癖が、ユカリをして突発的、衝動的行動をなかなか取らせないのだ。
「お前ならナンバーワンになれなくても、オンリーワンになれるさ」
何かの折に、松下がもらした言葉だ。
ユカリが「それって、歌でしょ」と詰め寄ると「ばれたか。でも、ほんとだぞ」と、真顔で言う松下だった。
“戻ろうかしら、また…”
早晩そうなりそうな気がしてくるユカリだった。
松下も又同じ思いにかられていた。
キャバクラに通って半年、そして同居生活を含めてもわずか一年の期間だ。
元々ユカリを指名したのは、ある意図があってのことだった。
観察力、洞察力のあることが条件だった。
はじめての入店時に、わざとみすぼらしい格好をしたのも、靴だけは高級品にしたのも、そのテストのためだった。
目立たぬ出で立ちで通い地味な金の使い方を続ける松下に対して、ユカリだけが上客だと判断した。
理由を問いただすと、「靴が高級だもの」と事もなげに言う。
そして松下の冗談めいた頼み事を、しっかりとこなしたユカリだった。
その情報で裏が取れたと判断した松下、株において大勝負を仕掛けて大金をせしめた。
なにも知らぬユカリに対し「ユカリが気に入った。パリにでも行くか?」と、褒美の旅行へと連れ出した。
有頂天になったユカリ、ここで大きな勘違いをしてしまった。
そしてそれが、今、ユカリを苦しめることになってしまった。
松下にしても疎ましさを感じ始めてきていた。
「そろそろだな…」
思わず口に出てしまった。
電車からの乗降客と雨宿りのために留まった乗客たちで、構内は大混雑だ。
諦めて雨の中に走り出す若者たちが増える中、どこといって行くあてを持たぬ松下だ。
外出と言えば聞こえは良いが、実のところは自宅マンションから逃げ出してきた。
半年ほど同居生活を送っているユカリからの逃避だ。
今日も朝からパソコンに向かっていた。
隣の居間では、これみよがしに大音量で映画に見入るユカリが居る。
「あーあ、こんなことならお店を辞めるんじゃなかったわ」
松下に向かって大声で話しかける。しかし松下からはなんの反応もない。
腹を立てたユカリ、大きく足を踏みならしながら部屋に入った。
チラリとユカリを一瞥した松下だが、なんの言葉もなくモニターに目を戻した。
ユカリはその場に立って、じっと松下を睨み付けた。
しばらくの後
「どういうつもりなの、あなた!」
と、ユカリが口を開いた。
振り向くこともなく
「なにがだ」
と松下が答えた。
見る見るユカリの顔が紅潮し
「人の目を見て話しなさいよ。失礼でしょ、そんなのって」
と、きつい口調で詰った。
「大事な場面なんだよ、今。話なら後にしてくれ!」
思わず怒鳴ってしまった。そしてうるさそうに、手で払う仕草を見せた。
「もう、頭にきた!」
そう叫ぶや否や、パソコンのコードをコンセントから引き抜いた。
画面の消えたモニターを見つめながら
「どういうつもりだ。今、どれだけの損失を出したか分かるか。
お前の年収分ぐらい、吹っ飛んだかもしれないんだぞ」
と、静かな声で言った。
「知らないわよ、そんなこと。あなたが悪いんだから」
口を尖らせるユカリに、松下の怒りが爆発した。
左頬に信じられない痛みを感じたユカリ、手に届く物を手当たり次第に投げ出した。
「許せない、許せない!」
ヒステリックに泣き叫ぶユカリに手を焼いた松下、ほうほうの体で部屋を逃げ出した。
ひとり取り残されたユカリ、その場にしゃがみ込んでしまった。自問自答を繰り返すが、答えは出ない。
“どこを間違えたの? 玉の輿に乗ったはずなのに…”
昨夜も口論となった。
中食と称される総菜類を並べるユカリに対し「たまには料理ぐらいしたらどうだ!」と、松下がこぼしたことからの口論だった。
家政婦じゃないんだから、と言い返したものの、己に非があることが分かっているユカリ、ただ泣き叫ぶしかなかった。
「あたしがどれだけの犠牲を払ったと思っているのよ。
ナンバーワンのあたしがお店を辞めて、ここに来てあげたのよ」
しかし松下の反応は冷たいものだった。
「なにが来てやった、だ。頼んだ覚えもないのに勝手に来て住み着いたんじゃないか。
ナンバーワンだ? ほのかに追い抜かれて、KAYの三人娘にも追い上げられて、青息吐息だったろうが。
ことみ・あかね、わかの三人だよ。俺の情報収集力をなめるなよ。
投資というのは、情報が命なんだよ。
そもそもあの店に通ったのは、なにもお前が気に入ったからじゃないんだ。あそこに通っていた…」
話し続ける松下の言葉が、ユカリには届かなくなった。
ナンバーワンではなくなっていたという事実、与えられていた特権を剥奪されたという事実、松下の元に逃げ込んできたという事実、それら全てを見透かされていた。
ユカリのプライドが、今、ずたずたに引き裂かれた。
ふらふらとテーブルを離れ、寝室に閉じこもった。
さすがに言い過ぎたと感じた松下、ドア越しに
「悪かった、ユカリ。言い過ぎたよ。今度、食事に行こう。
それからどうだ、もう一度パリに行かないか。明日にも相談しようじゃないか」
と、声を掛けた。
このことがあっての今日だった。
楽しみにしていたユカリに対し、松下からなんの話もない。
朝から夜になった今まで、株のチャート画面ばかりを見ている。
朝に声を掛けた折には、三台あるモニター画面の一つとして、旅行会社のサイトは出ていない。
ならば午後からにと思っても同じくで、そして夜になってもだ。
昨日の言葉はその場限りのことだったと、ユカリの気持ちが爆発した。
松下の居ない部屋で、独り取り残されたユカリ、これからのことを考えると不安でいっぱいになる。
自殺という文字が頭をかすめた。
“あてつけにやってやろうかしら”
しかしそれができない己であることは、ユカリ自身がよく知っている。
感情的になりやすいが、それとてすぐに収まってしまう。
そしてその因を分析し始める。
相手に非があってのこともあるが、その殆どは己の我がまま、思い過ごし、そして予測違いによるものだ。
そうなのだ、この分析癖が、ユカリをして突発的、衝動的行動をなかなか取らせないのだ。
「お前ならナンバーワンになれなくても、オンリーワンになれるさ」
何かの折に、松下がもらした言葉だ。
ユカリが「それって、歌でしょ」と詰め寄ると「ばれたか。でも、ほんとだぞ」と、真顔で言う松下だった。
“戻ろうかしら、また…”
早晩そうなりそうな気がしてくるユカリだった。
松下も又同じ思いにかられていた。
キャバクラに通って半年、そして同居生活を含めてもわずか一年の期間だ。
元々ユカリを指名したのは、ある意図があってのことだった。
観察力、洞察力のあることが条件だった。
はじめての入店時に、わざとみすぼらしい格好をしたのも、靴だけは高級品にしたのも、そのテストのためだった。
目立たぬ出で立ちで通い地味な金の使い方を続ける松下に対して、ユカリだけが上客だと判断した。
理由を問いただすと、「靴が高級だもの」と事もなげに言う。
そして松下の冗談めいた頼み事を、しっかりとこなしたユカリだった。
その情報で裏が取れたと判断した松下、株において大勝負を仕掛けて大金をせしめた。
なにも知らぬユカリに対し「ユカリが気に入った。パリにでも行くか?」と、褒美の旅行へと連れ出した。
有頂天になったユカリ、ここで大きな勘違いをしてしまった。
そしてそれが、今、ユカリを苦しめることになってしまった。
松下にしても疎ましさを感じ始めてきていた。
「そろそろだな…」
思わず口に出てしまった。