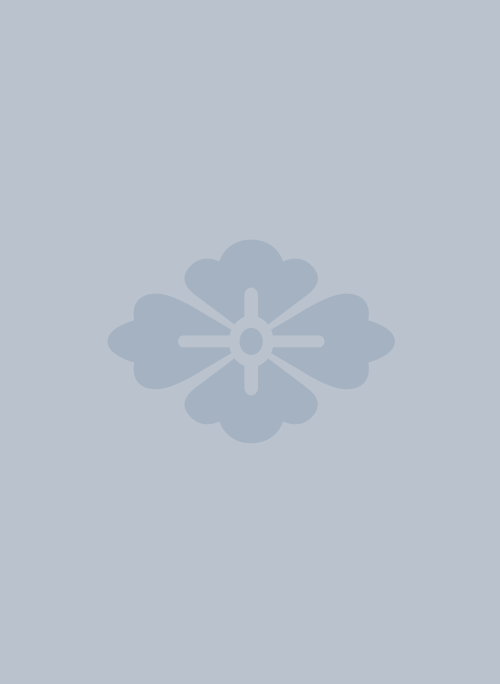今日、三十二才の誕生日を迎えた栄子。誰とて祝ってくれる人もいない。
「今さら祝ってもらう歳でもないわ」とうそぶくが、やはり心内では寂しくもある。
人気のないスタジオに一人残った栄子に、声を掛けて退出した練習生は一人もいない。
この教室ではベテランになってしまった。同期生のすべてが家庭に入り、子持ちになっている。
子供の手が離れたら戻りますから…と、みな退会してしまった。
今夜は花の金曜日、窓から見る通りには腕を組んで歩くカップルが目立つ。
四、五人のグループが信号待ちをしていたが、まだ赤信号だというのにその内の一人が車道に飛び出した。
急ブレーキを掛けてタクシーが止まり事なきを得たが、相当に酔っているように見える。
残りの者が平身低頭して、その車に謝った。しかし当の本人は、どこ吹く風とはしゃぎ回っている。
雑多な騒音が飛び交う中、部屋の中に街頭のにおいが入り込んでくる。
体にまとわりつく熱気も、栄子を苛立たせる。エアコンを切って三十分ほどが経っている。
すでに室温は三十度を優に超えた。
クルリクルリと体をターンさせて、両手を大きく上に伸ばす。
指先にスイッチを入れると、ゆっくりと柔らかく動かす。手首を軽く動かしながら、腰を軽く回していく。
体は十分に温まっている。すぐにも激しい動きに入れる。
音楽を流しながら、頭の中で動きを思い描く。カンタオールの強い声が、栄子を突き動かす。
タンタンと足を踏みならしながら、声に合わせて手をグルグルと回す。
次第に動きが大きくなり、力強くそして早くなる。どっと噴き出す汗が、ぼとりぼとりと床に滴り落ちた。
「エアコンの効いた中での練習では、スタミナが付かないのよ」
栄子の持論は、練習生とは相容れない。
趣味としてのフラメンコなのだ、栄子のようにプロを自任する者とは、一線が画される。
そしてそんな練習生が増えた今、栄子の時間が削られていく。
まったりとした空気が漂う中、ますます追い込まれていく。次第に険のある表情を見せることが多くなった。
主宰からの注意を受けることも度々だ。
踊りにおいても、力を抜きなさいと、口酸っぱく言われる。
今の精神状態では身体にも余計な負担を掛けてしまうわよと、指導を受ける。
しかし栄子に納得できはしない。
「嫉妬しているのよ」そう思っている。いや、思い込もうとしている。
つい先日に、十一月中旬のショー依頼が入った。
代役ではあったが教室としても久しぶりのことで、大いに盛り上がった。
力の入った練習が始まったのだが、栄子以外の者はすぐに音を上げた。
明らかにスタミナ不足だ。といって練習量を増やすことを、皆が嫌った。
仕事に影響が出ては困るのだ。あくまで趣味としての範囲を逸脱しない、それが皆の気持ちだった。
結局の所、栄子の踊りを増やし、全員はラストの一曲だけということになった。
更には客をステージに上げて簡単なステップの披露をすることで、一時間のショーを組み立てた。
今夜は、健二が来る予定だ。
フラメンコのギタリストではないのだが、栄子のためにとエレキギターをフラメンコギターに持ち替えて演奏してくれる。
CDによる演奏では、どうしても型どおりになってしまい、栄子の踊りができない。
舞台では演じ手の癖がある。それぞれに微妙にテンポが違うのだ。
もちろん栄子のテンポに合わせてくれる演じ手も居てくれる。
しかし栄子には、健二との相性が一番だ。
健二の奏でるギターの音色に包まれると、苛立つ気持ちも消えていく。
時計を見ると、八時半を指している。
「いつものことよ、あいつが約束を守ったことなんて、ほんの数えるほどじゃないの」
口に出してこぼしてみるが、誰も慰めてはくれない。気を取り直してCD機に手を伸ばした。
「ごめん、ごめん。遅くなっちゃったよ」
健二の声が背後から届く。決して正面切っては話をしない。
どうせ、せせら笑いをしているのだろうと栄子は思う。
ぐっとこみ上げてくる涙をこらえながら、「来てくれるとは思ってなかったわ。どういう風の吹き回しかしら?」と、せめてもと険のある言葉で返した。
「なあ、栄子。もう一度医者に診せないか。知り合いがな、大学病院の医師を紹介してくれると言うんだけど。
手術は、イヤか? 歩けなくなるかも、なんて言ってたけど…」
栄子の背に話しかける。相手の目を見て話すことが苦手な健二だ。
自分さえ持て余し気味なのだ、他人の人生を背負い込むことなど到底考えられない健二だった。
栄子に対する愛情は本物なのだ、しかし漠然とした不安が健二を押しつぶそうとしている。
「やめて、その話は! あたしは続けるのよ、まだ。トップに立つのよ。
どうなの、協力してくれる気はあるの。どうなの!」
健二の話を遮って絶叫する栄子だ。健二は無言でギターを手にした。
ゴルペ板を指先で叩きながら「カンテは誰なんだ」と、栄子に問いかけた。
右足を前に出して準備を終えた栄子が「知らないわよ、そんなこと。急な話だから、主宰も大慌てよ」と、不機嫌に答えた。
健二の演奏に合わせて、ゆっくりと背を伸ばし両手を高く掲げる。
くるりくるりと回る手首、指先もまた動き始める。
健二の甲高い声が響くと、その声に合わせて足を踏み鳴らす。
ギターのリズムが早くなると同時に両手を腰にあてがい、大きくターン。
続いてスカートの裾をつかんで大きく跳ね上げる。
片手を上げて背筋を伸ばし、大きく再度のターン。床を踏みならす靴音がより激しくなる。
額に噴き出す汗が左右に飛び散った。
「オーレ! オーレ!」の掛け声と共に指の動きも激しくなり、腰を使っての動きも強くなる。
突然ギター演奏が止まった。苦痛に歪んだ表情を見てとった健二が声を張り上げた。
「だめだ、だめだ! 引退だ、もう。床が泣いてるぞ。栄子にも分かってるだろう」
顔面蒼白で立ちすくむ栄子、ひと言も発しない。ただじっと足下を見つめて、噴き出る汗を拭こうともしない。
床にポタリポタリと滴が落ちる。汗なのか、涙なのか…。
「続けて!」
栄子の絶叫が響いた。
「今さら祝ってもらう歳でもないわ」とうそぶくが、やはり心内では寂しくもある。
人気のないスタジオに一人残った栄子に、声を掛けて退出した練習生は一人もいない。
この教室ではベテランになってしまった。同期生のすべてが家庭に入り、子持ちになっている。
子供の手が離れたら戻りますから…と、みな退会してしまった。
今夜は花の金曜日、窓から見る通りには腕を組んで歩くカップルが目立つ。
四、五人のグループが信号待ちをしていたが、まだ赤信号だというのにその内の一人が車道に飛び出した。
急ブレーキを掛けてタクシーが止まり事なきを得たが、相当に酔っているように見える。
残りの者が平身低頭して、その車に謝った。しかし当の本人は、どこ吹く風とはしゃぎ回っている。
雑多な騒音が飛び交う中、部屋の中に街頭のにおいが入り込んでくる。
体にまとわりつく熱気も、栄子を苛立たせる。エアコンを切って三十分ほどが経っている。
すでに室温は三十度を優に超えた。
クルリクルリと体をターンさせて、両手を大きく上に伸ばす。
指先にスイッチを入れると、ゆっくりと柔らかく動かす。手首を軽く動かしながら、腰を軽く回していく。
体は十分に温まっている。すぐにも激しい動きに入れる。
音楽を流しながら、頭の中で動きを思い描く。カンタオールの強い声が、栄子を突き動かす。
タンタンと足を踏みならしながら、声に合わせて手をグルグルと回す。
次第に動きが大きくなり、力強くそして早くなる。どっと噴き出す汗が、ぼとりぼとりと床に滴り落ちた。
「エアコンの効いた中での練習では、スタミナが付かないのよ」
栄子の持論は、練習生とは相容れない。
趣味としてのフラメンコなのだ、栄子のようにプロを自任する者とは、一線が画される。
そしてそんな練習生が増えた今、栄子の時間が削られていく。
まったりとした空気が漂う中、ますます追い込まれていく。次第に険のある表情を見せることが多くなった。
主宰からの注意を受けることも度々だ。
踊りにおいても、力を抜きなさいと、口酸っぱく言われる。
今の精神状態では身体にも余計な負担を掛けてしまうわよと、指導を受ける。
しかし栄子に納得できはしない。
「嫉妬しているのよ」そう思っている。いや、思い込もうとしている。
つい先日に、十一月中旬のショー依頼が入った。
代役ではあったが教室としても久しぶりのことで、大いに盛り上がった。
力の入った練習が始まったのだが、栄子以外の者はすぐに音を上げた。
明らかにスタミナ不足だ。といって練習量を増やすことを、皆が嫌った。
仕事に影響が出ては困るのだ。あくまで趣味としての範囲を逸脱しない、それが皆の気持ちだった。
結局の所、栄子の踊りを増やし、全員はラストの一曲だけということになった。
更には客をステージに上げて簡単なステップの披露をすることで、一時間のショーを組み立てた。
今夜は、健二が来る予定だ。
フラメンコのギタリストではないのだが、栄子のためにとエレキギターをフラメンコギターに持ち替えて演奏してくれる。
CDによる演奏では、どうしても型どおりになってしまい、栄子の踊りができない。
舞台では演じ手の癖がある。それぞれに微妙にテンポが違うのだ。
もちろん栄子のテンポに合わせてくれる演じ手も居てくれる。
しかし栄子には、健二との相性が一番だ。
健二の奏でるギターの音色に包まれると、苛立つ気持ちも消えていく。
時計を見ると、八時半を指している。
「いつものことよ、あいつが約束を守ったことなんて、ほんの数えるほどじゃないの」
口に出してこぼしてみるが、誰も慰めてはくれない。気を取り直してCD機に手を伸ばした。
「ごめん、ごめん。遅くなっちゃったよ」
健二の声が背後から届く。決して正面切っては話をしない。
どうせ、せせら笑いをしているのだろうと栄子は思う。
ぐっとこみ上げてくる涙をこらえながら、「来てくれるとは思ってなかったわ。どういう風の吹き回しかしら?」と、せめてもと険のある言葉で返した。
「なあ、栄子。もう一度医者に診せないか。知り合いがな、大学病院の医師を紹介してくれると言うんだけど。
手術は、イヤか? 歩けなくなるかも、なんて言ってたけど…」
栄子の背に話しかける。相手の目を見て話すことが苦手な健二だ。
自分さえ持て余し気味なのだ、他人の人生を背負い込むことなど到底考えられない健二だった。
栄子に対する愛情は本物なのだ、しかし漠然とした不安が健二を押しつぶそうとしている。
「やめて、その話は! あたしは続けるのよ、まだ。トップに立つのよ。
どうなの、協力してくれる気はあるの。どうなの!」
健二の話を遮って絶叫する栄子だ。健二は無言でギターを手にした。
ゴルペ板を指先で叩きながら「カンテは誰なんだ」と、栄子に問いかけた。
右足を前に出して準備を終えた栄子が「知らないわよ、そんなこと。急な話だから、主宰も大慌てよ」と、不機嫌に答えた。
健二の演奏に合わせて、ゆっくりと背を伸ばし両手を高く掲げる。
くるりくるりと回る手首、指先もまた動き始める。
健二の甲高い声が響くと、その声に合わせて足を踏み鳴らす。
ギターのリズムが早くなると同時に両手を腰にあてがい、大きくターン。
続いてスカートの裾をつかんで大きく跳ね上げる。
片手を上げて背筋を伸ばし、大きく再度のターン。床を踏みならす靴音がより激しくなる。
額に噴き出す汗が左右に飛び散った。
「オーレ! オーレ!」の掛け声と共に指の動きも激しくなり、腰を使っての動きも強くなる。
突然ギター演奏が止まった。苦痛に歪んだ表情を見てとった健二が声を張り上げた。
「だめだ、だめだ! 引退だ、もう。床が泣いてるぞ。栄子にも分かってるだろう」
顔面蒼白で立ちすくむ栄子、ひと言も発しない。ただじっと足下を見つめて、噴き出る汗を拭こうともしない。
床にポタリポタリと滴が落ちる。汗なのか、涙なのか…。
「続けて!」
栄子の絶叫が響いた。