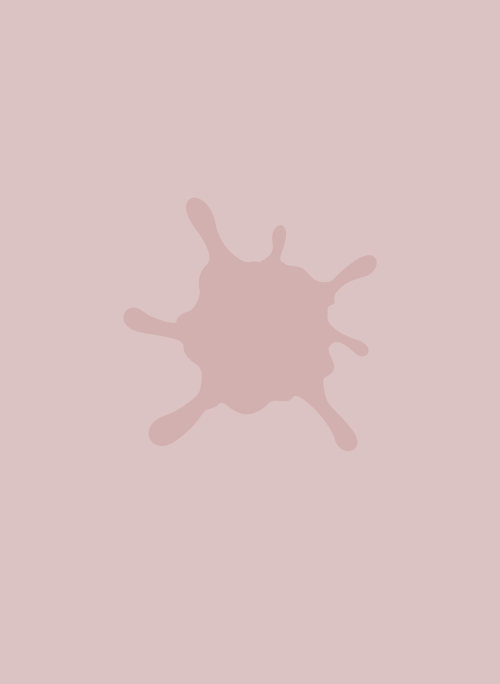千霧がそう思うのは仕方ないことだった。
側で見ていた皇は、自分の皇子の為に仕事を蔑ろになどしない人だ。
「千霧様、どうします?首を突っ込んでみますか?」
「当たり前だ!さっさとその王子を見つけ出して白王の政治を正す!」
「……御意に」
千霧は腹立ち紛れに、目の前に置かれた茶を一気に飲み干した。
*
昼間から既に薄暗い部屋に、小さく整った寝息が響いていた。
呉羽は、千霧の手入れの行き届いた滑らかな髪を指でとかしながら、寝顔を見つめていた。
部屋に通されると同時に、倒れるように眠りについてしまったのだから、だいぶ無理をしていたのだろう。
あの警戒心の強い皇子が、自分の横で、遊び疲れた子供のような顔をして眠っている。
「気付かなくてすみませんでした。……私はどうやら、人に疎いようですね」
愛しさにも似た感情をおぼえて、手を放す。
「私は貴方を護るためだけに存在する。でも貴方は違う。どんなに足掻こうと、私と貴方は違う──」
呉羽はため息をつくと、自分も目を閉じた。
隣で眠る千霧と同じ夢を望みながら。