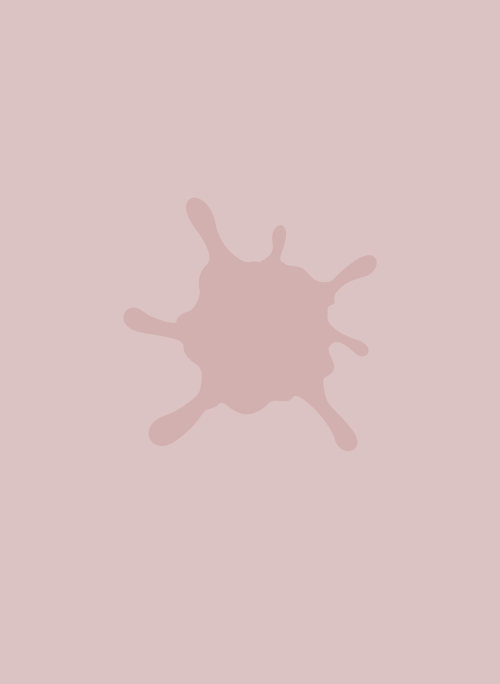「そんなに怖い顔をしなくとも大丈夫さ。別に隠しておくつもりもないしな」
珀の静かな瞳が、千珠の瞳と重なる。
千珠はゴクリ、と喉を鳴らした。
「癸火は異形ではない。しかし真っ当な人間でもないだろうな。──混血、というやつか?たぶん、蒐は癸火の血の匂いを感じるんだ」
そう語る珀は、どことなく上機嫌に見える。
「嬉しそうですね、珀様」
「そうだな。──癸火が混血なのは、この陰にとって良いことだ」
「良いこと?」
含み笑いを浮かべる珀に、千珠は眉を寄せる。
珀はさらに続けた。
「ああ、良いことだ。なんせ、癸火は“王の資質を持つ者”だからな」