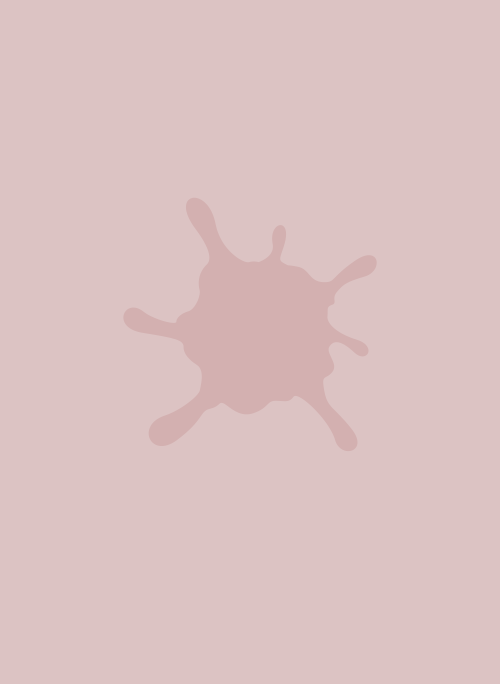会ったばかりのはずなのに、彼といる時間は不思議と気が楽だった。
それには彼が王宮の人間でないという理由もいくらかあったが、それ以上に深い『慈愛』を感じるからだろう。
愛を知らない千霧に、彼の存在は心地よかった。
本当は、直接客人と会うことは皇に固く禁じられている。
それだけ千霧の存在は皇の威厳に関わるものなのだろう。
だから今、こうして呉羽と言葉を交わせるのは奇跡に近いことだ。
王宮の人間は優しい。
でも、その優しさはうわべだけのもの。
皆、嘘で自分を塗り固めている。
それが嫌だった。
憎いなら憎いと言えばいい。
……なのに、彼らは千霧の前では取り繕っている。
そんなものは必要なかった。
「……皇子?」
我に返ると、呉羽が不思議そうにしていた。
その時、不意に外套が揺れて隙間から碧い瞳が覗いた。その瞳には、確かに見覚えがあった。
思い出そうとした途端、頭に響くような痛みが走った。
『タスケテ』
『タリナイ』
『タスケテ』
『コワイ、クライ──』
無数の声が入り交じり、重くのし掛かるような感覚をおぼえ、堪えきれずに頭を押さえる。
「うう……あ……ぁあっ!」
苦痛に顔が歪み、視界がぐらりと揺れる。
「皇子!?」
倒れそうになった千霧の身体を、呉羽が支えた。
「大丈夫……」
憎悪と嘆きの、異形の聲だ。
助けを求める、本来は異形同士にだけ伝わるはずの、特殊な声。
幼い時から千霧には聞こえてきた。
「ふ、所詮、私も異形ということか──」
「皇子?」
行かなければ。
呼んでいるなら。