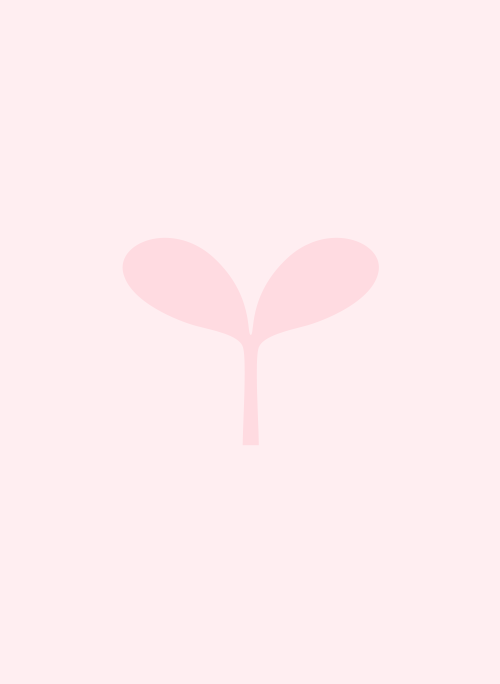*
庭先の桜が、あっという間に花開いた。
薄桃色の花たちは出来立ての綿菓子みたいにふわふわしていて、儚い。
「綺麗だねえ」
「そうだなあ。ほらシロ、籠だせ」
「あ、はいはい」
昼の営業が済んだ、暖かな午後。
私と梅之介は、今晩の料理のあしらいに使うために桜の花をとっていた。
あしらいだけでなく、塩漬けにもするらしい。
塩漬けを使った美味しい上用饅頭をつくってやるな、と眞人さんが言っていた。楽しみだ。
脚立の上に座った梅之介が桜を摘んでは、下にいる私の持つ籠に入れていく。
「もったいない気もするけど、でも綺麗」
竹籠にふわりふわりと降り積もる花たちをみるとうっとりしてしまう。
春は華やかで、いいよねえ。
「よし、と。まあこれくらいでいいかな」
梅之助が私の手の中の籠を見て言う。
「うん、いいんじゃないかな」
「ふたりとも、それくらいでいいから戻ってこい」
背後から声がして、振り返れば眞人さんが立っていた。
「団子ができたから、一緒に食おう。きな粉と黒蜜、それに餡子があるぞ」
「だんご」
なんていい響き。
思わず顔が綻ぶ私を見て、梅之介が「お前、顔に出過ぎ」と言う。
「早くきな粉に黒蜜かけて食べたい。あっついお茶が合うよねえ、なんて考えてるだろ」
「ふお! 梅之介すごい。一言一句間違えてないよ」
「わかるんだよ、お前の考えてることくらい」
ひょい、と脚立から飛び降りた梅之介が、私の手から籠を取り上げる。
「ほら、行くぞ。眞人、こいつの団子は一回り小さいのにしてやって。太るから」
「ひどい! 大丈夫だもん。あ、眞人さん、私が熱いお茶淹れますねー」
眞人さんがそんな私たちを見て、笑いながら頷く。
私たち三人の生活は、本当に上手く、楽しく進んでいた。
「んー、ほかほかで美味しい!」
真っ白で艶のあるお団子の上に、とろりとした黒蜜、それとたっぷりのきな粉をかける。
口に含めば香ばしさと濃厚な甘さが広がって、それがもちもちした触感と相まって口の中を幸せにする。
「眞人さんのつくるものは、どれも全部美味しい」
しみじみと言えば、夜営業の仕込みに入っていた眞人さんが、「その団子は、誰が作っても簡単だし、美味いぞ」と言った。
「そうかなあ。私が作ると、こうはいかないと思う」
食べながら、「やっぱり眞人さんがつくると一味違う」と独りごちる。
「そうだろうなー。お前が作ると、食べ物になるのかも怪しいもんな……」
失礼な言葉がかかる。
「むか。私だって料理くらいできます」
「へえ、それは意外ですね……」
お腹がいっぱいになった梅之介は、睡魔が襲ってきたのらしい。
声のした方向を見れば、店のテーブルのひとつに突っ伏して微睡んでいた。
お子様健在である。
あと数分もすれば、眠りの世界にいってしまうことだろう。
庭先の桜が、あっという間に花開いた。
薄桃色の花たちは出来立ての綿菓子みたいにふわふわしていて、儚い。
「綺麗だねえ」
「そうだなあ。ほらシロ、籠だせ」
「あ、はいはい」
昼の営業が済んだ、暖かな午後。
私と梅之介は、今晩の料理のあしらいに使うために桜の花をとっていた。
あしらいだけでなく、塩漬けにもするらしい。
塩漬けを使った美味しい上用饅頭をつくってやるな、と眞人さんが言っていた。楽しみだ。
脚立の上に座った梅之介が桜を摘んでは、下にいる私の持つ籠に入れていく。
「もったいない気もするけど、でも綺麗」
竹籠にふわりふわりと降り積もる花たちをみるとうっとりしてしまう。
春は華やかで、いいよねえ。
「よし、と。まあこれくらいでいいかな」
梅之助が私の手の中の籠を見て言う。
「うん、いいんじゃないかな」
「ふたりとも、それくらいでいいから戻ってこい」
背後から声がして、振り返れば眞人さんが立っていた。
「団子ができたから、一緒に食おう。きな粉と黒蜜、それに餡子があるぞ」
「だんご」
なんていい響き。
思わず顔が綻ぶ私を見て、梅之介が「お前、顔に出過ぎ」と言う。
「早くきな粉に黒蜜かけて食べたい。あっついお茶が合うよねえ、なんて考えてるだろ」
「ふお! 梅之介すごい。一言一句間違えてないよ」
「わかるんだよ、お前の考えてることくらい」
ひょい、と脚立から飛び降りた梅之介が、私の手から籠を取り上げる。
「ほら、行くぞ。眞人、こいつの団子は一回り小さいのにしてやって。太るから」
「ひどい! 大丈夫だもん。あ、眞人さん、私が熱いお茶淹れますねー」
眞人さんがそんな私たちを見て、笑いながら頷く。
私たち三人の生活は、本当に上手く、楽しく進んでいた。
「んー、ほかほかで美味しい!」
真っ白で艶のあるお団子の上に、とろりとした黒蜜、それとたっぷりのきな粉をかける。
口に含めば香ばしさと濃厚な甘さが広がって、それがもちもちした触感と相まって口の中を幸せにする。
「眞人さんのつくるものは、どれも全部美味しい」
しみじみと言えば、夜営業の仕込みに入っていた眞人さんが、「その団子は、誰が作っても簡単だし、美味いぞ」と言った。
「そうかなあ。私が作ると、こうはいかないと思う」
食べながら、「やっぱり眞人さんがつくると一味違う」と独りごちる。
「そうだろうなー。お前が作ると、食べ物になるのかも怪しいもんな……」
失礼な言葉がかかる。
「むか。私だって料理くらいできます」
「へえ、それは意外ですね……」
お腹がいっぱいになった梅之介は、睡魔が襲ってきたのらしい。
声のした方向を見れば、店のテーブルのひとつに突っ伏して微睡んでいた。
お子様健在である。
あと数分もすれば、眠りの世界にいってしまうことだろう。