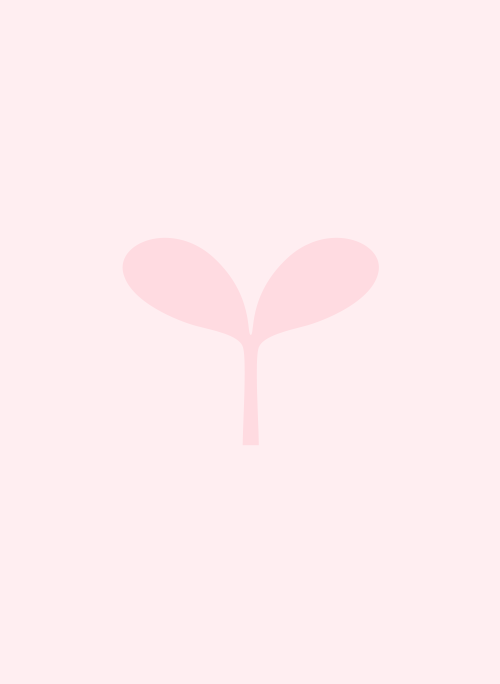背中が小さくなった頃、梅之介がため息をついた。
「わざわざ探し当てたって感じだな。向こうは、だいぶ眞人を欲しがってる」
「ねえ、華蔵ってなに?」
梅之介を見上げて訊く。私を見下ろした梅之介は、「料亭だよ」と言った。
「K市にある、知る人ぞ知る店だ」
K市……隣県にある市か。小京都だなんて呼ばれている、風情ある土地だということしか知らない。
「ふうん、料亭かあ。なるほどねえ、眞人さんの料理、美味しいもんねえ」
「ただの料亭じゃないぞ。一見さんお断りの超が付くくらいの高級料亭だ。文化人や、会社のお偉いさんなんかがこぞって利用するところで、一回の食事代は勿論ハンパない額になる」
「ふ、ふおお」
な、なんか敷居がすっごく高そう!
戻って来て下さいと言われていたってことは、眞人さんはそこで料理を作っていたことがあるんだよね。
そりゃ、どれも美味しいはずだよ、と納得してしまう。
「あの浦部って奴の話だと、眞人は何か理由があって『華蔵』を辞めたんだろうな。で、戻ってきてほしいと懇願されている、と」
「ふ、ふむふむ。どんな理由だろう」
「それだよ。なんだろうな」
梅之介と顔を見合わせる。
「すっごく、嫌がってたよね」
「ああ。どのツラ下げて戻れと、なんて言ってたし、トラブルがあったのは間違いないな」
うーん、とふたりで唸る。しかし、理由なんか思いつくはずもない。
「とりあえず、知らない顔をして戻ろう。眞人から何か言ってくれたなら、初めて知った風でいくぞ。多分、何あれって訊くのはまずい」
梅之介の言葉にこっくり頷く。
訊かれたくないこと、言いたくないことは誰にだってある。
今回のこれはきっと、眞人さんのそれに違いないと思う。
「そ、そうだね。眞人さん次第ってことで!」
「よし!」
万が一眞人さんから相談を持ちかけられたらどういう対応でいくか。
そんな打ち合わせを梅之介として、私たちは素知らぬ顔で家に帰ったのだった。
「お帰り。映画、どうだった?」
そして、私たちを出迎えた眞人さんは、いつもと変わらなかった。
「あ、よかったよ。すげえ泣けた。マチコの悲恋がさあ」
「あれ? ホラーじゃなかったか」
「ホラーだよ。だけど、泣けるの。あ、これお土産の芋羊羹だよ。食後にみんなで食べましょう」
笑いかけながら眞人さんの様子を探る。
やはり、私たちに何か言うつもりはないらしい。ごく普通の様子だった。
「おお、ありがとう。ここに店の、美味いんだよな」
紙袋を受け取る顔も、おかしなところはない。
しかし、眞人さんは何気ない口調で続けた。
「外で、誰かに会わなかったか?」
梅之介の片眉がピクリと動く。私も、動きを一瞬だけ止めてしまった。
「いや? 誰にも会わなかったよ」
梅之介が言うと、眞人さんは「そうか」とだけ返した。
「わざわざ探し当てたって感じだな。向こうは、だいぶ眞人を欲しがってる」
「ねえ、華蔵ってなに?」
梅之介を見上げて訊く。私を見下ろした梅之介は、「料亭だよ」と言った。
「K市にある、知る人ぞ知る店だ」
K市……隣県にある市か。小京都だなんて呼ばれている、風情ある土地だということしか知らない。
「ふうん、料亭かあ。なるほどねえ、眞人さんの料理、美味しいもんねえ」
「ただの料亭じゃないぞ。一見さんお断りの超が付くくらいの高級料亭だ。文化人や、会社のお偉いさんなんかがこぞって利用するところで、一回の食事代は勿論ハンパない額になる」
「ふ、ふおお」
な、なんか敷居がすっごく高そう!
戻って来て下さいと言われていたってことは、眞人さんはそこで料理を作っていたことがあるんだよね。
そりゃ、どれも美味しいはずだよ、と納得してしまう。
「あの浦部って奴の話だと、眞人は何か理由があって『華蔵』を辞めたんだろうな。で、戻ってきてほしいと懇願されている、と」
「ふ、ふむふむ。どんな理由だろう」
「それだよ。なんだろうな」
梅之介と顔を見合わせる。
「すっごく、嫌がってたよね」
「ああ。どのツラ下げて戻れと、なんて言ってたし、トラブルがあったのは間違いないな」
うーん、とふたりで唸る。しかし、理由なんか思いつくはずもない。
「とりあえず、知らない顔をして戻ろう。眞人から何か言ってくれたなら、初めて知った風でいくぞ。多分、何あれって訊くのはまずい」
梅之介の言葉にこっくり頷く。
訊かれたくないこと、言いたくないことは誰にだってある。
今回のこれはきっと、眞人さんのそれに違いないと思う。
「そ、そうだね。眞人さん次第ってことで!」
「よし!」
万が一眞人さんから相談を持ちかけられたらどういう対応でいくか。
そんな打ち合わせを梅之介として、私たちは素知らぬ顔で家に帰ったのだった。
「お帰り。映画、どうだった?」
そして、私たちを出迎えた眞人さんは、いつもと変わらなかった。
「あ、よかったよ。すげえ泣けた。マチコの悲恋がさあ」
「あれ? ホラーじゃなかったか」
「ホラーだよ。だけど、泣けるの。あ、これお土産の芋羊羹だよ。食後にみんなで食べましょう」
笑いかけながら眞人さんの様子を探る。
やはり、私たちに何か言うつもりはないらしい。ごく普通の様子だった。
「おお、ありがとう。ここに店の、美味いんだよな」
紙袋を受け取る顔も、おかしなところはない。
しかし、眞人さんは何気ない口調で続けた。
「外で、誰かに会わなかったか?」
梅之介の片眉がピクリと動く。私も、動きを一瞬だけ止めてしまった。
「いや? 誰にも会わなかったよ」
梅之介が言うと、眞人さんは「そうか」とだけ返した。