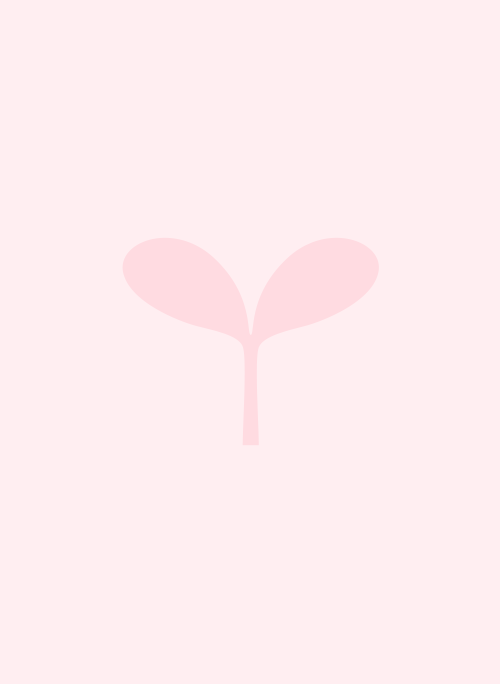今夜はクリスマスイブ。
彼氏持ちばかりの友人たちは、それぞれの幸せな夜を過ごしていることだろう。
誰に連絡を取っても、困らせるだけに違いない。
「私も、そうだと思ってたんだけど、な」
あったかい部屋で、達也の作ったご飯を食べて、クリスマスケーキも食べて。
シャンパンを飲んで、すごく美味しいよ、なんて言って笑いあう。
そんな夜を過ごせると思っていたのに。
ぐず、と鼻を啜ったと同時に、お腹が大きな音をたてた。
「そういえば、ごはん食べてないんだっけ……」
昼食を十二時に摂って以来、何も食べていない。空腹に気付くと、堪らなく苦しくなってきた。
「ごはん、食べよ」
お腹をいっぱいにすれば、この虚しさから僅かでも離れられるかもしれない。
ファストフード店でも、どこでもいいや。
冷え切った引手に手をかけ、私は痛む右足を庇いながら歩きだした。
しかし。
「ここ、どこ?」
当てもなくふらふらと彷徨っていたせいで、私はよく知らない街まで来ていたらしい。
どこをどう歩けば望む店につくのか、見当もつかない。
土地勘のないまま手ごろなお店を探してみたものの、ついには寂れかけた商店街に出てしまった。
クリスマスムードが無い代わりに、活気もない。シャッターが下りた店ばかりが並んでいた。
「どうしよ」
お腹はぐるぐると鳴り続けるし、止まない雪のせいで体の熱が奪われ、ガタガタと震える。
指先にはもう感覚がない。さながら、遭難した気分だ。
「戻るしか、ないかな」
腕時計に目を落とす。もう二十三時に差し掛かろうとしていた。
二十四時間営業のお店なんて、途中にあったかな。分かんない。
ああ、なんて最悪なクリスマス。
凍死、なんて言葉がそろそろと忍び寄ってきている気がする。
絶望感が襲ってきて、「ううー」と唸り声を上げた、その時だった。
泣きすぎて鼻づまりを起こしていた鼻腔に、奇跡的に温かな香りが侵入してきた。
これは、美味しそうなおだしの匂い。
「どこから⁉」
きょろきょろと辺りを見渡す。視線のずっと先、シャッターの道の向こうに、灯りが見えた。
まだやっているお店があるかも!
引手を握る手に最後の力を籠め、私は駆け出すようにして光に向かった。
だんだん近づいてくると、紺色の暖簾がみえた。
白い字で『小料理』と染め抜いているのが分かる。やった、飲食店だ!
と、お店の引き戸がガラリと開き、中から誰かがのそりと現れた。背の高いがっしりした、男の人のようだ。その人は、暖簾に手をかけた。
も、もしかして店じまい⁉
「ま、待って下さいぃぃ!」
思わず叫ぶと、暖簾を下ろしたその人がびくりとした。こちらを振り返る。
紬の作務衣に、真っ白の前掛け姿。料理人だろうか。
それはとっても好都合だ。
「な、なにか食べさせて下さいぃぃ!」
ああもう、このリヤカー邪魔! だけどこれ、私の全財産だし放っていけないし!
靴、すっごく走りにくい! 足痛い! だけど!
必死でガラガラとリヤカーを引き、店の前まで駆けた。暖簾を手に茫然としている男の人の服の裾を掴む。
「な、なんだ?」
「お、お願いです。ごはん、食べさせてください!」
彼氏持ちばかりの友人たちは、それぞれの幸せな夜を過ごしていることだろう。
誰に連絡を取っても、困らせるだけに違いない。
「私も、そうだと思ってたんだけど、な」
あったかい部屋で、達也の作ったご飯を食べて、クリスマスケーキも食べて。
シャンパンを飲んで、すごく美味しいよ、なんて言って笑いあう。
そんな夜を過ごせると思っていたのに。
ぐず、と鼻を啜ったと同時に、お腹が大きな音をたてた。
「そういえば、ごはん食べてないんだっけ……」
昼食を十二時に摂って以来、何も食べていない。空腹に気付くと、堪らなく苦しくなってきた。
「ごはん、食べよ」
お腹をいっぱいにすれば、この虚しさから僅かでも離れられるかもしれない。
ファストフード店でも、どこでもいいや。
冷え切った引手に手をかけ、私は痛む右足を庇いながら歩きだした。
しかし。
「ここ、どこ?」
当てもなくふらふらと彷徨っていたせいで、私はよく知らない街まで来ていたらしい。
どこをどう歩けば望む店につくのか、見当もつかない。
土地勘のないまま手ごろなお店を探してみたものの、ついには寂れかけた商店街に出てしまった。
クリスマスムードが無い代わりに、活気もない。シャッターが下りた店ばかりが並んでいた。
「どうしよ」
お腹はぐるぐると鳴り続けるし、止まない雪のせいで体の熱が奪われ、ガタガタと震える。
指先にはもう感覚がない。さながら、遭難した気分だ。
「戻るしか、ないかな」
腕時計に目を落とす。もう二十三時に差し掛かろうとしていた。
二十四時間営業のお店なんて、途中にあったかな。分かんない。
ああ、なんて最悪なクリスマス。
凍死、なんて言葉がそろそろと忍び寄ってきている気がする。
絶望感が襲ってきて、「ううー」と唸り声を上げた、その時だった。
泣きすぎて鼻づまりを起こしていた鼻腔に、奇跡的に温かな香りが侵入してきた。
これは、美味しそうなおだしの匂い。
「どこから⁉」
きょろきょろと辺りを見渡す。視線のずっと先、シャッターの道の向こうに、灯りが見えた。
まだやっているお店があるかも!
引手を握る手に最後の力を籠め、私は駆け出すようにして光に向かった。
だんだん近づいてくると、紺色の暖簾がみえた。
白い字で『小料理』と染め抜いているのが分かる。やった、飲食店だ!
と、お店の引き戸がガラリと開き、中から誰かがのそりと現れた。背の高いがっしりした、男の人のようだ。その人は、暖簾に手をかけた。
も、もしかして店じまい⁉
「ま、待って下さいぃぃ!」
思わず叫ぶと、暖簾を下ろしたその人がびくりとした。こちらを振り返る。
紬の作務衣に、真っ白の前掛け姿。料理人だろうか。
それはとっても好都合だ。
「な、なにか食べさせて下さいぃぃ!」
ああもう、このリヤカー邪魔! だけどこれ、私の全財産だし放っていけないし!
靴、すっごく走りにくい! 足痛い! だけど!
必死でガラガラとリヤカーを引き、店の前まで駆けた。暖簾を手に茫然としている男の人の服の裾を掴む。
「な、なんだ?」
「お、お願いです。ごはん、食べさせてください!」