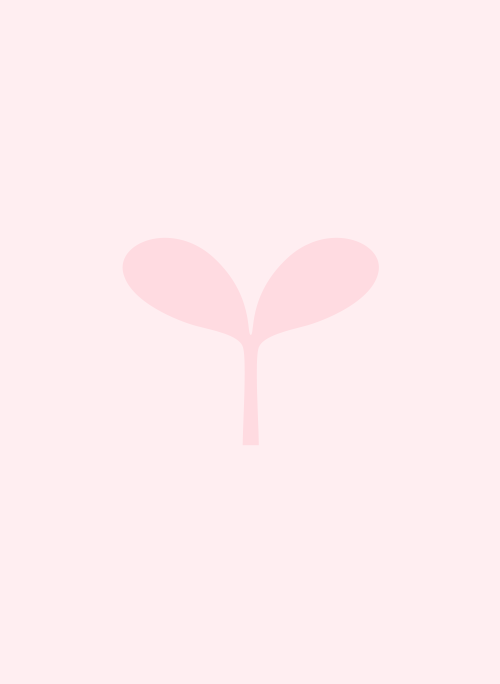「達也、まだ来てるんだ。いい加減、だっさ」
真帆が苦々しく呟くが、私は首を傾げる。
松子の声には棘なんか全然ない。むしろ喜んでいるような響きがあった。
「達也がいたら無視しな、白路」
「うん、勿論。って……」
外に出た私は、目を疑った。
そこには、眞人さんが立っていたのだ。
なんで? お店は?
って、ああそうか、今日は木曜日。定休日だ。
でもどうしてこんな所に眞人さんがいるの?
「眞人さん! やだ嬉しい! 梅之介くんが私の勤め先やシフトを訊いてきたのって、もしかして……⁉ やだ、どうしよう」
さっきまでの無愛想ぶりが嘘のようにきゃあきゃあと声を上げた松子が、近くにいた結川さんに「この人が私の言ってた人なんです」と笑いかける。
結川さんは「へえ」と気のない言葉を返した。
「うわ。例の、狙ってた男ってあれか。確かに、クズ達也よりレベルが上だわ」
私の横にいた真帆が苦々しく言う。
「どうして松子ってあんなに順風満帆なんですかね。狙った男は外さないって、スナイパーすぎでしょ」
近くにいためぐみがそう言って、「でもあれは羨ましいかも……」と続けた。
私は、目の前の光景を呆然と見つめていた。
すらりと背の高い彼に良く似合った、ベージュのジャケットに黒いシャツ、デニムのボトム。
印象的な黒い瞳は夜だというのにその魅力を削られることは無くて、どころか冴えている気さえした。
そんな彼がのんびりと煙草を燻らせる仕草は、目を奪われるに十分だった。
細く吐きだした紫煙が冬の空に溶け込んでいく。
真帆が苦々しく呟くが、私は首を傾げる。
松子の声には棘なんか全然ない。むしろ喜んでいるような響きがあった。
「達也がいたら無視しな、白路」
「うん、勿論。って……」
外に出た私は、目を疑った。
そこには、眞人さんが立っていたのだ。
なんで? お店は?
って、ああそうか、今日は木曜日。定休日だ。
でもどうしてこんな所に眞人さんがいるの?
「眞人さん! やだ嬉しい! 梅之介くんが私の勤め先やシフトを訊いてきたのって、もしかして……⁉ やだ、どうしよう」
さっきまでの無愛想ぶりが嘘のようにきゃあきゃあと声を上げた松子が、近くにいた結川さんに「この人が私の言ってた人なんです」と笑いかける。
結川さんは「へえ」と気のない言葉を返した。
「うわ。例の、狙ってた男ってあれか。確かに、クズ達也よりレベルが上だわ」
私の横にいた真帆が苦々しく言う。
「どうして松子ってあんなに順風満帆なんですかね。狙った男は外さないって、スナイパーすぎでしょ」
近くにいためぐみがそう言って、「でもあれは羨ましいかも……」と続けた。
私は、目の前の光景を呆然と見つめていた。
すらりと背の高い彼に良く似合った、ベージュのジャケットに黒いシャツ、デニムのボトム。
印象的な黒い瞳は夜だというのにその魅力を削られることは無くて、どころか冴えている気さえした。
そんな彼がのんびりと煙草を燻らせる仕草は、目を奪われるに十分だった。
細く吐きだした紫煙が冬の空に溶け込んでいく。