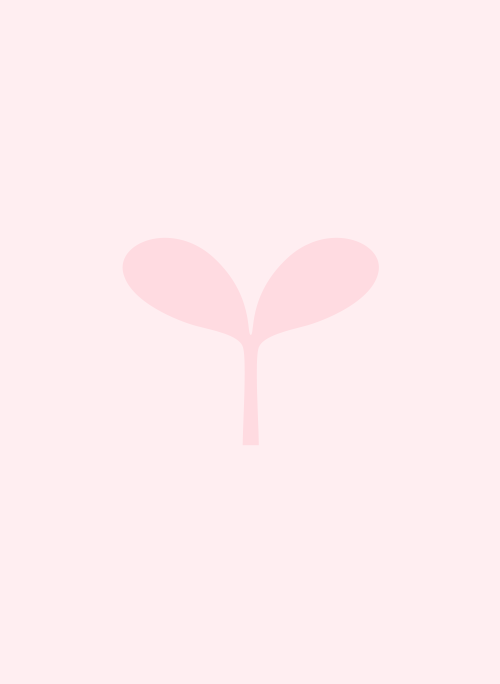数日後、松子と出勤が重なった。
先日のことがあったからか、松子は私と目も合わさない。
なにか言われるよりそっちのほうが余程楽なので、私は黙々と働いた。
そのお蔭で、トラブルも何もない一日を過ごすことができた。
「空気は、異常なくらい張りつめてたけどね。あんたたちが接近するたびに、こっちは冷や冷やしてた」
閉店作業の当番は、私だった。
真帆が手伝ってくれたので早く終わることができた。更衣室に向かいながら言う真帆に、クスリと笑ってみせた。
「喧嘩なんて、しないよ。松子ももう、何もしてこないでしょ」
松子にはもう、私を傷つけることはできない。だから、大丈夫。
「あら、妙にすっきりしてるわね」
「まあね。もう、気にしないようにしようと思ってる」
「いいことじゃない。どうせ、あとひと月程度のことだもんね。気にしないようにしたほうがいいわ」
「うん。お疲れ様でーす」
更衣室に入ると、空気が重苦しい。
見れば、松子がまだ着替えている最中だった。
他のスタッフも松子とは距離を取っているので、変な沈黙が広がっていたのだ。
「おつかれさまー」
数人の子が私たちに声をかけてくれる。
しかし松子は私を見ることもなければ、挨拶をすることもない。
私もまた、彼女の方は見ないようにして、後ろにいた真帆に笑いかけた。
「さ、着替えて帰ろう」
こんな場はさっさと離れたほうがいい、と手早く着替えを済ませた。
しかし、早く着替えすぎたらしい。ほぼ同時に、店を出ることとなった。
「逆に遅らせた方がよかったんじゃないの、白路」
「うん……、間違えたね、私」
先を歩く松子から少し離れて歩く。通用口をでた、その時だった。
「どうしてこんな所にいるんですかぁ⁉」
先に出た松子の大きな声が耳に届いた。
先日のことがあったからか、松子は私と目も合わさない。
なにか言われるよりそっちのほうが余程楽なので、私は黙々と働いた。
そのお蔭で、トラブルも何もない一日を過ごすことができた。
「空気は、異常なくらい張りつめてたけどね。あんたたちが接近するたびに、こっちは冷や冷やしてた」
閉店作業の当番は、私だった。
真帆が手伝ってくれたので早く終わることができた。更衣室に向かいながら言う真帆に、クスリと笑ってみせた。
「喧嘩なんて、しないよ。松子ももう、何もしてこないでしょ」
松子にはもう、私を傷つけることはできない。だから、大丈夫。
「あら、妙にすっきりしてるわね」
「まあね。もう、気にしないようにしようと思ってる」
「いいことじゃない。どうせ、あとひと月程度のことだもんね。気にしないようにしたほうがいいわ」
「うん。お疲れ様でーす」
更衣室に入ると、空気が重苦しい。
見れば、松子がまだ着替えている最中だった。
他のスタッフも松子とは距離を取っているので、変な沈黙が広がっていたのだ。
「おつかれさまー」
数人の子が私たちに声をかけてくれる。
しかし松子は私を見ることもなければ、挨拶をすることもない。
私もまた、彼女の方は見ないようにして、後ろにいた真帆に笑いかけた。
「さ、着替えて帰ろう」
こんな場はさっさと離れたほうがいい、と手早く着替えを済ませた。
しかし、早く着替えすぎたらしい。ほぼ同時に、店を出ることとなった。
「逆に遅らせた方がよかったんじゃないの、白路」
「うん……、間違えたね、私」
先を歩く松子から少し離れて歩く。通用口をでた、その時だった。
「どうしてこんな所にいるんですかぁ⁉」
先に出た松子の大きな声が耳に届いた。