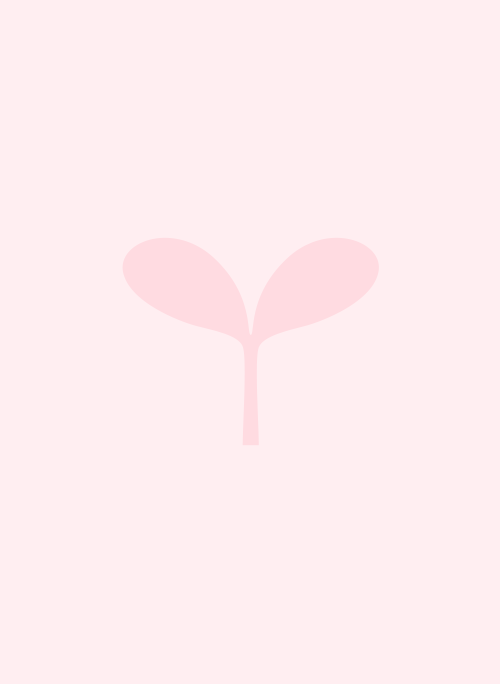達也は二ヶ月前に、務めていたジュエリーショップを辞めている。
見た目もよく、トーク技術の高い達也は女性客に人気があって、売り上げもすごくよかった。
だけど、達也の営業態度に妙な勘違いする女性が多くて、トラブルも多かった。
達也はすごく優しい。
お客様を無下には出来ない、とやんわりと断っていたけれど、中には勘違いが度を越して、部屋にまで押しかけてくる人もいた。
私も、全く知らない人に突然、達也と別れてと迫られたことが何度かあった。
『白路に嫌な思いさせてまで、この仕事したくない』
これも仕事だからと我慢していた私に達也はそう言ってくれて、惜しまれながら退職したのだった。
その行動に、私は達也の気持ちを感じていた。愛されているのだと思っていた。
次の仕事が決まるまで私はどれだけでも待つつもりでいたし、その間は支え続けると誓っていた。
なのに、どうして? こんな置手紙一つで、私は達也と終わりなの……?
『そ、それでですね、三倉さん。契約は今日でおしまいなので、今日中に出て行ってもらわないといけないんですが』
チラシの裏を呆然と見つめる私に、管理人さんが申し訳なさそうに言う。
『いつから、そんな話になってたんですか……?』
『退去の場合は……一ヶ月前にはご連絡頂いてます』
ひと月も前……。
そんなに前から、達也は別れるつもりでいたのか。
全然、気付かなかった。
そうね。達也は、自分の本心を隠すのが上手いもんね。
どれだけ嫌なお客様でも、笑顔を曇らせないのが自慢だって言ってたもんね。
『どんな些細なことでもいいから、その人のいいところを見つけるんだ。そして、一緒にいる間はそれを理由にして心から好きになる。本心からの好きが伝われば、嫌な思いをする女はいないよ』
いつかに言ったあの台詞、あれは私にも当てはまっていたのかな。
『あの、三倉さん。可哀想だけど、その』
『荷物……、運びたいので。何か運べそうなもの貸してもらえませんか?』
こんな声が自分から出るのかと思うほど低い声が出た。
管理人さんがあからさまに安堵の息を吐く。
『古いリヤカーでいいなら、あげますよ。その荷物くらいなら全部乗るでしょう』
『ありがとう、ございます』
決まりだから、ごめんねえ。そう言いながら、年配の管理人さんは私の荷物を運ぶ手伝いをしてくれて、あったかな缶コーヒーを一本くれた。
心配そうに見送る彼に会釈を一つだけして、私は行く当てもなく歩き出した。
達也と住んだマンションから少し離れると、涙が堰を切ったように溢れだした。
別れを拒むことも出来ず、思い出に身を預けることも出来ないなんて。
大切だった場所なのに、背を向けて去ることしかできない自分が憐れで、私は泣きながら足を動かしたのだった。
見た目もよく、トーク技術の高い達也は女性客に人気があって、売り上げもすごくよかった。
だけど、達也の営業態度に妙な勘違いする女性が多くて、トラブルも多かった。
達也はすごく優しい。
お客様を無下には出来ない、とやんわりと断っていたけれど、中には勘違いが度を越して、部屋にまで押しかけてくる人もいた。
私も、全く知らない人に突然、達也と別れてと迫られたことが何度かあった。
『白路に嫌な思いさせてまで、この仕事したくない』
これも仕事だからと我慢していた私に達也はそう言ってくれて、惜しまれながら退職したのだった。
その行動に、私は達也の気持ちを感じていた。愛されているのだと思っていた。
次の仕事が決まるまで私はどれだけでも待つつもりでいたし、その間は支え続けると誓っていた。
なのに、どうして? こんな置手紙一つで、私は達也と終わりなの……?
『そ、それでですね、三倉さん。契約は今日でおしまいなので、今日中に出て行ってもらわないといけないんですが』
チラシの裏を呆然と見つめる私に、管理人さんが申し訳なさそうに言う。
『いつから、そんな話になってたんですか……?』
『退去の場合は……一ヶ月前にはご連絡頂いてます』
ひと月も前……。
そんなに前から、達也は別れるつもりでいたのか。
全然、気付かなかった。
そうね。達也は、自分の本心を隠すのが上手いもんね。
どれだけ嫌なお客様でも、笑顔を曇らせないのが自慢だって言ってたもんね。
『どんな些細なことでもいいから、その人のいいところを見つけるんだ。そして、一緒にいる間はそれを理由にして心から好きになる。本心からの好きが伝われば、嫌な思いをする女はいないよ』
いつかに言ったあの台詞、あれは私にも当てはまっていたのかな。
『あの、三倉さん。可哀想だけど、その』
『荷物……、運びたいので。何か運べそうなもの貸してもらえませんか?』
こんな声が自分から出るのかと思うほど低い声が出た。
管理人さんがあからさまに安堵の息を吐く。
『古いリヤカーでいいなら、あげますよ。その荷物くらいなら全部乗るでしょう』
『ありがとう、ございます』
決まりだから、ごめんねえ。そう言いながら、年配の管理人さんは私の荷物を運ぶ手伝いをしてくれて、あったかな缶コーヒーを一本くれた。
心配そうに見送る彼に会釈を一つだけして、私は行く当てもなく歩き出した。
達也と住んだマンションから少し離れると、涙が堰を切ったように溢れだした。
別れを拒むことも出来ず、思い出に身を預けることも出来ないなんて。
大切だった場所なのに、背を向けて去ることしかできない自分が憐れで、私は泣きながら足を動かしたのだった。