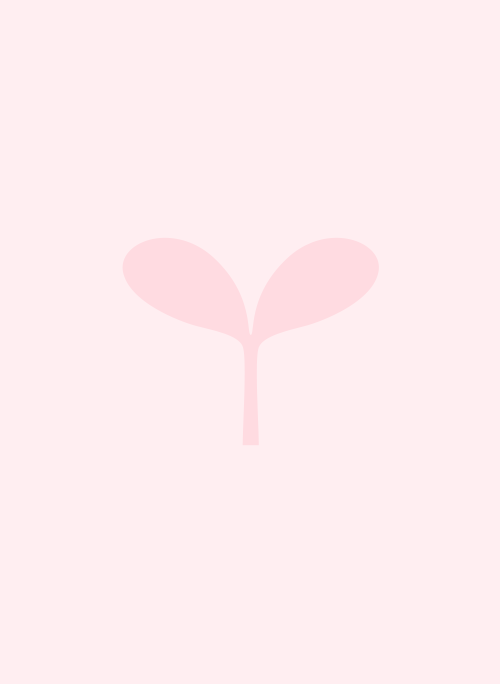次に目覚めた時には、私はひとりだった。
障子越しにさんさんと光が差し込んできて、その眩さに目覚めた私は即座に周囲を確認したが、部屋には私しかいなかったのだ。
「あれ……」
一体、どれくらい寝ていたんだっけ。ていうか、眞人さんは?
目を擦りながら首を傾げる。
そんな私の鼻先を、美味しそうな香りが漂った。
そうか、眞人さんはもう起きたんだ。
「ええと今何時……」
壁にかけられた時計を見上げて、「ぎゃ」と声を上げた。もう、昼に差し掛かろうとしていた。
「は、早く起きなきゃ!」
飛び起きた私は、慌てて服を着替えたのだった。
「……おはよ、ございます」
挨拶をしなくちゃ。お詫びをしなくちゃ。
だけど、どんな顔をしていけばいいの。恥ずかしくて死にそう。
眞人さんだって、気まずい思いをしてるんじゃないかな。
いくら私があんなに迫ったとはいえ、ひとつのお布団に寝ていたわけだし……。
そんな感じで扉の前で逡巡すること、十分。
身支度を整えた私は何度も深呼吸を繰り返したのち、意を決して厨房の扉を開けた。
「おう、起きた? おはよ」
しかし迎えてくれた眞人さんは、ごく普通の様子で料理を作っていた。
ことことと小鍋が煮立ち、蓋の隙間から湯気が上がっている。
「今昼飯作ってるから、待ってな。簡単なものだけど、いい?」
「それは勿論。ありがとうございます。あ、あの。昨日の夜のこと、なんですが」
もぐもぐと言葉を探していると、眞人さんが振り返って「俺、ガキの頃犬を飼ってたんだわ」と言った。
「へ? は、はあ。犬ですか」
「そう。サチっていうプードルなんだけど。すっげえ可愛がってて、あいつも俺に懐いてて。いつも一緒に寝てたんだよ」
眞人さんは懐かしそうに目を細めた。
どうして今ここで飼い犬の話を? と首を傾げてしまうが、私は黙って頷いた。
「冬になるとすげえあったかったんだよなあ。でさ、昨日、サチの夢見た」
「は?」
「シロって、サチと毛並みが一緒なんだなー。そのふわふわした頭の感触で、思いだした」
しみじみとそう言って、眞人さんは笑った。
「よく寝られた。ありがとな」
「は、はあ」
予想外の言葉をかけられて、目をぱちぱちさせる。
犬。犬か私。
まあ、いいけど。
あ!
ああ、なるほど。
私の事を女として意識してないから大丈夫だって安心させてくれてるのか。気にするなって、そういうことか。
……いい人! 眞人さんってすごくいい人だよ!
障子越しにさんさんと光が差し込んできて、その眩さに目覚めた私は即座に周囲を確認したが、部屋には私しかいなかったのだ。
「あれ……」
一体、どれくらい寝ていたんだっけ。ていうか、眞人さんは?
目を擦りながら首を傾げる。
そんな私の鼻先を、美味しそうな香りが漂った。
そうか、眞人さんはもう起きたんだ。
「ええと今何時……」
壁にかけられた時計を見上げて、「ぎゃ」と声を上げた。もう、昼に差し掛かろうとしていた。
「は、早く起きなきゃ!」
飛び起きた私は、慌てて服を着替えたのだった。
「……おはよ、ございます」
挨拶をしなくちゃ。お詫びをしなくちゃ。
だけど、どんな顔をしていけばいいの。恥ずかしくて死にそう。
眞人さんだって、気まずい思いをしてるんじゃないかな。
いくら私があんなに迫ったとはいえ、ひとつのお布団に寝ていたわけだし……。
そんな感じで扉の前で逡巡すること、十分。
身支度を整えた私は何度も深呼吸を繰り返したのち、意を決して厨房の扉を開けた。
「おう、起きた? おはよ」
しかし迎えてくれた眞人さんは、ごく普通の様子で料理を作っていた。
ことことと小鍋が煮立ち、蓋の隙間から湯気が上がっている。
「今昼飯作ってるから、待ってな。簡単なものだけど、いい?」
「それは勿論。ありがとうございます。あ、あの。昨日の夜のこと、なんですが」
もぐもぐと言葉を探していると、眞人さんが振り返って「俺、ガキの頃犬を飼ってたんだわ」と言った。
「へ? は、はあ。犬ですか」
「そう。サチっていうプードルなんだけど。すっげえ可愛がってて、あいつも俺に懐いてて。いつも一緒に寝てたんだよ」
眞人さんは懐かしそうに目を細めた。
どうして今ここで飼い犬の話を? と首を傾げてしまうが、私は黙って頷いた。
「冬になるとすげえあったかったんだよなあ。でさ、昨日、サチの夢見た」
「は?」
「シロって、サチと毛並みが一緒なんだなー。そのふわふわした頭の感触で、思いだした」
しみじみとそう言って、眞人さんは笑った。
「よく寝られた。ありがとな」
「は、はあ」
予想外の言葉をかけられて、目をぱちぱちさせる。
犬。犬か私。
まあ、いいけど。
あ!
ああ、なるほど。
私の事を女として意識してないから大丈夫だって安心させてくれてるのか。気にするなって、そういうことか。
……いい人! 眞人さんってすごくいい人だよ!