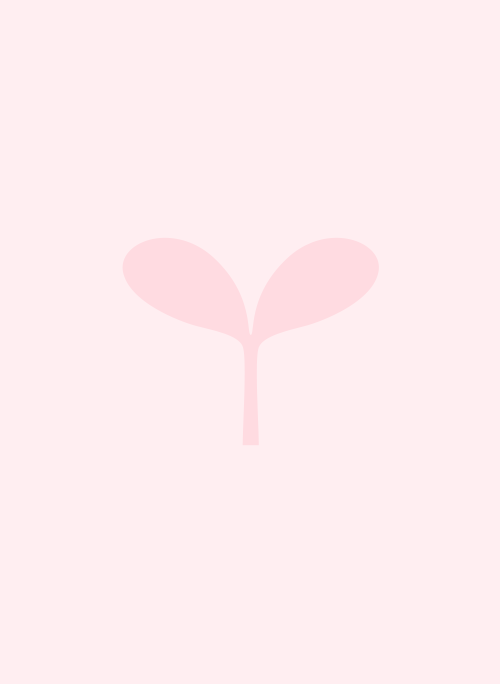リヤカーの前で立ちすくむ私に、梅之介が言う。
「行こう、白路。……ああ、ちょうどよかったじゃないか。ほら、見送りが来たぞ」
梅之介が、私の背後に視線をやって皮肉に言った。振り返れば、眞人さんがいた。
無表情の眞人さんは、荷物の乗ったリヤカーをじっと見ていた。
「あ……」
「眞人。お世話になりました。僕と白路は、出て行きます」
梅之介が、高らかに言う。
「青森で、頑張ってよね」
「……ああ」
「元気で。行くよ、白路」
ああ、もう、本当に、最後なんだ。
もう少し、もう少し一緒に、と思うけれど、そんな事を言い出したら、私はずっと離れられない。
梅之介の言葉に従って、ここを去った方がいいのかもしれない。
心を決めて、眞人さんと、向き合った。
大好きな瞳を、真っ直ぐに見る。
私を助けてくれた、とても大好きな人。
あなたに会えてよかった。
ずっと。
ずっと甘やかして欲しいと願ったこともあったけれど。
それは、叶うはずのない夢。
束の間でも、あんな時間を与えてもらったことを幸福だと思おう。
「眞人さん」
「ああ」
「今まで、ありがとう。私、ここでの生活を忘れない」
「……ああ」
眞人さんの顔が、歪んだ。
少しくらい、私の事を想ってくれたのかな。
別れを、惜しむくらいには。
それは、すごく嬉しいよ。
「……『飼い犬』として、本当に幸せだった。じゃあ、」
ぐっと喉元に熱が込みあげる。それを必死で堪えて、笑顔を作った。
「さようなら」
最後くらい、笑っていたい。その一心で、私は顔を作った。
「さよう……なら」
眞人さんが、別れの言葉を口にした。
「行くぞ、白路」
リヤカーを引いた梅之介が言う。
「うん」
踵を返して、先を行く梅之介の後に続く。
門を出て、薄闇の広がる商店街へと歩き出した。
数ヶ月前、雪の中泣きながらリヤカーを引いた。
世界で自分が一番不幸だと泣いた私だったけれど、今の方が、辛い。
ぼろぼろと零れ落ちる涙を拭う力もなくて、私はただ、梅之介の後ろを歩いた。
梅之介は何も言わずに、いうことをきかないリヤカーを引いてくれた。
どれだけ私がしゃくり上げようとも、「泣くな」とは言わなかった。
それはきっと、どれだけでも泣いていいということなのだろう。
「行こう、白路。……ああ、ちょうどよかったじゃないか。ほら、見送りが来たぞ」
梅之介が、私の背後に視線をやって皮肉に言った。振り返れば、眞人さんがいた。
無表情の眞人さんは、荷物の乗ったリヤカーをじっと見ていた。
「あ……」
「眞人。お世話になりました。僕と白路は、出て行きます」
梅之介が、高らかに言う。
「青森で、頑張ってよね」
「……ああ」
「元気で。行くよ、白路」
ああ、もう、本当に、最後なんだ。
もう少し、もう少し一緒に、と思うけれど、そんな事を言い出したら、私はずっと離れられない。
梅之介の言葉に従って、ここを去った方がいいのかもしれない。
心を決めて、眞人さんと、向き合った。
大好きな瞳を、真っ直ぐに見る。
私を助けてくれた、とても大好きな人。
あなたに会えてよかった。
ずっと。
ずっと甘やかして欲しいと願ったこともあったけれど。
それは、叶うはずのない夢。
束の間でも、あんな時間を与えてもらったことを幸福だと思おう。
「眞人さん」
「ああ」
「今まで、ありがとう。私、ここでの生活を忘れない」
「……ああ」
眞人さんの顔が、歪んだ。
少しくらい、私の事を想ってくれたのかな。
別れを、惜しむくらいには。
それは、すごく嬉しいよ。
「……『飼い犬』として、本当に幸せだった。じゃあ、」
ぐっと喉元に熱が込みあげる。それを必死で堪えて、笑顔を作った。
「さようなら」
最後くらい、笑っていたい。その一心で、私は顔を作った。
「さよう……なら」
眞人さんが、別れの言葉を口にした。
「行くぞ、白路」
リヤカーを引いた梅之介が言う。
「うん」
踵を返して、先を行く梅之介の後に続く。
門を出て、薄闇の広がる商店街へと歩き出した。
数ヶ月前、雪の中泣きながらリヤカーを引いた。
世界で自分が一番不幸だと泣いた私だったけれど、今の方が、辛い。
ぼろぼろと零れ落ちる涙を拭う力もなくて、私はただ、梅之介の後ろを歩いた。
梅之介は何も言わずに、いうことをきかないリヤカーを引いてくれた。
どれだけ私がしゃくり上げようとも、「泣くな」とは言わなかった。
それはきっと、どれだけでも泣いていいということなのだろう。