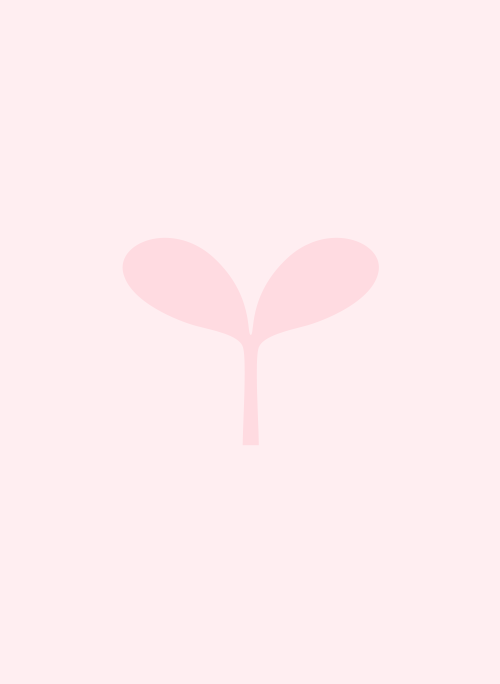食事は、ゆっくりと進む。
時折、梅之介と「美味しいね」と言い合いながら食べるのは、とても幸せだった。
「さて、次はシロの好きなものだな」
そうして、かいがいしく動く眞人さんが私の前に置いたのは、扇形の、翡翠色をしたお皿だった。
美味しい食事というのは、どうしてこんなにも心をほぐすのだろう。
気付けば、あんなにしかめっ面をしていた梅之介までもが笑顔になって、箸を動かしていた。
ビールを飲み、眞人さんと軽口を交わす。
時折私も混じって、三人で笑い合った。
ああ、なんて贅沢で素敵な時間を、私はここで過ごしてきたんだろう。
笑い過ぎて目じりに滲んだ涙を拭いながら、この時間がいつまでも続けばいいのにと思う。
いつまでも、いつまでも。
三人でこうして、美味しいねって笑い合っていられたら。
だけど、いずれ終わりは来るのだ。
「……もう、おしまい」
最後の料理である、紫芋の葛饅頭を食べ終えた私が、ぽつりと呟いた。
それは、誰かに聴いて欲しかったわけではなく、思いが口から勝手に零れただけのことだった。
「……そうだな」
梅之介が、応える。
「最後の食事は、これにて終了、だ」
ぱちりと、梅之介がお箸を置く音が響いた。それは、終了の合図でもあった。
「これで、おしまい。今まで、ありがと、ね……」
涙が勝手に溢れる。それはすぐに、ぽたりと落ちた。
ず、と鼻を啜り、涙を拭う。
そんな私の頭に、大きな手のひらが乗った。
「泣くな」
「ありがと……、眞、人、さん。私……」
もう、言葉が出てこない。ただ、何度も何度もお礼を言った。
「俺こそ、ありがとう。もう家族なんて持つことはないと思ってたのに、お前たちみたいないい奴らと出会えて、一緒に居られて、よかった」
眞人さんの言葉に、何度も頷く。
私も、そうだ。
家族のいない私には、この温もりはとても心地よかった。
もうとっくの昔に失って、もう二度と手に入らないかもしれないとも思っていたもの。
「泣くなよ、白路。終わりだってことは、もう分かってたことだろ」
梅之介が少し怒ったように言う。
「あ、ごめん。そうだよね、うん」
どうにか涙をこらえ、手の甲で濡れた頬を拭う。
頭に乗った眞人さんの手を取り、それからそっと押し返した。笑顔を作る。
「じゃあ、『飼い犬』も、もうおしまいだね」
そう言うと、眞人さんが息を飲んだ。
「今まで、ありがとうございました」
深く、頭を下げた。
「眞人、さん?」
長くそうしていたけれど、返事がない。
無言に訝しさを感じて顔を上げると、眞人さんが奇妙に顔を歪めていた。
「どうか、した?」
「……いや、なんでもない。そうだな、おしまい、だな」
はは、と力なく笑って、眞人さんがジョッキを取る。
中身を飲み干して息をついた眞人さんは、もう一度虚ろに笑った。
時折、梅之介と「美味しいね」と言い合いながら食べるのは、とても幸せだった。
「さて、次はシロの好きなものだな」
そうして、かいがいしく動く眞人さんが私の前に置いたのは、扇形の、翡翠色をしたお皿だった。
美味しい食事というのは、どうしてこんなにも心をほぐすのだろう。
気付けば、あんなにしかめっ面をしていた梅之介までもが笑顔になって、箸を動かしていた。
ビールを飲み、眞人さんと軽口を交わす。
時折私も混じって、三人で笑い合った。
ああ、なんて贅沢で素敵な時間を、私はここで過ごしてきたんだろう。
笑い過ぎて目じりに滲んだ涙を拭いながら、この時間がいつまでも続けばいいのにと思う。
いつまでも、いつまでも。
三人でこうして、美味しいねって笑い合っていられたら。
だけど、いずれ終わりは来るのだ。
「……もう、おしまい」
最後の料理である、紫芋の葛饅頭を食べ終えた私が、ぽつりと呟いた。
それは、誰かに聴いて欲しかったわけではなく、思いが口から勝手に零れただけのことだった。
「……そうだな」
梅之介が、応える。
「最後の食事は、これにて終了、だ」
ぱちりと、梅之介がお箸を置く音が響いた。それは、終了の合図でもあった。
「これで、おしまい。今まで、ありがと、ね……」
涙が勝手に溢れる。それはすぐに、ぽたりと落ちた。
ず、と鼻を啜り、涙を拭う。
そんな私の頭に、大きな手のひらが乗った。
「泣くな」
「ありがと……、眞、人、さん。私……」
もう、言葉が出てこない。ただ、何度も何度もお礼を言った。
「俺こそ、ありがとう。もう家族なんて持つことはないと思ってたのに、お前たちみたいないい奴らと出会えて、一緒に居られて、よかった」
眞人さんの言葉に、何度も頷く。
私も、そうだ。
家族のいない私には、この温もりはとても心地よかった。
もうとっくの昔に失って、もう二度と手に入らないかもしれないとも思っていたもの。
「泣くなよ、白路。終わりだってことは、もう分かってたことだろ」
梅之介が少し怒ったように言う。
「あ、ごめん。そうだよね、うん」
どうにか涙をこらえ、手の甲で濡れた頬を拭う。
頭に乗った眞人さんの手を取り、それからそっと押し返した。笑顔を作る。
「じゃあ、『飼い犬』も、もうおしまいだね」
そう言うと、眞人さんが息を飲んだ。
「今まで、ありがとうございました」
深く、頭を下げた。
「眞人、さん?」
長くそうしていたけれど、返事がない。
無言に訝しさを感じて顔を上げると、眞人さんが奇妙に顔を歪めていた。
「どうか、した?」
「……いや、なんでもない。そうだな、おしまい、だな」
はは、と力なく笑って、眞人さんがジョッキを取る。
中身を飲み干して息をついた眞人さんは、もう一度虚ろに笑った。