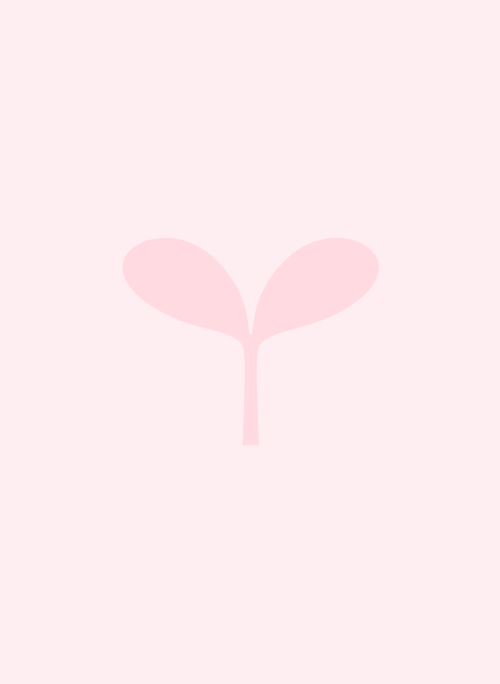「シロの強さが、好きだ。どんな酷い目にあっても、涙をこらえてニコニコ笑って頑張るお前が、俺にはいつだって眩しかった。俺の作るメシを、いつだって美味しそう食う姿を可愛いと思った。素直で真っ直ぐなシロが、俺も好きだ」
「……。うん」
泣き出しそうになるのを、必死に堪える。
どれだけ手を動かしても、花弁はひとひらも私の手の中に納まってくれない。
こんなに、降り注いでいるのに。
「でも、それは、『飼い犬』への想いだ」
果たして、眞人さんが言う。胸の奥がずきりと痛んだ。
「……う、ん」
「俺に懐いてくれるから、可愛いと思う。俺に素直だから、愛しいと思う。そんな感情なんだ。お前は俺にとって、『飼い犬』なんだ」
「……ん」
花弁はきっと、掴めない。
諦めて、手を降ろした。膝の上に置き、ぎゅっとこぶしを作る。
「だから、その立場にいて欲しい。そこから出ないでほしい。お前とのせっかくの関係を、嫌なものに変えたくないんだ」
大丈夫だよ、白路。
こんなの、ショックを受けることじゃない。
眞人さんに想いを受け入れてもらえるなんて、思ってなかったでしょう。
拒否されなかっただけ、いいじゃない。
「悪いと、思ってる。だから……」
眞人さんが困ってる。言葉を選んでる。それが、痛いくらい分かる。
「ごめんね、私、困らせてる、ね……」
声が、震えた。気を緩めたら、張りつめてる気持ちがはち切れて、涙となって溢れてしまう。
でも、ここで泣いたらダメだ。だって、眞人さんをもっと困らせてしまう。
「分かって、たの。言うつもりなんてなかったの。私は、『飼い犬』でよくて、本当にそれでよくて、なのに……」
「ごめん」
黙って、首を横に振った。
「いいの……。ちゃんと話してくれて、ありがとう」
ぐっとお腹に力を入れて、笑顔を作る。
ここは、笑うところだ。
眞人さんが真摯に向かい合ってくれたんだもの。
私も、それに応えなくちゃ。
「お蔭で、すっきりした」
声も、明るくする。
そうしたら、眞人さんが少しだけほっとしたような息をついた。
よかった、私の為に暗い顔をする眞人さんなんて、見たくない。
「……。うん」
泣き出しそうになるのを、必死に堪える。
どれだけ手を動かしても、花弁はひとひらも私の手の中に納まってくれない。
こんなに、降り注いでいるのに。
「でも、それは、『飼い犬』への想いだ」
果たして、眞人さんが言う。胸の奥がずきりと痛んだ。
「……う、ん」
「俺に懐いてくれるから、可愛いと思う。俺に素直だから、愛しいと思う。そんな感情なんだ。お前は俺にとって、『飼い犬』なんだ」
「……ん」
花弁はきっと、掴めない。
諦めて、手を降ろした。膝の上に置き、ぎゅっとこぶしを作る。
「だから、その立場にいて欲しい。そこから出ないでほしい。お前とのせっかくの関係を、嫌なものに変えたくないんだ」
大丈夫だよ、白路。
こんなの、ショックを受けることじゃない。
眞人さんに想いを受け入れてもらえるなんて、思ってなかったでしょう。
拒否されなかっただけ、いいじゃない。
「悪いと、思ってる。だから……」
眞人さんが困ってる。言葉を選んでる。それが、痛いくらい分かる。
「ごめんね、私、困らせてる、ね……」
声が、震えた。気を緩めたら、張りつめてる気持ちがはち切れて、涙となって溢れてしまう。
でも、ここで泣いたらダメだ。だって、眞人さんをもっと困らせてしまう。
「分かって、たの。言うつもりなんてなかったの。私は、『飼い犬』でよくて、本当にそれでよくて、なのに……」
「ごめん」
黙って、首を横に振った。
「いいの……。ちゃんと話してくれて、ありがとう」
ぐっとお腹に力を入れて、笑顔を作る。
ここは、笑うところだ。
眞人さんが真摯に向かい合ってくれたんだもの。
私も、それに応えなくちゃ。
「お蔭で、すっきりした」
声も、明るくする。
そうしたら、眞人さんが少しだけほっとしたような息をついた。
よかった、私の為に暗い顔をする眞人さんなんて、見たくない。