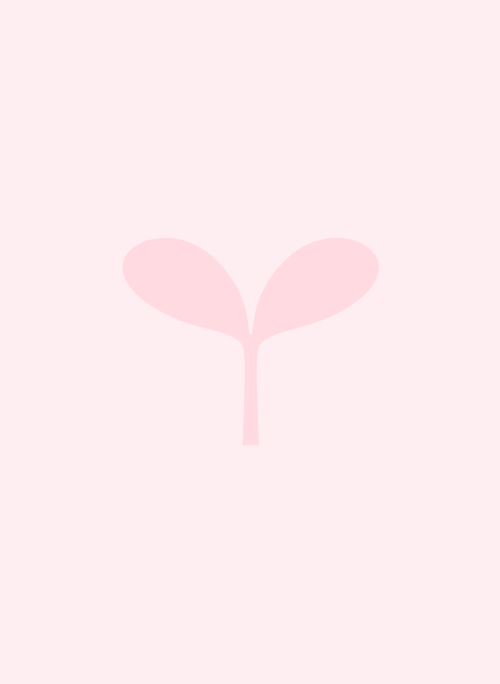「なんでもない。……あ、眞人」
ぴたりと、梅之介が足を止めた。
梅之介の言葉を間違いなく聞き漏らすまいと迫っていた私は、急に止まったせいで背中にぶつかってしまう。
「ぶえ、痛い。え、眞人さん?」
「ああ。ほら」
梅之介が前方を指差す。
ひときわ大きな桜の木の下のベンチに、眞人さんが座っていた。
ビールの缶を灰皿代わりにして、ゆっくりと紫煙を吐きだしている。
考え事をしているのか、夜空を仰ぐように上を向いていた。
「帰って来ないと思ったら、こんなところにいたか。まあ、いいタイミングなのかもしれないな」
ふ、と梅之介が息を吐く。それから、繋いでいた手をゆっくりと解いた。
振り返り、私に言う。
「行って来いよ、白路」
「え?」
「あんな勢い任せの告白を一方的にしてるんだぞ。ちゃんと、話して来いよ」
ほら、と梅之介が私を急かす。
だけど、心の準備も何もしていないのに、どうしろって言うの。
おろおろと梅之介を見ると、「行くべきだぞ」と言った。
「ちゃんと、どうしたいか伝えなきゃだろ。お前だって、さっき僕がお前に全てを丸投げしたら、困ってたはずだろ」
……それは、そうだ。
梅之助は気持ちを伝えた上で、返事はまだいらないと私に言う。今までの関係でいい、とも。
私は、すごくそれが嬉しかった。
「行って来る、私」
「ああ。僕、先に帰ってるよ。白路は、眞人と帰ってきな」
私を見下ろす梅之介が、一瞬だけ目を細めて笑った。
だけど、その笑顔はどこか寂しそうだった。
その顔を見て、は、とする。
梅之介は、眞人さんを好きな私をどんな思いで見ていたんだろう。
どうして気付かなかったんだろう。
好きな人が他の人を見てることがどれだけ苦しいか、私は知らないわけじゃない。
「ご、ごめん、梅之介! 私、すごくすごく無神経だった!」
「なんだよ、急に」
びっくりしたように眉を上げた梅之介の手を握る。
「本当に、ごめん! 私、梅之介のこと、全然考えられてなかったと思う! 梅之介、辛かったよね、ごめんなさい!」
「……なんだよ、びっくりした。謝んなくっていいよ。好きになったのは、僕の勝手だ。僕が何をどう感じようが、白路のせいじゃない」
手を解いて、梅之介は笑う。
「白路も、白路の勝手を通して来いよ。それがどんな結果になろうと、僕のことは考えなくっていい。大丈夫、僕は眞人のことも好きだから、お祝いだって言える」
「お祝い? それはないよ。だって、ありえない」
「どうかな。まあ、頑張ってきなよ」
そう言って、梅之介は本当に帰って行った。
しばらくその場に立ち尽くして背中を見つめていた私だったが、すう、と深呼吸して心を落ち着けた。
梅之介が私にしてくれたように、私もすべきだ。
ちゃんと、眞人さんと話して来よう。
勢いで告白なんてしてしまった。そのケリをちゃんとつけて来よう。
どんな結果になっても、納得しよう。
受け入れよう。
いけ、白路。
ぴたりと、梅之介が足を止めた。
梅之介の言葉を間違いなく聞き漏らすまいと迫っていた私は、急に止まったせいで背中にぶつかってしまう。
「ぶえ、痛い。え、眞人さん?」
「ああ。ほら」
梅之介が前方を指差す。
ひときわ大きな桜の木の下のベンチに、眞人さんが座っていた。
ビールの缶を灰皿代わりにして、ゆっくりと紫煙を吐きだしている。
考え事をしているのか、夜空を仰ぐように上を向いていた。
「帰って来ないと思ったら、こんなところにいたか。まあ、いいタイミングなのかもしれないな」
ふ、と梅之介が息を吐く。それから、繋いでいた手をゆっくりと解いた。
振り返り、私に言う。
「行って来いよ、白路」
「え?」
「あんな勢い任せの告白を一方的にしてるんだぞ。ちゃんと、話して来いよ」
ほら、と梅之介が私を急かす。
だけど、心の準備も何もしていないのに、どうしろって言うの。
おろおろと梅之介を見ると、「行くべきだぞ」と言った。
「ちゃんと、どうしたいか伝えなきゃだろ。お前だって、さっき僕がお前に全てを丸投げしたら、困ってたはずだろ」
……それは、そうだ。
梅之助は気持ちを伝えた上で、返事はまだいらないと私に言う。今までの関係でいい、とも。
私は、すごくそれが嬉しかった。
「行って来る、私」
「ああ。僕、先に帰ってるよ。白路は、眞人と帰ってきな」
私を見下ろす梅之介が、一瞬だけ目を細めて笑った。
だけど、その笑顔はどこか寂しそうだった。
その顔を見て、は、とする。
梅之介は、眞人さんを好きな私をどんな思いで見ていたんだろう。
どうして気付かなかったんだろう。
好きな人が他の人を見てることがどれだけ苦しいか、私は知らないわけじゃない。
「ご、ごめん、梅之介! 私、すごくすごく無神経だった!」
「なんだよ、急に」
びっくりしたように眉を上げた梅之介の手を握る。
「本当に、ごめん! 私、梅之介のこと、全然考えられてなかったと思う! 梅之介、辛かったよね、ごめんなさい!」
「……なんだよ、びっくりした。謝んなくっていいよ。好きになったのは、僕の勝手だ。僕が何をどう感じようが、白路のせいじゃない」
手を解いて、梅之介は笑う。
「白路も、白路の勝手を通して来いよ。それがどんな結果になろうと、僕のことは考えなくっていい。大丈夫、僕は眞人のことも好きだから、お祝いだって言える」
「お祝い? それはないよ。だって、ありえない」
「どうかな。まあ、頑張ってきなよ」
そう言って、梅之介は本当に帰って行った。
しばらくその場に立ち尽くして背中を見つめていた私だったが、すう、と深呼吸して心を落ち着けた。
梅之介が私にしてくれたように、私もすべきだ。
ちゃんと、眞人さんと話して来よう。
勢いで告白なんてしてしまった。そのケリをちゃんとつけて来よう。
どんな結果になっても、納得しよう。
受け入れよう。
いけ、白路。