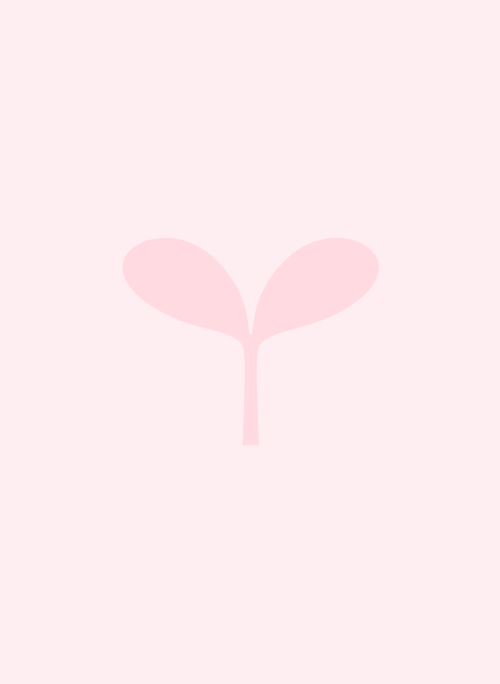「……ねえ、梅之介。私、まだ甘えてていいの?」
見上げて訊けば、梅之介は目を見開いた。それから、「ああ」と頷いた。
「いいよ。僕もお前の返事なんて聞きたくないし、お前と仲良くしていたい」
「……うん」
そっと笑って、「ありがとう」と小さくお礼を言った。
「お前は僕より年上のくせに、甘えんぼだからな」
「……うるさい」
「ふ。ほら、帰ろ」
梅之介が私に手を出す。
それを取っていいのか躊躇っていると、「行きよりも絶対に酔っ払いが増えてるぞ。何かあったら困るだろ」と掴まれた。
「まあ、お前みたいなファンキーな頭の女に手を出す酔狂な奴は、いないと思うけど」
「むか。手を離せ馬鹿」
「ほら、さっさと行くぞ」
先を歩く梅之介に引かれるようにして境内を後にした。
花見客の喧騒の中を、無言でサクサク歩く。
ぎゅっと握られた手を見ると、複雑な気持ちになる。
普通通りに話したいと思うのに、何を話していいのか分からなくなる。
見慣れた背中が、知らない人の背中にも見えた。
いつもの梅之介なのに、梅之介とはちょっとだけ違う、別の人。
眞人さんも、こんな気分だったんだろうか。
私の想いを知って、眞人さんも私が『知らない女』に見えたかもしれない。
「なあ、白路」
「……え? ん?」
ふいに梅之介に名前を呼ばれ、我に返る。
「あのさ。心配、いらない。お前は、他の女と違って眞人に拒否されたりしないよ」
梅之介は真っ直ぐ前を見たまま言う。
「ど、うして?」
「『飼い犬』だから」
「なにそれ。だから、その『飼い犬』の枠を私がいきなり飛び出して、『女』になっちゃったんだよ? 他の人と同じように拒否されることだって、十分あり得るよ」
はあ、とため息をつく。
小紅さんの登場で、眞人さんの傷は深くなったと思う。
女への嫌悪感が増していてもおかしくない。
そんなときに、私が『女』になっちゃってどうするのさ。
昼間のアレは、お前まで俺を困らせるのか、と眞人さんが思うには充分な状況だった。
「お前は、なんにもわかってないな。そんなわけ、ないよ」
「どうして断言できるのよ」
梅之介が、私の手を強く握る。
そんなに力を入れなくたって、さすがの私もはぐれたりしないのに。
「実際のお前は、犬なんかじゃない普通の女だろ」
私の方を見ることなく歩き続ける梅之介。
その声が怒っているように聞こえるのは、喧騒に負けないように少し大きな声で話しているからだろうか。
「『飼い犬』ですって名乗ってただけで、マルチーズやチワワに見える訳じゃない。その頭は、マルチーズみたいだけどな」
「うるさい」
開いた方の手で背中をポコンと叩く。梅之介は続けた。
「眞人が傍に置いてたのは、お前だってこと!」
首を傾げる。
向かいから、大学生らしき集団がやって来た。
酷く酔っ払っているみたいで、みんな大きな声で笑いあっている。
少し端に寄りながら、梅之介に言った。
「それは分かってるけど、梅之介の言いたいことはよく分かんない。分かりやすく言ってよ」
「お前を一番、『飼い犬』ってカテゴリに居させたがっていたのは多分…………」
すれ違いざま、ひときわ大きな笑い声が響いた。
「え? ごめん、聞こえなかった。なに」
見上げて訊けば、梅之介は目を見開いた。それから、「ああ」と頷いた。
「いいよ。僕もお前の返事なんて聞きたくないし、お前と仲良くしていたい」
「……うん」
そっと笑って、「ありがとう」と小さくお礼を言った。
「お前は僕より年上のくせに、甘えんぼだからな」
「……うるさい」
「ふ。ほら、帰ろ」
梅之介が私に手を出す。
それを取っていいのか躊躇っていると、「行きよりも絶対に酔っ払いが増えてるぞ。何かあったら困るだろ」と掴まれた。
「まあ、お前みたいなファンキーな頭の女に手を出す酔狂な奴は、いないと思うけど」
「むか。手を離せ馬鹿」
「ほら、さっさと行くぞ」
先を歩く梅之介に引かれるようにして境内を後にした。
花見客の喧騒の中を、無言でサクサク歩く。
ぎゅっと握られた手を見ると、複雑な気持ちになる。
普通通りに話したいと思うのに、何を話していいのか分からなくなる。
見慣れた背中が、知らない人の背中にも見えた。
いつもの梅之介なのに、梅之介とはちょっとだけ違う、別の人。
眞人さんも、こんな気分だったんだろうか。
私の想いを知って、眞人さんも私が『知らない女』に見えたかもしれない。
「なあ、白路」
「……え? ん?」
ふいに梅之介に名前を呼ばれ、我に返る。
「あのさ。心配、いらない。お前は、他の女と違って眞人に拒否されたりしないよ」
梅之介は真っ直ぐ前を見たまま言う。
「ど、うして?」
「『飼い犬』だから」
「なにそれ。だから、その『飼い犬』の枠を私がいきなり飛び出して、『女』になっちゃったんだよ? 他の人と同じように拒否されることだって、十分あり得るよ」
はあ、とため息をつく。
小紅さんの登場で、眞人さんの傷は深くなったと思う。
女への嫌悪感が増していてもおかしくない。
そんなときに、私が『女』になっちゃってどうするのさ。
昼間のアレは、お前まで俺を困らせるのか、と眞人さんが思うには充分な状況だった。
「お前は、なんにもわかってないな。そんなわけ、ないよ」
「どうして断言できるのよ」
梅之介が、私の手を強く握る。
そんなに力を入れなくたって、さすがの私もはぐれたりしないのに。
「実際のお前は、犬なんかじゃない普通の女だろ」
私の方を見ることなく歩き続ける梅之介。
その声が怒っているように聞こえるのは、喧騒に負けないように少し大きな声で話しているからだろうか。
「『飼い犬』ですって名乗ってただけで、マルチーズやチワワに見える訳じゃない。その頭は、マルチーズみたいだけどな」
「うるさい」
開いた方の手で背中をポコンと叩く。梅之介は続けた。
「眞人が傍に置いてたのは、お前だってこと!」
首を傾げる。
向かいから、大学生らしき集団がやって来た。
酷く酔っ払っているみたいで、みんな大きな声で笑いあっている。
少し端に寄りながら、梅之介に言った。
「それは分かってるけど、梅之介の言いたいことはよく分かんない。分かりやすく言ってよ」
「お前を一番、『飼い犬』ってカテゴリに居させたがっていたのは多分…………」
すれ違いざま、ひときわ大きな笑い声が響いた。
「え? ごめん、聞こえなかった。なに」