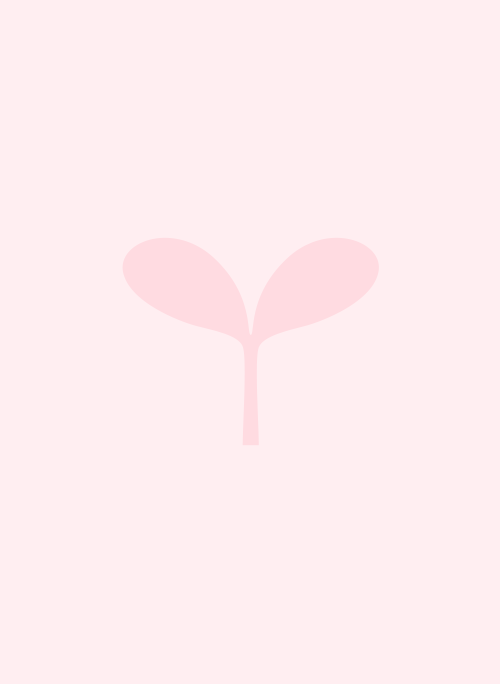店の中から零れる灯りに照らされた、男の人の顔を見た。
その人は、ひどくかっこいい顔をしていた。
切れ長の瞳は深い黒をしていて、すっと通った鼻梁はなだらかに高い。
形のいい唇に、少しの無精ひげ。
それらが精悍さとセクシーさを同居させるような最高のバランスで収まっていた。
私が正常だったら、見とれていたかもしれない。
本来だったら目を奪われてしまうほど、彼は私の好みに合致する素敵な顔立ちをしている。
だけど、今の私はどうしようもない空腹感に支配されていて、それどころではなかった。
「お、お金なら払います。だからお願いします。おかゆでも雑炊でもなんでもいいんで、あったかいものを食べさせてください! お腹空いてるし、寒いし、死にそうなんです!」
男の人は瞳を瞠って、私を見下ろした。
それは怒っているようにも見えるきつい眼差しで、普段の私だったら怖気づいてしまっていただろう。
が、先にも言った通りそんな状態ではない。
これを逃したら死んでしまうんじゃないかという気がしてきていた私は、必死で言葉を重ねた。
「住むところがなくなって、今夜行くところもないんです! お腹空いて、このままじゃ凍えて死んじゃうんです! だからお願いします。ご飯だけでも食べさせてください!」
涙と鼻水で、顔はぐしゃぐしゃ。
雪を充分浴びたお蔭でアフロな髪はちりちりウェーブになっていることだろう。
そんな女がこんな風に泣いて縋っているのは、思えば酷く恐怖なことだろう。
拒否されて当然だし、警察を呼ばれてもおかしくなかったかもしれない。
私はもっと冷静にお願いするべきだった。
だけど。彼は、私に言った。
「ちょっと、待ってろ」
「え?」
「見ての通り、店じまいなんだ。大したモンは作れねえけど、食わせてやる。その前に」
暖簾を抱えた彼は、そう言って店の中に入って行った。
すぐに、大きなビニール袋を何枚も持って戻ってくる。
「とりあえず、荷物にはこれを掛けとけ」
積もった雪を払い、ビニール袋を掛けてくれた彼が私を見た。
「ほら、中に入れよ。寒いんだろ?」
大きな手が店内を指し示す。
それに従うように店内に目をやれば、さっき香ってきたおだしの匂いが再び鼻腔を擽った。
深く息を吸って、温かな香りで肺を満たすと、お腹がぐるぐると鳴った。
その悲鳴のような音は彼の耳にも届いたらしく、彼は「ぶは」と吹き出した。
「すげえ飢えてんな。ほら、来いよ」
「は、はい!」
助かった。
安堵の涙が一筋流れたのを手の甲で拭って、私は示されるままに店内に入った。
温かな空気で満たされたそこはこじんまりとしていて、どこか安心できる雰囲気を持っていた。
古い建物らしいけれど、古臭さはない。丁寧に手入れされているのだろうと思う。
「ほら、ここ」
「あ、はい」
きょろきょろと見まわしていると、男の人が椅子を引いて座るよう促した。
懐かしさを覚えるダルマストーブの前だ。寒さでかじかんでいた私は、素直にそこに腰かける。
ストーブにはヤカンが乗せられていた。しゅんしゅんと音を立てるヤカンの口からは湯気が上っている。
「あったかい……」
じんじんと痺れる手を翳し、ほう、とため息をつく。
「コート、脱いで椅子に掛けとけよ」
厨房の方へ姿を消した彼から声がかかる。
肩口に手を置くとコートはぐっしょりと濡れそぼっていた。
うわ、こんなに濡れてたんだ。
「はい」
のたのたと脱いで、手近な椅子に掛ける。
すぐにストーブの前に戻り、再び手を翳した。
熱がゆっくりと体をほぐしてくれる。
ちらちらと揺れる炎が、心を穏やかにさせてくれる。
舞う炎をぼんやりと眺めていると、美味しそうな匂いが漂ってきた。
顔を厨房の方へ向けると、トレイを抱えた男の人が現れた。
その人は、ひどくかっこいい顔をしていた。
切れ長の瞳は深い黒をしていて、すっと通った鼻梁はなだらかに高い。
形のいい唇に、少しの無精ひげ。
それらが精悍さとセクシーさを同居させるような最高のバランスで収まっていた。
私が正常だったら、見とれていたかもしれない。
本来だったら目を奪われてしまうほど、彼は私の好みに合致する素敵な顔立ちをしている。
だけど、今の私はどうしようもない空腹感に支配されていて、それどころではなかった。
「お、お金なら払います。だからお願いします。おかゆでも雑炊でもなんでもいいんで、あったかいものを食べさせてください! お腹空いてるし、寒いし、死にそうなんです!」
男の人は瞳を瞠って、私を見下ろした。
それは怒っているようにも見えるきつい眼差しで、普段の私だったら怖気づいてしまっていただろう。
が、先にも言った通りそんな状態ではない。
これを逃したら死んでしまうんじゃないかという気がしてきていた私は、必死で言葉を重ねた。
「住むところがなくなって、今夜行くところもないんです! お腹空いて、このままじゃ凍えて死んじゃうんです! だからお願いします。ご飯だけでも食べさせてください!」
涙と鼻水で、顔はぐしゃぐしゃ。
雪を充分浴びたお蔭でアフロな髪はちりちりウェーブになっていることだろう。
そんな女がこんな風に泣いて縋っているのは、思えば酷く恐怖なことだろう。
拒否されて当然だし、警察を呼ばれてもおかしくなかったかもしれない。
私はもっと冷静にお願いするべきだった。
だけど。彼は、私に言った。
「ちょっと、待ってろ」
「え?」
「見ての通り、店じまいなんだ。大したモンは作れねえけど、食わせてやる。その前に」
暖簾を抱えた彼は、そう言って店の中に入って行った。
すぐに、大きなビニール袋を何枚も持って戻ってくる。
「とりあえず、荷物にはこれを掛けとけ」
積もった雪を払い、ビニール袋を掛けてくれた彼が私を見た。
「ほら、中に入れよ。寒いんだろ?」
大きな手が店内を指し示す。
それに従うように店内に目をやれば、さっき香ってきたおだしの匂いが再び鼻腔を擽った。
深く息を吸って、温かな香りで肺を満たすと、お腹がぐるぐると鳴った。
その悲鳴のような音は彼の耳にも届いたらしく、彼は「ぶは」と吹き出した。
「すげえ飢えてんな。ほら、来いよ」
「は、はい!」
助かった。
安堵の涙が一筋流れたのを手の甲で拭って、私は示されるままに店内に入った。
温かな空気で満たされたそこはこじんまりとしていて、どこか安心できる雰囲気を持っていた。
古い建物らしいけれど、古臭さはない。丁寧に手入れされているのだろうと思う。
「ほら、ここ」
「あ、はい」
きょろきょろと見まわしていると、男の人が椅子を引いて座るよう促した。
懐かしさを覚えるダルマストーブの前だ。寒さでかじかんでいた私は、素直にそこに腰かける。
ストーブにはヤカンが乗せられていた。しゅんしゅんと音を立てるヤカンの口からは湯気が上っている。
「あったかい……」
じんじんと痺れる手を翳し、ほう、とため息をつく。
「コート、脱いで椅子に掛けとけよ」
厨房の方へ姿を消した彼から声がかかる。
肩口に手を置くとコートはぐっしょりと濡れそぼっていた。
うわ、こんなに濡れてたんだ。
「はい」
のたのたと脱いで、手近な椅子に掛ける。
すぐにストーブの前に戻り、再び手を翳した。
熱がゆっくりと体をほぐしてくれる。
ちらちらと揺れる炎が、心を穏やかにさせてくれる。
舞う炎をぼんやりと眺めていると、美味しそうな匂いが漂ってきた。
顔を厨房の方へ向けると、トレイを抱えた男の人が現れた。