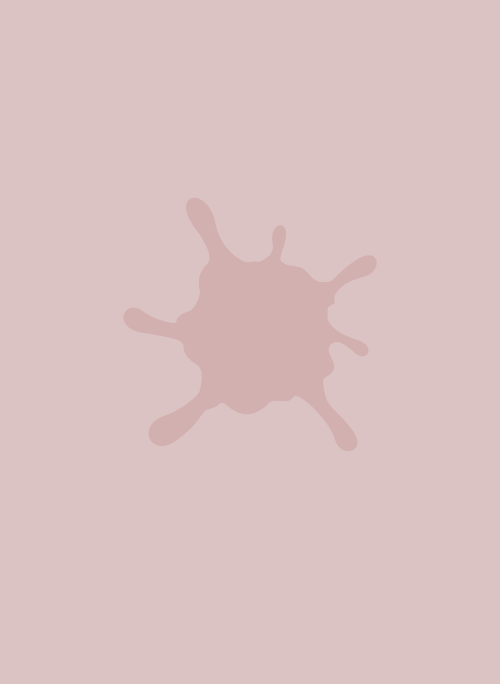「それより、これからどうすりゃいいんだよ」
蓮希が、両手で頭をかきむしる。
「とにかく、一刻も早く校舎から出よう。ここからだと、来客用の玄関が近いから、そこから出るんだ」
勇吾の提案に従い、杏奈たちは来客用の玄関を目指した。
まだ、勇吾は杏奈の手を握りしめてくれていたので、手のひらの温かさが、心強かった。
ほどなくして、来客用の玄関ホールが見えてきたので、杏奈はほっと息をついた。
勇吾の言う通り、校舎さえ出られれば助かる。
そう思いながら、来客用玄関へ近づくと、タイルの床になにかが転がっていた。
薄暗い灯りに照らされていたのは、初老の警備員だった。
顔の半分近くが食いちぎられており、おびただしい血で辺りが染まっている。
まるで血の海に沈んでいるようだった。
「うっ、うわあっ」
蓮希が亀のように首をすくめて、震える。
一花は口をおさえて、絶句していた。
杏奈は、冷たく汗ばんだ勇吾の手のひらを、ぎゅっとにぎりしめる。
蓮希が、両手で頭をかきむしる。
「とにかく、一刻も早く校舎から出よう。ここからだと、来客用の玄関が近いから、そこから出るんだ」
勇吾の提案に従い、杏奈たちは来客用の玄関を目指した。
まだ、勇吾は杏奈の手を握りしめてくれていたので、手のひらの温かさが、心強かった。
ほどなくして、来客用の玄関ホールが見えてきたので、杏奈はほっと息をついた。
勇吾の言う通り、校舎さえ出られれば助かる。
そう思いながら、来客用玄関へ近づくと、タイルの床になにかが転がっていた。
薄暗い灯りに照らされていたのは、初老の警備員だった。
顔の半分近くが食いちぎられており、おびただしい血で辺りが染まっている。
まるで血の海に沈んでいるようだった。
「うっ、うわあっ」
蓮希が亀のように首をすくめて、震える。
一花は口をおさえて、絶句していた。
杏奈は、冷たく汗ばんだ勇吾の手のひらを、ぎゅっとにぎりしめる。