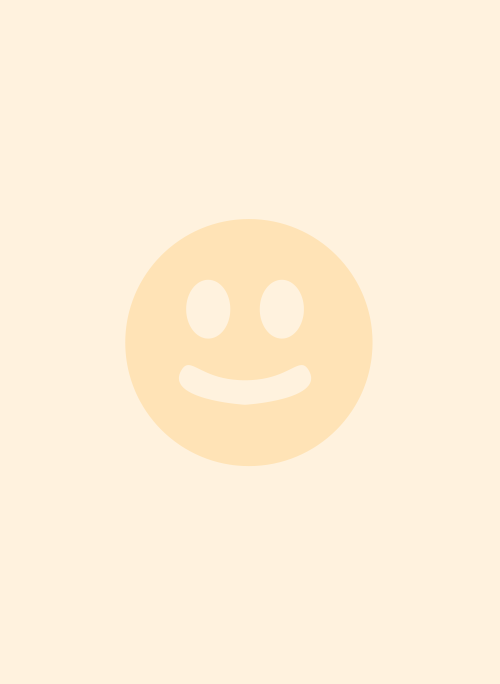その日は、特にこれといって変わった出来事はなかった。
男は田畑を耕しに、女は川へ洗濯に、魔法士は土肥やしの魔法陣を描きに外にでて行く。
そして1日の仕事を終え、疲れた体を休めに、男たちが家に帰ってきた夕暮れ時。
そこへ、あの奇妙な集団がやってきたのだ。
全身を白い布で包み、体を覆い隠した者たちが、夕闇が集落を覆うと同時に現れたのである。
形の定まらない、黒い“なにか”を身に纏って。
「ほほほ……」
貴婦人のような笑い声を上げ、その“黒いもの”は突然に集落を襲った。
田畑を潰し、井戸を壊し、家を焼き払い……あろうことか、神と奉られている大地の祠までをも破壊したのだった。
無論、崇拝対象まで破壊されて、誇り高き一族が黙っているはずはない。
女子供までもが刀を携え、ぎらりと目を光らせて、白布の者たちに斬り掛かった。
しかし魔法を使えぬ民は、みなことごとく“黒いもの”に呑み込まれ、そこには白骨のみが残った。
それどころか、土遁の魔法士でさえ、彼らの妖しい術をはねのけることはできなかった。
彼らの操る“黒いもの”は、全てを飲み込み、跡形もなく消しとばす。
「命乞いをしろ。
そうすれば助けてやってもいい」
彼らの先頭に立った白布の男は、静々とそう言っていた。
……その傲岸不遜な言葉が、少年の耳にこびりついていた。
少年はこの集落の長の長男坊だった。
剣術の腕にも優れていたが、少年には魔法士の才もあった。
魔法士の数だけ、村は豊かになる。
少年は魔法士になることを選んだ。
魔法士を志願する者は、みな中央都市までの旅に出て、一人前になって帰ってくることを義務とされる。
魔法士なにるための決まりに倣い、少年は15歳になったこの日に、旅に出ることを決意していた。
あの白布の者たちに襲撃されたのは、ちょうど、少年が旅に出ようと馬に跨った直後である。