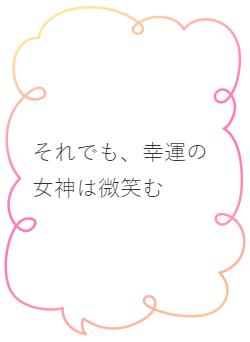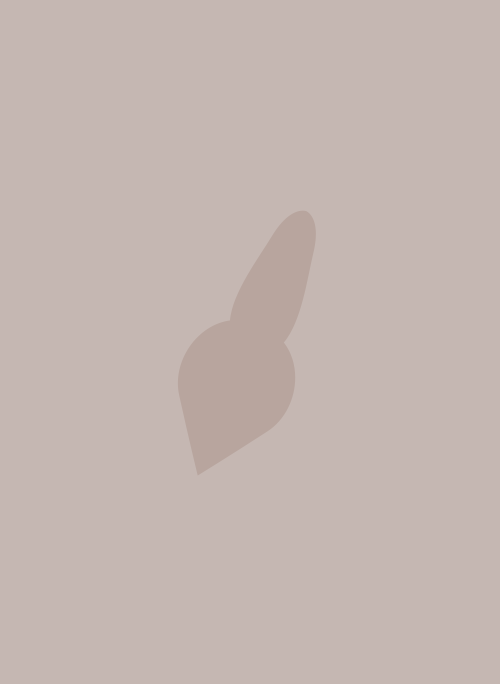「――――愛してたのよ。
おそらくだけど。
そう、愛してたのよ、あたしはあの人を。
あの人はあたしを。
愛してたはずだったのに・・・・・・。
一体何をどう間違えたのかしらね?
狂おしいほどまでに愛してたはずだったのに。
一体いつ、想いは歪んで薄れて、消えてしまいそうなほどに儚くなってしまったのでしょうね?
愛してたわ。
好きだった。
その思いに偽りはないはずよ。
けれど――おそらく、忘れてしまったのでしょうね、あたしもあの人も。
お互いを愛すことを、忘れてしまったのよ。
愛し合っていたあの頃を、忘れてしまったのよ。
だから、お互いに違う人に想いを寄せたの。
うぅん―――それのどこがいけなかったのかしらね?
イマイチよく分からないわ。
どうしてそのことで、何にも知らない世間様にヒソヒソ嫌味を言われなくちゃならないの?
わっからないのよねぇ・・・。
そりゃあ、やっぱりきちんと離婚してから次を探すべきだったとは思うわよ?
子供を放ったらかしにしてたのも、悪かったとは思うわよ?
でも、どうして世間様に嫌味を言われなくちゃならないのかが、分からないのよ。
子供に嫌味や文句を言われるのならまだしも、ね。
うぅん―――本当、分からないわ。
世間様は、お暇なのね、きっと。」
そう言い、彼女はにっこりと好戦的に笑った。