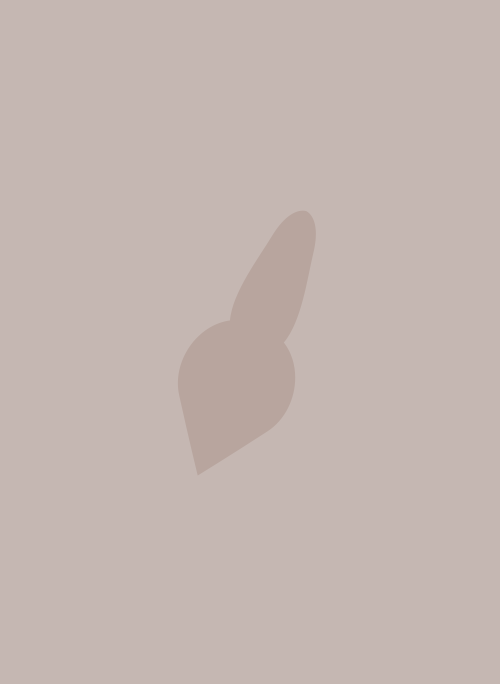「……」
しばし呆然としていたパイセン先輩。
「俺、実は今まで義務感みたいなもので彼女といて…
その、彼女は俺のこと異常なほど愛してくれてるんです。
でもいまいちわからなくて、そーゆーの。
彼女の死んだ兄の変わりにって、ただ…それだけだったんで」
必死に現状をわかってもらいたくなった。
ひたすら言い聞かしてきた、千晶は大事、千晶は好き。
それはほぼ自己暗示だった。
「……」
また考えて。
「…少なくとも、さっきの嬉しそうなテンションじゃ、俺はお前が彼女を愛してると見た」
「…っ」
真面目っぽいのが照れ臭いのか、カウンターの醤油の量をちょろっと確認したりする先輩。
「しかも、長い間いるんだろ?
さすがに一切愛してなきゃ、愛が伝わってなきゃ――彼女はお前から離れてるはず。
女っちゅーのはそーゆーのに敏感だしよ…って体がとかじゃねーぞ、変態くん」
いいのが台無し。
お前がだよ、と何人がツッコミを入れたろうか。
「あと、義務感とか言ってるのは失礼だと思うし、言い訳にしか聞こえねーなーって思った」