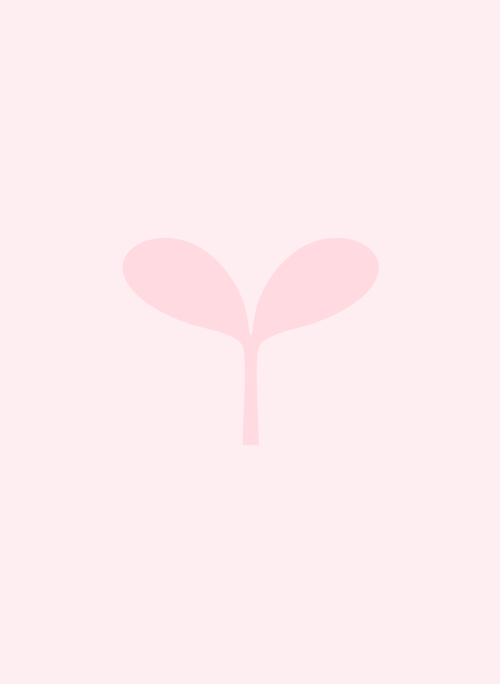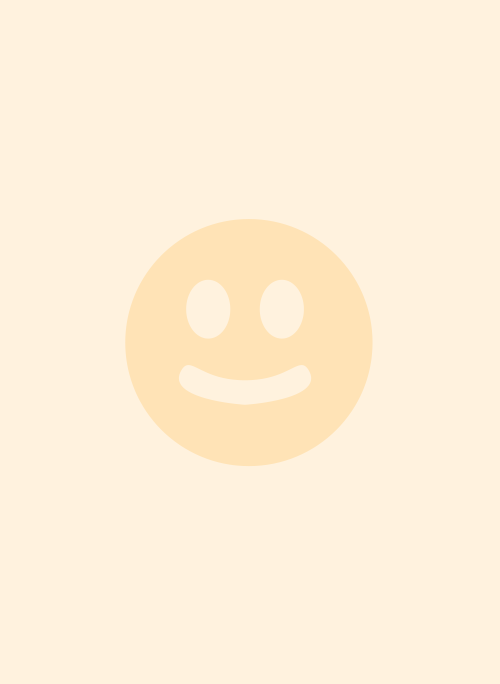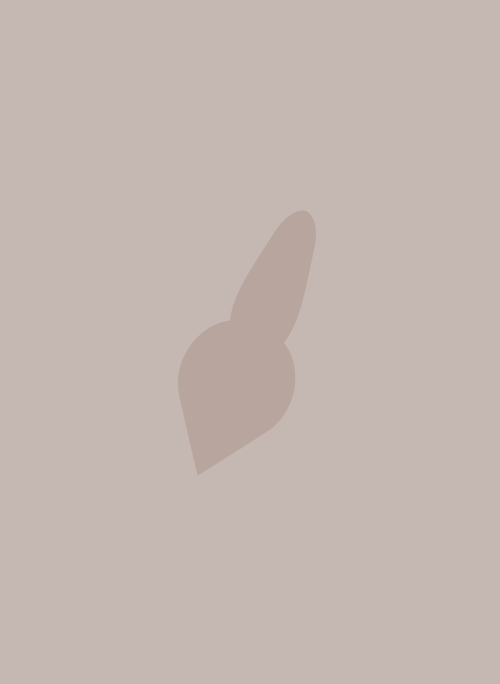「……」
何なんだ。
ちらりと後ろを見た少年は、無言で歩く速度を速めた。
《ケケケケケケケケケ》
人を馬鹿にしたような不気味な音を発し、少年の後をついてくるヤツ。
その存在を確認した少年は、ついてくるな!!と叫びたい衝動を押しとどめて、帰路を急いだ。
きっとヤツ等が視えるのは生まれつきだった。
ある業界では天才、選ばれし者などと称されるその体質は、少年にしてみれば迷惑なものだ。
少年が‘ヤツ等’と称するのは、世間一般で言う‘妖怪’。
人間を軽く超える外見のユニークさを持ち、個性に満ち溢れているヤツ等。
小さく、名前も持たない、いわゆる雑鬼と一纏めに呼ばれるモノ達くらいの低級なモノなら、それこそそこら中を闊歩している。
それは建物の中も例外ではない。
よく、妖怪は夜活動する。と言うが、昼間でも堂々と出現する。
何度、学校で叫びそうになったことか。
最近では、人ごみの中にヤツ等が紛れていようと、ヤツ等が人の体を通り抜けようと、無視が出来るようになってきたのが唯一の救いだろう。
しかし。
《ケケケケケケケケケケ》
「だぁーもう!!ついてくるなよっ!!」
無視をしていても絡んでくるヤツ等が後を絶たないのもまた事実。
イラつきがピークに達した少年は、自宅の庭に入るや否や、ぐるんと180度方向転換して怒鳴りつけた。
《ケケケヶ…》
先ほどから、《ケケケ》としか発さない目の前の黒くて丸い、猫ほどの大きさの毛玉は、しゅんとして動かなくなった。
…と言っても、全身が真っ黒な毛で覆われているため、顔が何処にあるのかさっぱり分からないので、声色で判断するしかなかったのだが。
「…お前、俺に何か用か?」
《…ケケ》
「……理解不能」
《…ケ》
「…はぁ。これじゃあ、らちが明かないな」
言葉を話せないのだろうか。同じ言葉を発し続けるヤツにため息を吐く。人語を理解しない個体が多いことも事実だが…
「少しジッとしてろよ」
足元に転がっている毛玉を見下ろしていた少年だったが、しゃがんで毛玉に手を伸ばした。
《ヴーッッ》
「大丈夫」
全身の毛を逆立てて威嚇してくる毛玉に微笑んでみせた。