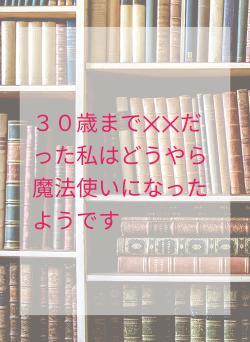「うん。小学校の頃好きな子がいたんだけど、一緒にいると気分が悪くなったり、呼吸困難になって倒れたりしたの」
「それって、ただの偶然じゃなくて?」
あたしは左右に首を振り、そんなことが何度か起こったことを説明した。
「だけど、俺のときにはそのアレルギーだ出なかった?」
あたしはうなづく。
すると、船見くんの手がするりと離れて行った。
きっと嫌われたんだ。
こんな変な体質だし、アレルギーが出なかったから一緒にいたのだと思われてしまった。
目の奥がツンッと痛くなって視界が滲んだ。
涙が幕のように張って周囲が歪んで見える。
後ろに立っている船見くんは何も言わず、どんな顔をしているのかもわからない。
だけどきっと幻滅された。
研司があたしから遠ざかったのだって、納得できる。
あたしだって、こんな体質の人が恋人なんて嫌だから。
やがて、雨がぽつぽつと降り始め、それはあっという間に地面をぬらしていく。
「もう、帰らなきゃね」
あたしは振り向かずに声をかけ、お気に入りの傘を差すこともなく、公園を出たのだった。
「それって、ただの偶然じゃなくて?」
あたしは左右に首を振り、そんなことが何度か起こったことを説明した。
「だけど、俺のときにはそのアレルギーだ出なかった?」
あたしはうなづく。
すると、船見くんの手がするりと離れて行った。
きっと嫌われたんだ。
こんな変な体質だし、アレルギーが出なかったから一緒にいたのだと思われてしまった。
目の奥がツンッと痛くなって視界が滲んだ。
涙が幕のように張って周囲が歪んで見える。
後ろに立っている船見くんは何も言わず、どんな顔をしているのかもわからない。
だけどきっと幻滅された。
研司があたしから遠ざかったのだって、納得できる。
あたしだって、こんな体質の人が恋人なんて嫌だから。
やがて、雨がぽつぽつと降り始め、それはあっという間に地面をぬらしていく。
「もう、帰らなきゃね」
あたしは振り向かずに声をかけ、お気に入りの傘を差すこともなく、公園を出たのだった。