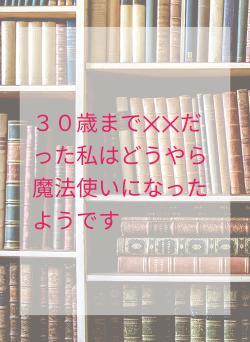歩くたびに綾の茶色い髪の毛が揺れて、シャンプーの香りがする。
備え付けのシャンプーは使わなかったのか、それは俺とは違う香りだった。
ギュッと握られた手からは綾の温もりを感じて、自分の鼓動が少しずつ早くなるのを感じていた。
いつからだろう。
綾の事を幼馴染以上だと思い始めたのは。
気が付けば俺の目は綾を追いかけていた。
だけど、俺はこの気持ちを綾に伝える気はなかった。
お互いに大きな企業の子供だと理解している。
綾は綾で、俺は俺はで定められた相手がいるのだ。
「え、これだけしかいないの?」
綾の言葉に我に返ると、いつの間にか広間に到着していた。
しかし、そこにいたのは数人の生徒たちだけだった。
さっき廊下で見た生徒を合わせても10人くらいしかいない。
「先生たちは?」
俺は集まって来た生徒たちへ向けてそう聞いた。
備え付けのシャンプーは使わなかったのか、それは俺とは違う香りだった。
ギュッと握られた手からは綾の温もりを感じて、自分の鼓動が少しずつ早くなるのを感じていた。
いつからだろう。
綾の事を幼馴染以上だと思い始めたのは。
気が付けば俺の目は綾を追いかけていた。
だけど、俺はこの気持ちを綾に伝える気はなかった。
お互いに大きな企業の子供だと理解している。
綾は綾で、俺は俺はで定められた相手がいるのだ。
「え、これだけしかいないの?」
綾の言葉に我に返ると、いつの間にか広間に到着していた。
しかし、そこにいたのは数人の生徒たちだけだった。
さっき廊下で見た生徒を合わせても10人くらいしかいない。
「先生たちは?」
俺は集まって来た生徒たちへ向けてそう聞いた。