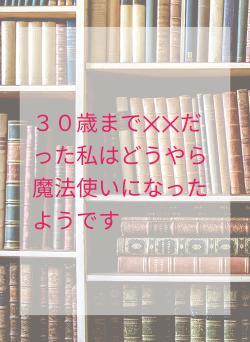しかし、それに返事を返す人は誰もいなかった。
一寸先も見えない闇に消えていった澪がどうなったのか誰も想像もつかない。
「もし、外へ出られたならきっと、誰かを呼んできてくれるよ」
その場の雰囲気を明るくするように、優志が言った。
「そ、そうだよね! 真っ暗っていっても下は線路なのはわかってるし、歩いていけば明かりも見つかると思うし!」
あたしは優志の言葉に何度も頷きながらそう言った。
どうであってほしいという、願いも込めて。
「でも、澪の足音は聞こえてこなかったわ」
愛奈があたしの期待を砕くようにそう言った。
あたしの心臓はドクンッと跳ねる。
石が敷き詰められている線路を歩いていれば、普通足音が聞こえてくるはずだ。
電車が下りただけでも、聞こえてくるその音が聞こえてこなかった事を思い出す。
「……とにかく、澪に期待して待つしかないんじゃないかな?」
旺太が穏やかな口調でそう言った。
嫌な予感はぬぐえないけれど、今外へ出たのは澪1人なのだ。
その澪にかけるのは普通の事だった。
「じゃぁ、澪が帰ってくるまで俺たちはもう1度電車の中を調べよう」
優志がそう言ったので、あたしたちはようやく動き始めたのだった。
一寸先も見えない闇に消えていった澪がどうなったのか誰も想像もつかない。
「もし、外へ出られたならきっと、誰かを呼んできてくれるよ」
その場の雰囲気を明るくするように、優志が言った。
「そ、そうだよね! 真っ暗っていっても下は線路なのはわかってるし、歩いていけば明かりも見つかると思うし!」
あたしは優志の言葉に何度も頷きながらそう言った。
どうであってほしいという、願いも込めて。
「でも、澪の足音は聞こえてこなかったわ」
愛奈があたしの期待を砕くようにそう言った。
あたしの心臓はドクンッと跳ねる。
石が敷き詰められている線路を歩いていれば、普通足音が聞こえてくるはずだ。
電車が下りただけでも、聞こえてくるその音が聞こえてこなかった事を思い出す。
「……とにかく、澪に期待して待つしかないんじゃないかな?」
旺太が穏やかな口調でそう言った。
嫌な予感はぬぐえないけれど、今外へ出たのは澪1人なのだ。
その澪にかけるのは普通の事だった。
「じゃぁ、澪が帰ってくるまで俺たちはもう1度電車の中を調べよう」
優志がそう言ったので、あたしたちはようやく動き始めたのだった。